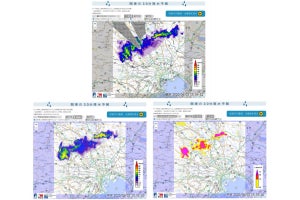科学技術振興機構(JST)は7月28日に、JST理事長記者説明会を開催し、2月に公表した「令和2年度創発的研究支援事業」(2020年度分)に採択された研究の中で注目を集めている「人工冬眠」の研究開発計画について解説した。
令和2年度創発的研究支援事業によって7年間にわたる研究開発テーマに選ばれた人工冬眠のテーマは、理化学研究所生命機能科学研究センターの砂川玄志郎(すながわげんしろう)上級研究員が人工冬眠療法などの実現を目指して研究開発を進めているものだ。
砂川上級研究員は、2019年度から理研生命機能科学研究センター内に「QMINプロジェクト」を設けて、哺乳類の冬眠現象の仕組みを調べ、将来的には人工冬眠療法の実用化を図るために基礎研究を始めてきた。
もし将来、人間の人工冬眠が可能になるとすれば「病人患者の疾患進行の抑制や救急車などでの医療搬送、全身麻酔の代替技術、対象組織の保存などが可能になる」と砂川上級研究員は、人工冬眠技術の人への応用の未来像を説明する。
また、砂川上級研究員は「2004年から2006年まで、小児科医・救急医として小児麻酔や救急医療、集中治療に従事した際に、人工冬眠技術があれば酸素供給が少なくても対処できる医療の可能性に気付いていた」と、人工冬眠研究を始めた動機を説明。
直接的なきっかけは「クマやリスなどの哺乳動物が冬眠する現象以外に、ハツカネズミなどの哺乳動物も日内休眠(Daily torpor)という数時間の休眠をする現象に着目し、哺乳類は日内休眠をする仕組みを持っていることに気が付いたこと」という。
そして、この日内休眠時には、体温が10℃以下になり、代謝が低下する現象を見出し、この代謝が低下する現象時は体内の酸素の消費量が落ちていることを発見した。
砂川上級研究員は「人間(などの哺乳類)はふだんの活動は代謝の需要と供給が均衡している状態と考え、人間が病気などの際に消費するエネルギー供給が障害を受けても、人工冬眠が可能になれば、エネルギー需要を抑制でき、その時点でのエネルギー収支を平衡に保てると推定して、人工冬眠技術の実用化を目指している」という。
現在は、マウスを使った休眠実験として「マウスの飢餓性休眠」(Fasting-induced Torpor)の研究を進めており、飢餓性休眠時のマウスは熱産生感度を低下させていることが分かり始めているとした。
そして、「神経誘導性低代謝のマウスを用いた実験から(ヒトを含めた)哺乳類の冬眠誘導が可能かどうかを研究している」と説明する。(注)
現在は“冬眠モデルマウス”で、哺乳類の組織内での低代謝適応の原理を解明中だという。
今後については「低代謝適用による疾患進行抑制を検証する」という研究開発計画を進めているとするほか、「ヒト組織に低代謝適応機構を実装化し、その先にある人工冬眠による治療法実現につなげたい」と説明する。そして「2040年ごろにはヒトでの短時間睡眠の実現を目指す未来像を描いている」という。
(注)
動物などの体内では、アデノシン三リン酸(ATP)から ADP(アデノシン二リン酸)とリン酸基に分かれる際に放出されるエネルギーが生体内での主要なエネルギー源となっている。冬眠はこの基本的な反応を若干変えていると推定されている。