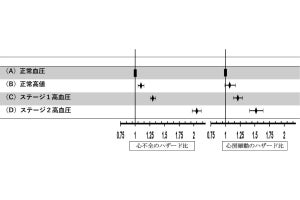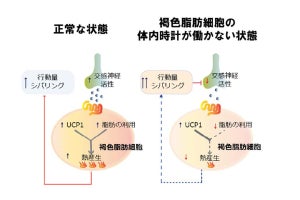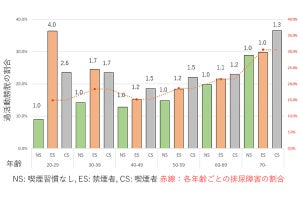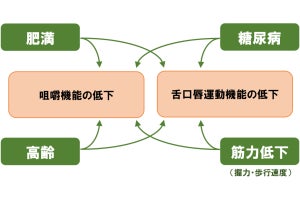大阪大学(阪大)は6月17日、マグネシウムが日々の活動期における血圧上昇を抑制する仕組みを解明したと発表した。
同成果は、阪大 微生物病研究所 環境応答研究部門 細胞制御分野の船戸洋佑助教、同・三木裕明教授らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。
ヒトをはじめとする多くの生物が生命活動を維持するためにさまざまな微量な元素を必要としている。マグネシウムもその1つで、細胞内では2価の陽イオン「Mg2+」として存在し、“エネルギーの通貨”などと呼ばれる「アデノシン三リン酸(ATP)」などと結合し、数多くの生体内化学反応に関わることが知られているほか、免疫にも関わっていることも知られており、その摂取不足はさまざまな疾患の発症リスクを高めることが、疫学的な調査研究から明らかにされている。中でも、高血圧と深く関わりがあることは以前から知られていたが、その具体的な作用機構についてはまったくわかっていなかったという。
そのような背景を受けて研究チームは今回、マグネシウム再吸収に関わるイオンチャネル「TRPM6」を、腎臓において特異的に遺伝子ノックアウトしたマウスを作成して観察を行ったところ、日々の活動期で見られる血圧上昇が起こらなくなることが確認されたという。
-
1日を通しての1時間ごとの収縮期血圧(左)と拡張期血圧(右)。通常、マウスは活動期に入ると血圧が上昇するが(黒丸)、腎臓特異的TRPM6遺伝子ノックアウトマウスでは血圧上昇が見られなくなり(白丸)、血圧変化の概日リズムが消失することが確認された (出所:阪大Webサイト)
分析の結果、その原因は血圧上昇を起こすホルモンである「レニン」の分泌が妨げられているためであることが判明。TRPM6が発現しているのは、腎臓の糸球体で血液からこし出された原尿が通過していく尿細管の末端に近い「遠位尿細管」で、遠位尿細管はマグネシウム再吸収の起こる場であるとともに、レニンを分泌する「傍糸球体細胞」に隣接しており、これらの細胞間でなんらかの情報のやり取りが行われていることが考えられるという。
-
腎臓の中でのレニン分泌細胞とTRPM6発現細胞が隣接している様子。レニン(緑)とTRPM6(赤)の二重蛍光染色によって、レニンを分泌する傍糸球体細胞が、TRPM6を発現する遠位尿細管の末端部に隣接して存在していることが見て取れる (出所:阪大Webサイト)
実際に、傍糸球体細胞からのレニン分泌を促す腎交感神経を外科的に除去したり、レニンの働きを阻害する降圧薬アリスキレンを投与したりすることによって、活動期の血圧上昇が強く抑制されることを確認。レニンの分泌の重要性が示されたとする。
また、内在性TRPM6の発現はマグネシウムの影響を強く受けており、通常の倍のマグネシウムを含む食餌で飼育すると、TRPM6の発現が低下することが判明。さらに、この高マグネシウム食摂取マウスでは、TRPM6ノックアウトマウスと同様に活動期の血圧上昇が見られなくなったという。
研究チームは、今回の研究成果により、マグネシウムと血圧調節を結ぶ、まったく新たな様式の血圧調節機構が発見されたことで、高血圧の病態の解明や新たな治療薬の開発などにつながることが期待されるとしている。