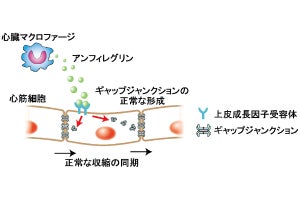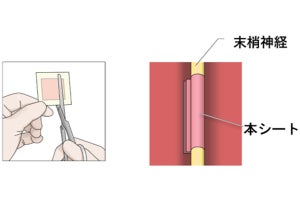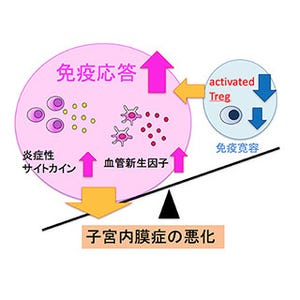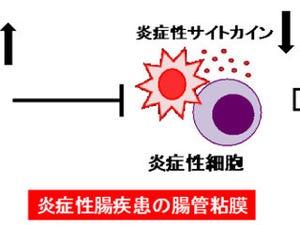神戸大学は4月23日、「遠心性収縮モデルマウス」を用いて、肉離れなどの重い筋損傷に対するアイシングが筋再生を遅らせることを明らかにしたと発表した。またこの現象に、「炎症性マクロファージ」の損傷細胞への浸潤度が関与する可能性を明らかにしたことも合わせて発表された。
同成果は、神戸大 大学院保健学研究科の荒川高光准教授、川島将人大学院生(当時)、千葉工業大学の川西範明准教授らによるもの。詳細は、応用生理学を題材とした「Journal of Applied Physiology」に掲載された。
肉離れなどの骨格筋損傷は、微細なレベルから重大なレベルまで実は頻繁に生じているという。しかも、学校の体育の現場、スポーツの現場などだけでなく、事故や災害による外傷などでも多く発生している傷害とされる。
その障害の程度に関わらず、骨格筋損傷が疑われる際に必ず行われるのが「RICE(ライス)」と呼ばれる処置だ。これは、英語の「Rest(安静)」、「Icing(アイシング)」、「Compression(圧迫)」、「Elevation(挙上)」の頭文字を取った処置法のことだ。
RICEは体育やスポーツ、医療の現場でも常識化している処置で、とりわけアイシングはどのような筋損傷であれよく実施されている。損傷の度合いによらず、肉離れなどの出血を伴わないようなケガの場合、とにかくアイシング、というのが常識となっている。しかし、その長期的な効果は不明なところが多く、ほぼ炎症反応の抑制のために用いられているのがこれまでのところだった。
この炎症反応をアイシングして抑えることはよいとされてきたが、近年、実は組織損傷後に起こる炎症は正常な回復の一過程であり、組織の再生にとって重要な反応であることが明らかになってきた。つまり、アイシングで炎症を抑制してしまうと再生を阻害してしまう可能性があるという。
ただし、これまでの筋損傷後にアイシングを施す実験では、筋再生が遅れたという報告もあれば、筋再生を阻害することはなかったという報告もあり、どちらが正しいのかわからない状態だったという。いえることは、これまでの研究では、スポーツ現場で起こるような、筋が収縮して起きてしまう筋損傷に対するアイシングの効果は、検討されてこなかったということだという。
そこで研究チームは今回、重度な肉離れに近い筋損傷を起こせる遠心性収縮モデルマウスを用いて実験を行ったという。具体的には、電気刺激によって強制的に筋を働かせている間に、その運動とは反対方向に、より強い力で足関節を運動させ、損傷を引き起こした筋を採取。筋損傷部に対するアイシングを行い、筋損傷をさせないマウス群と比較する形で行われたという。
損傷2週間後に再生骨格筋の観察が行われた結果、アイシングされた群はアイシングされていない群に比べて、横断面積の小さい再生筋の割合が有意に多いことが確認されたという。これは、アイシングによって骨格筋の再生が遅延している可能性があることを示すものであるという。
-
筋損傷2週間後の筋線維横断面と横断面積ごとの分布。(上)筋損傷後に無処置の動物の2週間後(non-icing Day 14)と、アイシングが施された動物の2週間後(icing Day 14)の筋横断面画像。(下)筋線維横断面積ごとの分布(%)。アイシングを施すと(黒四角)、2週間後、再生した筋線維は横断面積の小さい(細い筋線維が多い) (出所:神戸大Webサイト)
白血球の一種である「マクロファージ」には、炎症性と抗炎性の2種類があることが知られている。体内の組織が損傷した際、その急性期に損傷部に集まってくる細胞たちのことを「炎症細胞」というが、その代表格が炎症性マクロファージとされる。炎症細胞というと悪いイメージがあるが、決して悪い細胞というわけではなく、損傷筋の再生過程で炎症細胞が集まってくる目的は、たとえば炎症性マクロファージの場合は、損傷部位にある壊れた筋を貪食し、そこに新しい筋を作れるようにすることだという。
しかしアイシングをすると、損傷した筋細胞の中に炎症性マクロファージなどの炎症性細胞があまり入っていかない(到着が遅れる)ことが、今回の実験で明らかとなったという。
-
(左)筋損傷後の損傷筋細胞内に炎症細胞が入っている割合(%)。無処置(non-icing)が白、アイシング(icing)が施されたものが黒。アイシングが施された動物はどの時点でも、損傷した筋に炎症性細胞があまり入っていない。(中央と右)筋損傷後の炎症性、抗炎症性マクロファージの分布。(中央)無処置(non-icing)、アイシング(icing)における筋横断面。炎症性マクロファージ(白の矢印)、抗炎症性マクロファージ(白の矢頭(△))の分布を損傷3日後(Day 3)、5日後(Day 5)で比較されたもの。アイシングが施された筋で3日後、マクロファージの集まりが悪いが、5日後には集まっている。(右)炎症性マクロファージの視野における数の平均。アイシングを行うと、炎症性マクロファージが早期に損傷筋に集まっていない。遅れて5日後、7日後に炎症性マクロファージが観察されたという (出所:神戸大Webサイト)
炎症性マクロファージは貪食を終えると、抗炎症性マクロファージに特性を変化させると考えられている。抗炎症性マクロファージは、炎症性マクロファージとは真逆の炎症反応の抑制を行い、組織修復に向かわせる物質の放出も行うといわれているが、今回の研究結果により、遠心性収縮による重い筋損傷のあとにアイシングを施すと、炎症性マクロファージによる損傷筋の貪食が十分に行われず、それが原因で新しい菌細胞の形成が遅れる可能性が示されたとする。
研究チームによれば、今回のようにアイシングを施すと回復が遅くなる重い筋損傷がある一方で、アイシングを施してもよい程度の軽微な筋損傷が存在する可能性も否定できないという。その線引きを今後の課題とし、現在、軽微な筋損傷に対するアイシングがどのような影響を与えるのかを検討中としている。また、今後は筋損傷の度合いに合わせたアイシングの施し方などの検討を進めていき、スポーツ現場や臨床のリハビリテーションにおけるアイシングのぜひについて、正しい判断を行うための材料を提供するとしている。