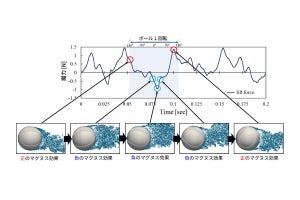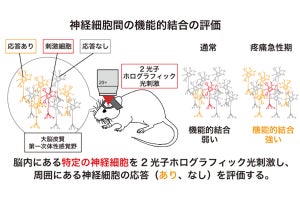東京農工大学(農工大)は3月23日、「ホログラフィック・コンタクトレンズディスプレイ」の開発に成功したと発表した。
同成果は、農工大大学院 工学研究院 先端電気電子部門の高木康博教授らの研究チームによるもの。詳細は、米光学会刊行の学術誌「Optics Express」に掲載された。
SF映画などにガジェットとして登場するコンタクトレンズ型のディスプレイは、究極のディスプレイ技術として研究されており、その多くが液晶ディスプレイやLEDをコンタクトレンズに内蔵する方向で、デバイス分野を中心に開発が進められている。
コンタクトレンズディスプレイは、その小ささや、そして球面であることなども開発の容易ならざる部分ではあるが、最大の課題は実はそこではない。コンタクトレンズ内に表示された画像に対して、目がピントを合わせられないという、使用者が対応できないことが最大の課題となっている。そのため、現在は画像表示は断念。グルコースセンサや無線デバイスを内蔵した血糖値を測定できるスマートコンタクトレンズの開発が先行して行われているという。
コンタクトレンズにディスプレイを内蔵しても、目はディスプレイにピント合わせできず、網膜に像を結ぶことができない。この問題を解決するため、以前はLEDにマイクロレンズを取り付けて、網膜に光を集光する方法が考えられていた。しかし、それはそれで、目が外界の物体にピントを合わせると目の焦点距離が変化するため、光の集光がうまくいかなくなる問題を抱えていたという。
-
ホログラフィック・コンタクトレンズディスプレイの原理。(a)コンタクトレンズ内のディスプレイに映像を投影した場合は、目がピントを合わせられない。(b)LEDにマイクロレンズを組み合わせれば、目はディスプレイの映像を見られるが、外界の物体にピントを合わせると焦点距離が変化するため、光の集光がうまくいかなくなることがある。(c)今回提案された方式。ホログラフィー技術を応用することで目が自然とピントを合わせられるようになる (出所:農工大Webサイト)
そこで今回の研究では、ホログラフィ技術を用いることが提案された。ホログラフィは、物体から発せられる光の波面を発生することで、立体表示を行う。目から離れた位置にある物体からの波面をコンタクトレンズ内の表示デバイスで発生することで、目が立体像に対して自然とピントを合わせられるようになるのだ。ホログラフィ技術を用いてCGの表示も可能なことから、さまざまな画像を表示することが可能になる。
今回提案されたホログラフィック・コンタクトレンズディスプレイの構造だが、レンズの厚さは一般に0.1mm程度と薄いため、そこに軽薄短小な装置を内蔵できるかどうかが実現の鍵となるという。
実現困難なイメージだが、現代の技術を用いれば、ホログラム表示を行う「位相型空間光変調器」や、光の偏光を制御する「偏光子」を数μm厚で実現することは可能だという。
今回の研究では、位相型空間光変調器をレーザー照明するバックライトの厚さを、「ホログラフィック光学素子」を用いることで0.1mm程度にすることに成功。原理確認実験で、実際の風景に、ホログラム技術で発生した画像として文字「AR」を重ねてAR表示がなされていることが確認された。
なお今回の技術は、コンタクトレンズディスプレイの光学技術に関する課題を解決するものとしているが、実用化に向けては、電力をどのように供給するかといった点など、まだまだ解決すべき課題があるという。そのため、今後は表示デバイスや通信デバイスに関する研究者や眼科の医師などの協力を得て、コンタクトレンズディスプレイの実用化に向けて研究をさらに進めていきたいとしている。