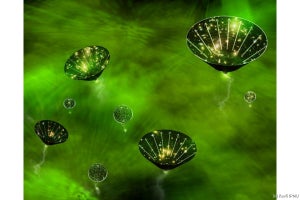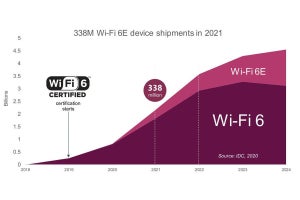東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)ならびに国立天文台は、コンピュータ上の仮想宇宙の銀河データを用いて、データ作成者と解析者を完全に分離した「宇宙論チャレンジ」を行い、物理解析の手法で宇宙の誕生と進化を支配する「宇宙論パラメータ」を正しく測定することができるか検証を実施したことを発表した。
同成果は、日本からは京都大学 基礎物理学研究所の西道啓博特定准教授(兼Kavli IPMU 客員科学研究員)、Kavli IPMUの高田昌広主任研究者らが参加したほか、加えて米・スタンフォード大学、米・ニューヨーク大学、CERN(欧州原子核研究機構)、米・プリンストン高等研究所、中国科学技術大学の研究者が参加した国際共同研究チームによるもの。詳細は、米物理学専門誌「Physical Review D」にオンライン掲載された。
宇宙論パラメータとは、宇宙の誕生から現在までを物理法則に従って記述する「宇宙モデル」の性質を決める基本的な物理パラメータのことだ。「宇宙の標準モデル」とされるのが、「ΛCDM(ラムダシーディーエム)モデル」だ。Λは、ダークエネルギーとしてアインシュタインの宇宙定数Λ(ラムダ)を表す。そしてCDMとは、ダークマターとして温度が無視でき、重力以外の力をまったく感じない冷たいダークマター(Cold Dark Matter = CDM)のことだ。ΛCDMモデルは、この2つを仮定しており、宇宙マイクロ波背景放射(CMB)を初めとする、多数の観測事実を矛盾なく説明する現代の標準モデルと考えられている。
ΛCDMモデルには6つの宇宙論パラメータが含まれる。宇宙の全エネルギーに対してダークマターなどの諸成分が占める割合、ダークエネルギーが関与する宇宙の膨張速度、宇宙初期に生み出された「原始揺らぎ」の大きさや距離依存性などだ。
この宇宙論パラメータの範囲について、ここ10年余りの観測技術の飛躍的進歩と、そこから得られる多様な観測量を解釈する理論研究の発展のおかげで、絞り込みが進んでおり、今や「精密宇宙論」と呼ばれる域に達しているという。
観測データが質的にも量的にも向上するのに応じて、理論研究者側に求められる予測の正確性も大変シビアなものとなってきているとされる。観測によって得られたデータを分析し、宇宙の謎に対する新たな知見を引き出すためには、物理理論に基づき、宇宙の構造進化に対して正確な予測を与える必要があるからだ。
今後、さらに観測が大型化し、データは増えていくと予想されている。そこで重要となってくるのが、膨大な観測データから正しく宇宙論パラメータを引き出す解析手法自体の精度を担保することだという。
しかしこれまでは、すでに別の観測で得られている宇宙論パラメータに近い値を解析者が先入観から信用してしまう「確証バイアス」が問題とされてきた。さらに、1つの解析手法に対して、限られた種類の宇宙データでしか検証がなされていなかった。そのため、その手法がどのような宇宙データに対しても普遍的に適用できるかどうかの検証は十分に行われていなかったのだという。
こうした背景を受けて、コンピュータ・シミュレーションによって作られた模擬的な宇宙について、どれだけ宇宙論パラメータを正確に求められのかという新しい挑戦が、日本と2つの米国の研究チーム(プリンストン高等研究所を中心とする東海岸チームと、スタンフォード大学を中心とする西海岸チーム)によって、今回行われることとなった。
まず、研究に参加した日本チームは、国立天文台のスーパーコンピュータ「アテルイII」を用いて実行された、一辺約400億光年におよぶ立方体に相当する宇宙のシミュレーションデータを用意。これは、宇宙論研究者が現時点までに構築してきた解析手法が、これまで以上に巨大な領域を調査する、究極の観測計画に対してどの程度通用するのかを明らかにするためのデータだという。
-
中央が今回の研究で日本チームが用意した模擬宇宙。一辺は約400億光年。模擬宇宙のムラは、ダークマターを主成分とする物質密度の濃淡を表し、赤い部分が高密度、青白い部分が低密度涼気に対応している。右上の拡大図からは、ネットワーク上に広がる複雑な構造を見て取れる。そして左の大きな青い立方体は、地球から観測可能な領域に等しい領域を立方体にしたもの。一辺は約750億光年。右の小さな青い立方体は、スローン・デジタル・スカイ・サーベイ(SDSS)で観測された領域に等しい体積の立方体。一辺は約90億光年。模擬宇宙は観測可能な全領域の立方体までは届いていないが、SDSSの立方体よりは遥かに大きいサイズで扱えるようになった。(c) 西道啓博氏(出所:国立天文台 天文シミュレーションプロジェクト Webサイト)
また、一辺は約750億光年という観測可能な領域に相当する体積の立方体も用意。観測可能な領域とは、地球から“宇宙の地平線”までの領域のことである。地球から遠くなるほど宇宙の膨張速度は増し、ある地点では遂に光の速度に到達し、そこから先は光の速度も超えていく(物体の移動とは異なり、空間自体の膨張なので、光の速度の限界には縛られない)。光の速度と等しくなる地点から先は、天体が発した光が地球までやってこないため、観測は不可能となる。そのため、宇宙の地平線といわれているのである。
ちなみに地球から宇宙の地平線までの距離は、450億光年以上と見積もられている。つまり、理論的には半径450億光年以上の球体が地球から観測可能な宇宙ということになる(実際には天の川銀河の中心部の向こう側など、観測できない領域もある)。
ちなみに、実際に行われた観測の中では最大の銀河サーベイであるスローン・デジタル・スカイ・サーベイの領域は一辺が約90億光年で、人類はまだ宇宙の非常に狭い領域しか観測していないことがわかる。
今回のチャレンジは取り組み方に特色があるが、これまで類似の研究がなかったわけではない。ただし、それらにおいては宇宙の構造形成を正確に追いかける計算にかかるコストの高さが障壁となっており、これに代わる近似的な計算によって作られた模擬宇宙データが用いられてきた。
しかし今回の研究では、これまで日本チームが整備してきた信頼性の高いシミュレーション技術と、アテルイIIが可能にする大規模計算によって、現在類似の研究で用いられている中では最大かつ最も精巧な模擬宇宙データを用意することができたとしている。
こうして作られた模擬宇宙から実際の観測を模した銀河データを作成し、宇宙論パラメータの導出のために使われる基本的な統計量である「パワースペクトル」が測定された。パワースペクトルとは、銀河が網目構造に集まっている「宇宙の大規模構造」における銀河の密度の濃淡(揺らぎ)を、フーリエ解析をもって異なる波長の波に分解し、波の波長ごとに揺らぎの大きさを見たものである。大きなスケールにおいては、この統計量が銀河の空間分布が持つ統計的情報の大部分を有していると考えられており、宇宙論解析の際に標準的に用いられている。
日本チームは、コンピュータ・シミュレーションの中で仮定されている宇宙論パラメータや、「模擬銀河カタログ構築の詳細」を伏せた状態で、パワースペクトルのデータを米国の2つのチームに提供。その状態で、宇宙論パラメータを正しく復元できるかどうかのテストが行われたのである。
-
宇宙論チャレンジプログラムの概要。日本チームは立方体状の領域から銀河を同定し(左パネル「模擬宇宙カタログ」で色付きの丸印で表したものが銀河に対応)、銀河の分布を特徴付ける統計量「パワースペクトル」を測定。それが米2チームに引き渡された。両チームはこのデータを有効場の理論に基づいて分析し、導かれた宇宙論パラメータを日本チームに提出。模擬宇宙の中で仮定されていた数値と比較し、その一致の良さが確かめられた。これにより、それぞれの解析チームが用いた解析手法の妥当性が検証されたのである。(c) 西道啓博氏、高田昌広氏(出所:国立天文台 天文シミュレーションプロジェクト Webサイト)
なお、銀河形成に関わる物理過程を直接解くことが難しいことから、その代わりに、重力によって作られた高密度領域に銀河を置く簡便な手法がしばしば取られる。この際、銀河ができると判定されるために満たすべき条件として、さまざまな可能性が検討されているが、今回は掃天観測の先駆けとして知られるスローン・デジタル・スカイ・サーベイにより観測された銀河に似た性質を持つように調整された“レシピ”が、模擬銀河カタログ構築に採用された。
有効場の理論に基づく解析が正しく機能しているのであれば、このレシピの詳細に依らず宇宙論パラメータを正確に引き出すことが期待されるという。
米国の2チームはこれまで独立に、場の量子論の分野で用いられてきた「有効場の理論」と呼ばれる手法を、宇宙の構造形成に応用する研究を進めてきた。今回、両チームはこの手法を用いて日本チームの提供したパワースペクトルを分析し、宇宙論パラメータの推定を実施。そしてその結果が出たあとの2019年6月4日、日本チームと米国の2チームがビデオ会議を行い、伏せられていた宇宙論パラメータと、米国チームの解析結果の突き合わせが行われた。
なおその時の条件は、米国チームが日本チームに解析結果を報告したあとには一切の変更は認められないこと、どんな結果が出ても最終結果として世に公開すること、だった。
米国の2チームが最終的に報告した宇宙論パラメータの値は、両チームとも誤差1%程度で真の値を再現しており、これは従来の宇宙論パラメータの決定精度の誤差よりも1桁上回る高精度な結果となった。最も大きな誤差を示したものは模擬宇宙のダークマターの総量で、報告された値は2チームとも真の値から1.3%離れていたという。しかし、これに関しても完璧に正しい解析をしたとしても約15%の確率で起こり得るものであり、概ね成功といえるものだとしている。
また今回の研究で重要だった点は、まずアテルイIIを駆使して、これまでにないほど巨大な模擬宇宙データを作った点だという。それにより、模擬宇宙データの統計的ばらつきに起因する誤差を小さくすることができ、宇宙論パラメータを導き出す解析手法そのものに起因する誤差を検証できたとした。
また、この模擬宇宙データは米国の2チームがそれぞれの解析手法の検証に使ってきた宇宙シミュレーションデータとは異なり、宇宙論パラメータの値はもちろん、模擬銀河データ構築にかかる仮定が米国チームに伏せられていた。これによって、確証バイアスを排除するとともに、どんな銀河サンプルに対しても適用できるという意味での普遍性を確認することに成功したのである。
今回のチャレンジによって、解析手法が持つ宇宙論パラメータの決定精度を客観的に担保することが可能となったという。つまり、実際の観測データを用いた解析でも、今回得られたものと同程度の精度で宇宙論パラメータを決定することが保証されるということだ。
さらに、解析手法の誤差を定量的に見積もることができたことにより、現在の解析手法をさらに向上させる手がかりも得ることができたとする。今回米国の2チームが用いた手法は、小さいスケールの構造を解析するほど大きな誤差が現れ、模擬宇宙の小さいスケールのデータが持つ情報をまだ十分に引き出せていないことがわかったからだ。将来、観測データから得られる情報を余すことなく取り出すためには、さらなる解析手法の改善が期待されるとした。
さらに、今回構築された模擬宇宙データは、日本が主宰するチャレンジプログラム「Multipole moment data for PT challenges」として、引き続き宇宙論パラメータを伏せた状態で公開中であり、世界中の研究者が新たな解析手法をテストできる状態となっている。
実際、今回の研究成果を公開したあと、新たに米カリフォルニア大学バークレー校のチームが挑戦。その結果に基づいて新たな高精度計算法が考案されるなど、宇宙論研究者コミュニティ全体を巻き込んだ展開に発展しつつあるという。今後の大規模観測データを用いた宇宙論パラメータの精密測定において避けては通れない、精密宇宙論を実現するための最終試験として注目を集めているという。
世界中で競って行われている宇宙のダークマター・ダークエネルギーの謎に迫る研究において、得られた観測データから情報をより多く、またより正確に取り出す手段を確立するために、今回の研究の模擬宇宙データが役立てられることが期待されるという。