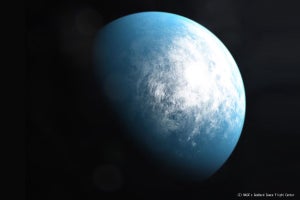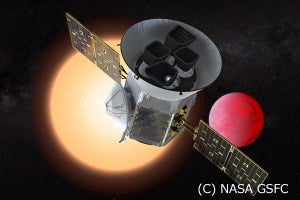東邦大学は、酸素に富む地球環境の持続期間が残り約10億年であることをシミュレーションによって明らかにしたと発表した。
同成果は、東邦大理学部 生命圏環境科学科の尾﨑和海講師、ジョージア工科大学のChristopher T. Reinhard氏による国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の地球科学を扱う学術誌「Nature Geoscience」に掲載された。
現在の地球の大気や海洋中には、大半の生物にとって生命活動を維持するのに最も必要な酸素が豊富に含まれている。酸素の大気中の割合は20%強で、窒素に次ぐ多さだ。
酸素に富む地球表層環境が実現しているということは、生命が惑星全体の環境に大きく影響していることを示す最も顕著な例となっている。そのため、地球以外の惑星や衛星での生命存否を示すシグナルである「バイオシグネチャー」としても注目されているところだ。
酸素は地球誕生当初から酸素分子として存在していたわけではなく、初期の頃は二酸化炭素(CO2)などの形で存在していた。そんな大気環境が激変したのは約30億年前といわれる。太陽光を用いてCO2から炭素を取り出して活用し、酸素は廃棄物として大気中に捨てるという、光合成の能力を獲得したシアノバクテリアが大量に繁殖し、酸素量が一気に増えたのだ。
本来、酸素は生物にとって猛毒である。その一方で、酸素は生命が活動するためのエネルギーを得るのに非常に効率のいい物質でもある。ヒトを含めて酸素で活動する好気生物は、酸素にはリスキーな一面があることも知りつつ、そのメリットを享受しているのだが、それもみな、シアノバクテリアが環境を破壊的なまでに大激変させた結果なのである。
30億年ほど前に光合成によって増えていった酸素だが、大気中のその濃度は一定だったわけではない。時代ごとに変化し、現在と同レベルとなったのは、およそ4億5000万年前から4億3000万年前の古生代オルドビス紀からシルル紀にかけてのことと考えられている。しかし、このような環境がいつまで維持されるのかということはよくわかっていない。この問題は地球生命圏の存続期間に関わるだけでなく、太陽系外での“第2の地球”の探査を行う上でも重要な研究課題となっているのだ。
酸素は主に藻類や陸上植物による光合成によって生成されるが、地質学的な時間スケールでの大気海洋中の酸素量は、光合成以外のさまざまな生物地球化学的作用の影響を受けて変化する。たとえば、水中や土壌中での有機物の分解や硫化鉄の沈殿、岩石の風化作用や火山性還元ガスの流入など、多岐にわたる。
尾﨑講師らは、酸素量を規定している地球表層圏の物質循環過程を包括的に考慮した数値モデルを構築。酸素に富んだ地球環境の持続期間を明らかにするため、シミュレーションを実施した。数値モデルには、恒星進化の理論から予測される太陽光度の変化という「地球外要因」と、火成活動の変化や生態系の応答といった「地球内要因」の両方が考慮された。40万を超える多種多様なシミュレーションを行い、富酸素な地球環境の持続期間を統計的に推定することにしたという。
その結果、太陽光度の増大に起因した温暖化と大気中のCO2濃度の低下によって生態系の一次生産が低下することで、徐々に貧酸素化が進行することが判明した。具体的には、現在の10%以上の酸素濃度が維持される期間は残り約8億9000万年から11億6000万年と推定され、その後急速に無酸素条件へ遷移していくことが予測されたのである。
-
モデルが含む不確定性を考慮したモンテカルロシミュレーションの結果。(a)大気中酸素濃度の進化シナリオ。地球大気は徐々に貧酸素化するというシミュレーション結果となった(青線)。一方、太陽光度を一定と仮定した場合は、将来20億年間にわたって現在と同等レベルに維持される(灰色線)。ただし、太陽は徐々に大きくなっており、地球公転軌道はハビタブルゾーン内ではあっても内側へと移りつつある。(b)富酸素大気の持続期間。パスツール点(現在の1%の酸素濃度)以上の富酸素な大気の持続期間についての確率密度分布。持続期間は9億4000万年から12億2000万年と推定された (出所:東邦大学Webサイト)
生物の嫌気的代謝と好気的代謝が切り替わる酸素濃度のしきい値のことを「パスツール点」という。酸素濃度1%がそのパスツール点と考えられているが、その1%の濃度ですら持続期間は9億4000万年から12億億2000万年と推定された。これ以降は、ヒトも含めて好気性の多細胞生物の生存は困難となってしまうのである。
また無酸素化は、さらなる環境の激変を招く。まず酸素がなくなることで、酸素原子3個からなるオゾン層が消失し、地表に有害な紫外線が降り注ぐようになる。また大気中のCO2濃度とメタン濃度が急増するため、気温が急増するという。その結果、生態系の一次生産が激減すると予測された。生命の棲みやすい星から、棲みにくい星へと大きく変わってしまうようである。
-
地球表層環境の進化シナリオ。(a)境界条件として与えた太陽光度。現在値が1とされている。(b)大気組成、(c)地表面平均気温、(d)全球の純一次生産の予測結果。大気中二酸化炭素濃度は太陽光度増大に起因した温暖化と陸域化学風化の促進によって億年スケールで低下すると予想された。温暖化と大気中二酸化炭素濃度の低下が生態系の一次生産力の低下を招くことで徐々に貧酸素化が進行し、約10億年後を境に急速に無酸素条件へと遷移する。この遷移に伴って大気中メタン濃度や気温の急増と一次生産の激減が生じ、これ以降の時代は好気性の多細胞生物の生存は困難となると考えられる。大気組成は痕跡量の酸素と高濃度のメタンを含む還元的な組成となり、大気中には炭化水素のもや(ヘイズ)が形成される可能性があるという (出所:東邦大学Webサイト)
数値モデルの結果は、長期的な貧酸素化が究極的には太陽進化によって駆動されていることを示しているという。その理由は、太陽光度を一定と仮定した場合の計算では、貧酸素化の長期トレンドが生じないからである。
一方、急激な酸素濃度の低下が起きるタイミングは、地球表層(大気-海洋-地殻)と地球内部(マントル)の間での物質循環を介した相互作用に影響を受けることも明らかとなった。地球内部からの還元力の供給率が大きい場合(マントルからの還元物質の流入や沈み込み帯での酸化物質の沈み込みが大きい場合)ほど、酸素に富む地球環境の持続期間は短くなるという予想結果だとした。
-
富酸素大気の持続期間。マントルから地球表層への還元ガスの流入や沈み込み帯での酸化的物質の沈み込みが多い場合など、地球内部からの還元力流入が卓越する状況ほど酸化的な地球環境の持続期間は短くなるとする。不確定性を小さくするためには、固体地球と地球表層環境の相互作用に関わる素過程(たとえば沈み込み帯での酸化還元収支)について、さらなる知見が必要だという (出所:東邦大学Webサイト)
なお今回の研究成果で導き出された酸素に富む地球環境の持続期間の推定値には、1億年以上の大きな不確定性が残っている。この不確定性を小さくするためには、生態系の応答特性や進化、地球内部との物質循環の素過程などについてさらなる理解が必要だという。
その一方で尾﨑講師らは、現在のような酸素に富む地球環境が、永続的に続くものではないことが初めて定量的に示されたことも重要な研究成果だとする。おそらく多くの人が、約50億年後に太陽が赤色巨星となって地球を飲み込むまで(地球は飲み込まれない可能性もある)、今の環境が続くと錯覚していたのではないだろうか。ところが、その1/5の10億年後には、酸素ボンベなしには地表で活動できない時代が来てしまうかも知れないのだ。今回の研究結果に基づくと、現在の10%以上の酸素濃度が維持される全期間は約15億年間(約5億年前から10億年後まで)と見積もられる。
また、地球環境がハビタブルな(生命生存に適した)状態にある期間は、最大でおよそ74億年間と考えられることから、富酸素な地球環境は全ハビタブル期間の約20%を占めるに過ぎないということになる。
-
地球のハビタブル期間を通じた地球環境変遷。(a)太陽定数、(b)生物生産の制限要因、(c)全球の純一次生産、(d)大気中CO2濃度、(e)大気中酸素濃度、(f)大気中メタン(CH4)濃度。地球における生命生存可能期間のうち約20%だけが好気性の多細胞生物の生存可能な状態にあると考えられるという結果が導き出された (出所:東邦大学Webサイト)
酸素は、太陽系外惑星での生命探査で最も注目される希望あふれるバイオシグネチャーだ。しかし今回の研究成果は、地球のように生命生存に適した惑星においても、貧-無酸素な状態が歴史の大半を占める可能性があることを示している。将来のバイオシグネチャー探査においては、酸素以外の指標でも生命存否を判断できるようなフレームワーク構築を考える必要があるとしている。