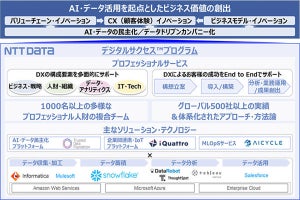クラウドベースのDWH(データウェアハウス)「Snowflake」を提供するSnowflakeは11月25日、国内事業戦略説明会を開催した。
同社は2015年から米国でAWSでサービス提供を開始。2017年にヨーローパ、その後オーストラリアでもサービス提供を開始。2019年に日本市場に参入し、2020年2月にAWS TOKYOからサービス提供を開始した。
当初はAWSのみでのサービス提供であったが、現在ではAzure、Google CLOUDでのサービス提供も行っている。
同社は昨年上場(IPO)を果たしたが、米Snowflake Chief Revenue Officer(最高売上責任者) Chris Degnan氏は、「クラウドネイティブにいち早く取り組むことができ、顧客もデータワークロードをどうクラウドに移行するかで悩んでいるため、大きくビジネスが伸びた」と、クラウドネイティブがビジネス成長の要因であると説明した。
同社はデータサイエンス、データエンジニアリングにも領域を広げ、アプリ開発もできるCLOUD DATA PLATFORMを2019年に提供、2020年にデータ共有もできるDATA CLOUDを提供した。
これについてChris Degnan氏は「Snowflakeは2020年に大きく変革した。構造データだけでなく、非構造データも含めて、分析、アナリティクスをマルチクラウドで実現できる。これはお客様が望む方向で、われわれはその方向に動いてきた」と語った。
同氏によれば、現在はワールドワイドで3000を超える顧客がおり、日本の顧客も30社を超えているというが、日本の顧客ニーズについて、Snowflake カントリーマネージャー 東條英俊氏は、経営者のデータ活用への期待が大きいと語った。
具体的には、データのサイロ化や更新頻度の課題があり、データに基づく意思決定がしたい、最新のデータで意思決定したいというニーズがあるという。
「企業は本業のビジネスに貢献するデータ活用を模索している。データに基づいてパーソナライズやカスタマイズをしていきたいというニーズがあり、そういったニーズに応えるためにデータ分析基盤としてのSnowflakeがある」(東條氏)
また、同氏はSnowflakeの差別化ポイントについて、「どのクラウドでも利用できるのがSnowflakeの価値。クラウドサービス、コンピュータ、ストレージがそれぞれが独立し、どのクラウドでも動かすことができる。これはこれまでのデータウェアハウスではできなかった大きな特徴だ」と述べた。
そして同氏は今後の国内の事業戦略について、ユースケースを業種別にたくさん公開するほか、顧客同士が情報交換する場としてコミュニティー等を積極的に用意するという。
そのほか日本語対応への取り組み強化し、ドキュメント、UIなどの日本語化のほか、来年上半期には有償のトレーニングプログラムを提供。さらに、来年下半期には日本語のテクニカルサポートも日本語で提供する予定だという。