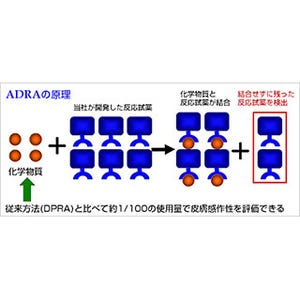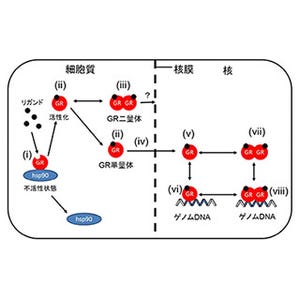順天堂大学は8月27日、研究段階にある食物アレルギーの治療法である「経口免疫療法」により食物アレルギー症状の発生が抑えられるメカニズムを、マウスモデルを用いた実験で明らかにしたと発表した。
同成果は、同大学大学院医学研究科アトピー疾患研究センターの中野信浩 助教、北浦次郎 先任准教授、奥村康 センター長、および同大学医学部小児科学講座の米山俊之 助手、清水俊明 教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国アレルギー・喘息・免疫学会が発行する学術誌「Journal of Allergy and Clinical Immunology」のオンライン版に掲載された。
免疫系は外部から侵入してきた異物を排除するために働くが、特定の抗原(物質)に対しては免疫反応を起こさない「免疫寛容」と呼ばれる仕組みも有している。腸管から吸収された食物も外部からの異物だが、通常は免疫寛容が誘導される仕組みで、大多数の人はアレルギー症状を発生しない。
しかし、特定の食物に対してアレルギー反応が誘発されてしまう食物アレルギーを発症している人たちも少なからずいる。日本における食物アレルギーの有症率は子供に多く、乳幼児で5~10%、学童以降が1.3~4.5%といわれている。食物アレルギーは、危険な症状が誘発されるため、軽視するわけにはいかない。原因食物を摂取すると即時型のアレルギー反応が発生し、ときには複数の臓器にアレルギー症状が現れ、重篤で生命の危険を伴うアナフィラキシーが引き起こされてしまうからである。
食物アレルギーは、成長するにしたがって改善するケースも多い。ただし、自然経過では改善が見込めそうにない症例もあり、それらに対して有効であるとして現在期待されているのが経口免疫療法だ。ただし同療法は研究段階にあり、まだ一般診療としては推奨されていない。その理由は、なぜ食物アレルギーが改善されるのか、その仕組みがよくわかっていないところなどにある。
同療法では、原因食物をアレルギー症状が起きないよう、ごく少量から摂取をし始め、毎日少しずつ増やしながら、まず「脱感作」と呼ばれる状態を誘導する。原因食物を摂取するとアレルギー症状が誘発される状態を「感作」といい、脱感作とは、感作の状態から連日にわたって摂取することで、アレルギー症状が誘発されていた量を超えて摂取しても症状が誘発されなくなる状態のことをいう。要は、毎日少しずつ原因物質に慣れさせていくのである。
脱感作の状態に誘導されたあとは、原因食物の摂取を2週間ほど中断し、再び摂取したときにアレルギー症状が誘発されなければ原因食物に対して持続的な不応統制が獲得されたと判断される。そして最終的には、アレルギー症状のない免疫寛容の獲得を目指すのだ。
しかし、経口免疫療法は前述したように、その詳しいメカニズムがわかっていない。また、同療法は低効率であることも課題となっている。小児の鶏卵アレルギー患者に対して同療法を実施した研究では、耐性を獲得できた小児は約28%だったという。そこで共同研究チームは今回、どのような細胞や分子が持続的な不応答性の獲得に関与しているのかを解明するため、経口免疫療法のマウスモデルを作成して解析を実施した。
まず、卵白アルブミン(鶏卵の白身のタンパク質)に対してアレルギー反応を起こすマウスに経口免疫療法が施され、脱感作および持続的な不応答の状態が誘導されるマウスモデルが作成された。続いてそのマウスモデルを用いて、免疫細胞の分化や獲得調節に関わる「Notch受容体」についての実験が行われた。Notch受容体とは、免疫細胞やそのほか多くの細胞の表面に発現している受容体のことで、この受容体を介して伝わるシグナルが細胞の分化などに関与していることが知られている。
実験の結果、Notch受容体を介して細胞内に伝わるシグナルを遮断する薬剤(Notchシグナル阻害剤)を経口免疫療法期間中に投与すると、脱感作は誘導されるものの、その後の持続的な不応答性が誘導されなくなることが判明したのである。要は、食物アレルギーがぶり返してしまうということだ。
さらに、(1)食物アレルギーを起こさせたマウス、(2)経口免疫療法によって持続的な不応答が誘導させれたマウス、(3)経口免疫療法期間中にNotchシグナル阻害剤を投与したことで持続的な不応答が誘導されなかったマウスの3種類に対し、細胞集団にどのような違いがあるのかの解析が行われた。
その結果、(2)の経口免疫療法マウスでは、免疫抑制性サイトカイン「インターロイキン-10(IL-10)」を産生する免疫細胞「抑制性T細胞」が腸管で増加していることが確認された。サイトカインとは、細胞間でやり取りされる多様な生理活性を持つタンパク質の1種である。また、免疫細胞「ヘルパーT細胞」の活性化を強力に抑制する「単球系骨髄由来抑制細胞」が腸管だけでなく、全身で増加していることも判明した。
T細胞とはリンパ球(免疫細胞)の一種であり、中でもヘルパーT細胞は、免疫応答において、多様な免疫細胞を活性化させる“司令官”的な役割を担う重要な細胞だ。複数のタイプがあり、アレルギーの発症に大きく関わるのが「2型ヘルパーT細胞」である。そして骨髄由来抑制細胞とは、炎症やがんなどで誘導される未熟な骨髄系細胞の集団のことで、免疫反応を抑制する機能を有する。骨髄由来抑制細胞は形態や機能の違いがあり、単球系と顆粒球系に分類されている。
また3種類のマウスのうち、(1)のアレルギーマウスでは、アレルギー疾患の発症に関与する「インターロイキン4(IL-4)」を産生する2型ヘルパーT細胞が腸管および全身で確認された。それに対して(2)の経口免疫療法マウスでは、前述したIL-10と同時にIL-4も産生する2型ヘルパーT細胞の集団が増加していることがわかったのである。
(3)のNotchシグナル阻害剤投与マウスについては、これらの免疫抑制性細胞の増加が見られなかった。また(2)の経口免疫療法マウスから骨髄由来抑制細胞を除去したところ、(3)のNotchシグナル阻害剤投与マウスのように、持続的な不応答が誘導されなくなることも確かめられたのである。
これらの結果から、経口免疫療法は制御性T細胞、単球系骨髄由来抑制細胞、IL-10を産生する2型ヘルパーT細胞といった免疫抑制に働く細胞集団を腸管または全身に増加させ、それが持続的な不応答の獲得に寄与していることが示された。さらに、これらの細胞集団の増加には、Notch受容体を介したシグナル伝達が重要な役割を果たしていることも明らかとなった。
共同研究チームでは今後、今回の研究で確認された経口免疫療法のメカニズムが、ヒトでも同様に働くのかを確認していく予定だ。そして今回の成果をもとに、経口免疫療法の効果や進捗を簡便にモニターできる指標ができることを期待しているとしている。