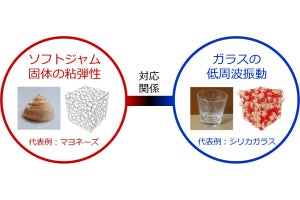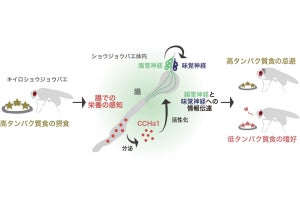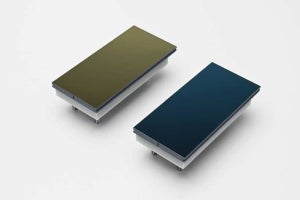太陽が誕生した当初は同じような質量を持つペアの星があり、互いに引力で影響し合う「連星」だったとする理論モデルを、米ハーバード大学の研究グループが発表した。太陽系の果てを包み込んでいるとみられる無数の小天体群「オールトの雲」や、未発見の第9惑星の成り立ちも説明がつくという。太陽系の見方に大きな影響を与える可能性がある説として、注目されそうだ。
このモデルによると、太陽とそのペアの星が同じガスの雲から生まれ連星となった。この連星の引力で遠くの天体が引き寄せられ、太陽系を巨大な殻のように取り囲むオールトの雲を形成した可能性がある。
オールトの雲は、太陽と地球の間の距離(約1億5000万キロ)の1万~10万倍の大きさと考えられている小さな天体の分布。従来は、惑星にならなかった小さな天体が、惑星の引力の影響で遠くにはね飛ばされて形成されたなどと説明されてきた。ただ、太陽が単独で存在したことを前提とする従来のモデルでは、オールトの雲の存在の説明に難があったという。
同大のアビ・ローブ教授は「連星は、単独の星よりはるかに効率的に天体を引き寄せる」と説明。別のメンバーは「連星があったとするモデルは明らかに洗練されたものだ。太陽のような星は多くが、連星の形で生まれた」との見方を示している。
海王星の軌道の外側には未発見の第9惑星があるとの説があり、発見競争が続いている。グループのモデルによると、この星は太陽系内でできたのではなく、連星の引力によって外から取り込まれたという。なお、ここでいう第9惑星は、2006年に惑星から除外された冥王星とは別物だ。
では、太陽のペアだった恒星はどこに行ったのか。グループのメンバーは「今では天の川のどこかにあるかもしれない」と、全く分からないという。ローブ氏は「近くを通過した星々の引力の影響で、太陽はペアの星と引き離されたのだろう。その前に、太陽系はオールトの雲と第9惑星を獲得した」とみている。
成果は18日、米天体物理学誌「アストロフィジカル・ジャーナル・レターズ」に掲載された。
|
関連記事 |