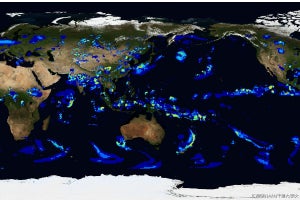理化学研究所(理研)、情報通信研究機構(NICT)、大阪大学(阪大)、エムティーアイ、筑波大学、東京大学(東大)、科学技術振興機構(JST)の7者は8月21日、同月25日から9月5日までの12日間にわたり、首都圏を対象に、解像度100mかつ30秒ごとに更新しつつ、30分後までの降水予報を行うリアルタイム実証実験を行うことを発表。実証実験で得られる予報データを基に、理研では天気予報研究Webページを、エムティーアイではスマートフォンアプリ「3D雨雲ウォッチ」を8月25日から公開した。
今回の実証実験は、理研計算科学研究センター データ同化研究チームの三好建正チームリーダー、情報通信研究機構 電磁波研究所 リモートセンシング研究室の佐藤晋介研究マネージャー、阪大大学院工学研究科の牛尾知雄教授、エムティーアイ ライフ事業部 気象サービス部の小池佳奈部長、筑波大 計算科学研究センターの朴泰祐教授、東大 情報基盤センターの中島研吾教授ら25人近くの研究者が加わっている共同研究チームによって行われている。
近年、ゲリラ豪雨(俗称であり、正式な学術用語ではない)と呼ばれる、突発的かつ局地的な集中豪雨によるリスクが高まっている。ゲリラ豪雨を降らせる積乱雲の発生から発達、そして降雨までが数分という短時間で発生するのがやっかいな部分で、現在の天気予報では追いつけない状況となっている。
現在の天気予報は、スーパーコンピュータを用いたシミュレーションに基づくものだが、1時間ごとに新たな観測データを取り込んで更新しているため、リアルタイムに更新することが難しかった。例えば気象庁で運用されている局地モデル(LFM)は、全国を対象に2km四方の解像度で、1時間ごとの更新頻度となっている。
1時間の更新だと、その間にゲリラ豪雨が発生し、かつ止んで雲がなくなってしまう可能性もある。また、降雨範囲も1km四方で収まるような場合もあり、それよりも大きな解像度では、ゲリラ豪雨を引き起こす積乱雲を十分に捉えることが難しいとされていた。
こうした問題に対し、理研の三好チームリーダーらは2016年、スーパーコンピュータ「京」を活用し、「解像度100m・30秒ごとの更新・30分後までの予報」を可能とする「ゲリラ豪雨予測手法」を開発。このときの研究では、気象データの取得に、NICT、阪大、東芝が共同で開発した、三次元降水分布を一辺100mの分解能かつ最短10秒間隔で観測することができる「フェーズドアレイ気象レーダー(PAWR)」が利用された。
しかし、実用化に向けては、「京」を駆使しても、30秒ごとに送られてくる大量のデータの処理が追いつかず、本来なら30秒以内に完了すべき計算に約10分かかるという課題があった。そこで研究チームは今回、リアルタイム予報を実現するための技術的課題解決に取り組んだという。
具体的には、計算時間の短縮に向け、スパコン上でのビッグデータの入出力を抑える工夫を行ったほか、予報モデルの計算の高速化も図ることで、それまで10分ほどかかっていた計算を、20秒程度に短縮することに成功したという。
またスパコン「富岳」の稼働に向け、「京」がシャットダウンされたことから、今回の研究ではスパコンを筑波大と東大が共同運営する最先端共同HPC基板施設(JCAHPC)の「Oakforest-PACS」に変更しており、これにより、システム全体の汎用性が増したともしている。
超高速降水予報システムのシミュレーションの特徴は、積乱雲の発生・発達・消滅といった気象学的なメカニズムも考慮されていること。これにより、これまでは捉えられなかったゲリラ豪雨の急激な変化も、実際に観測しているかのように予測することが可能となったという。
なお、今回の研究成果として、理研とエムティーアイでは、気象業務法に基づく予報業務許可を得て、予報データを活用した天気予報研究Webページとスマホアプリ「3D 雨雲ウォッチ」を公開中だ。
ただし、実証実験での予報はあくまでも試験的なものであり、実用レベルの十分な精度や安定した配信環境が保証されたものではないと研究チームでは説明しており、利用者の安全や利益に関わる意思決定を目的とした利用には、適さないとしている。
今回の実証実験は終了後に分析・検証が行われ、超高速降水予報システムの実用化に向けた開発がさらに進められる予定である。