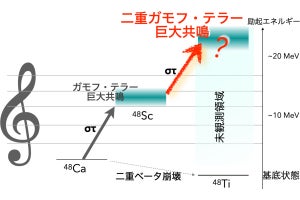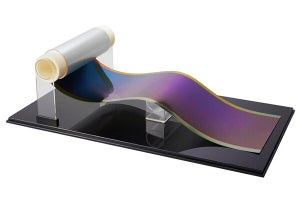魚のトゲウオの仲間のうち内陸の淡水で暮らす集団には、有害とされるゲノム(全遺伝情報)の変異が多く蓄積していることが、国立遺伝学研究所生態遺伝学研究室などのグループの研究で分かった。こうした集団では保全のため、個体数を増やして規模を大きくする必要があるとみられる。
トゲウオ科の魚は冷たい水を好み、本州では湧水など限られた水域でのみ生息できる。しかし湧水の枯渇や埋め立てなどが進み、この数十年で本州のトゲウオは絶滅の危機に瀕しているという。
グループは個体数が著しく減っている栃木・那須、福島・会津など本州5カ所のトゲウオの集団について、ゲノムの情報から有害な変異を推定し、海のトゲウオ集団と比較した。その結果、これらの内陸の集団は海の集団よりも有害変異が明らかに多く蓄積していることが分かった。
同研究所の太田朋子名誉教授らの「ほぼ中立説」によると、集団を構成する個体の数が減ると、有利な変異が増えたり不利な変異が減ったりする「自然選択」の効果が弱くなり、有害な変異が残るようになるとされる。こうした有害変異がある程度蓄積すると集団がさらに小さくなり、絶滅への負のスパイラルが生じうると考えられている。
ほぼ中立説は生物の保全を考える上で重要な視点となっている。有害変異の蓄積は栽培植物や家畜などの人為的に作られた生物の集団で確認されてきたものの、野外の絶滅危惧集団ではほとんど検証されてこなかったという。
同研究所の北野潤教授(進化生物学)は「ゲノム解析は絶滅危機種や集団のリスクの推定を通じ、生物の保全に貢献できる。今後は一つ一つの変異が、生物にとって実際に有害なのかを調べていきたい」と述べている。
研究グループは同研究所と岐阜協立大学、福井県立大学、東北大学で構成した。成果は英国のゲノム科学・進化生物学専門誌「ゲノム・バイオロジー・アンド・エボリューション」に3月31日に掲載され、同研究所が4月6日に発表した。
|
関連記事 |