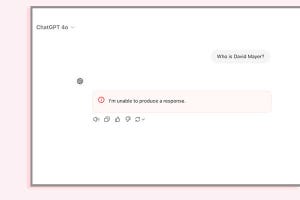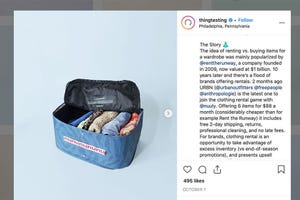今日、カスタマーエクスペリエンス(CX)はこれまで以上に重要性を増している。マーケターは潜在的な顧客に関する膨大な情報にアクセスすることが可能である一方、この情報の分析方法や利用方法により、CXにおける成功企業とそうでない企業の明暗が分かれている。
マーケティング(または顧客)にとって、コンテンツのパーソナライズ化はもはや真新しいことではない。情報へのアクセスと分析に裏打ちされ、マルチプラットフォームを活用した、ハイパー・パーソナライゼーションのさらなる進化が、2020年度のCXの改善策として重要になる。
以下、海外のトレンドを踏まえながら、これらがどのように展開していくかを考えてみたい。まずは、CXに関する2020年の予測を紹介しよう。
(1)データの民主化によるハイパー・パーソナライゼーション
2020年は、消費者のカスタマージャーニー全体にわたって、ハイパー・パーソナライゼーションの年になるとされており、2020年度のデータの民主化は、マーケターにとって重要な要素になっている。
これにより、各ブランドは、ビジネス全体にわたるデータを活用して、ターゲットオーディエンスのコンテキスト(背景・心理など)に基づく多角的な視点で顧客を理解するハイパー・パーソナライズされたCXの提供を可能にするマーケティング戦略を構築していくことが求められる。大手ブランドは、従来のCXを越えて、個別の製品およびサービスの提供と価格について検討するようになる。
(2)「多感覚ブランドエクスペリエンス」の台頭
顧客とブランドの関わり方は、既存のデジタルと物理的な接点を超越していくことになる。2020年には、顧客がデジタルの世界をどのように認識し、ブランドとどのように関わるかという点において、CXが大きく変化することが予想されている。
拡張現実(AR)、仮想現実(VR)、複合現実(MR)などの主要技術は、人々の知覚モデルと相互作用モデルを組み合わせることで、複数の感覚器官を活用したブランドエクスペリエンスを生み出す。その結果、顧客は製品だけでなく、あらゆる感覚を通してブランドを体験できるものに注目することになる。
(3)IoTとマーケティングエンジニアリング
IoTは、データによって駆動されるハイパー・パーソナライズされた体験を作り出す上で、不可欠な要素となるだろう。総務省によれば、2021年には350億のIoTデバイスが接続されると予測され、それぞれが重要度の高い消費者インサイトを収集することが可能となる。
マーケターはそれらを活用して、カスタマイズされコンテキストに沿ったコンテンツをリアルタイムで配信し、パーソナライズされたCXを提供することで、顧客とブランドのエンゲージを促進させることになる。前述した複数の感覚器官を活用する「多感覚ブランドエクスペリエンス」に適応することで、IoTはデジタルと物理的環境のギャップの橋渡しをし、あらゆる感覚を横断した顧客との接点を構築するだろう。
さらに、CXに焦点を当てた新しくてユニークなIoTの導入により、ブランドの製品開発、マーケティングの提供方法を強化することが可能になっていく。
(4)顧客満足度における音声検索の重要性
AIによる顧客とのやり取りから生成されたデータは、従来のデジタルチャネルを越えて、より本格的なデジタルコミュニケーションの体験を生み出す上で、大いにマーケターの助けになるだろう。
特に音声検索はそのシンプルさにより、今後大幅に普及するはずだ。Google AssistantやAmazon Alexaのような、AIを利用したインテリジェントなアシスタント機能が簡易化していることから、ブランド企業は既存のCXに音声検索を導入することが求められるようになるだろう。
(5)プライバシーへの懸念の高まり
ハイパー・パーソナライズされたCXへの需要が高まり、データへの依存度を高める一方で、個人情報の管理に対する消費者の関心も高まっている。同時に、企業は個人データの保護と管理の重要性をより認識するようになり、政府は組織がデータの保護と管理を実行するための厳しい法律を施行している。
企業は今後も、デジタル倫理とプライバシーに対する不安解消のため、透明性とトレーサビリティに重点を置くことが求められるだろう。規制要件に対処しつつ、高度なテクノロジーの使用に対する倫理的なアプローチを維持し、企業に対して高まる信頼の欠如を修復する必要がある。
5つの予測を踏まえた対応策
これら5つの予測に共通するのはデータの基盤であり、その基盤となるのがマーケティング・テクノロジーである。デジタルマーケティングの台頭により、企業によるMA、DMP、CMSなどのさまざまなソリューションの導入は一巡した感がある。デジタルマーケティングの流行に乗ってツールを導入してみたものの、「期待した結果が得られなかった」「自社の運用とは合わなかった」といった話はよく聞く。
筆者が長年携わっているCMSの分野を例にとると、デジタルマーケティング先行でスイート製品を導入したところ、MA機能は満足いくものだったが、CMSは柔軟性がなく、制作効率やコスト面で満足度が低かったという話をよく耳にする。自社に適したツールは何なのか、誰のために、どのような目的で導入するのか、一度自社で保有しているテクノロジーの棚卸しを実施し、自社のマーケティングテクノロジー・ロードマップを再構築することをお勧めしたい。
ベスト・オブ・ブリードによる最適化
マーケティング・テクノロジーの採用にあたっては、さまざまなツールがワンストップで提供されるスイート製品に対し、目的に応じて各分野でベストの製品を組み合わせるベスト・オブ・ブリードの2つのアプローチがある。ここ数年の動向を見ていると、変化の速いこのマーケットでは、時流に合わせた入れ替えが可能なベスト・オブ・ブリードの選択に落ち着くように思われる。これは、スイート製品を導入した企業で聞かれる「思いのほかそのメリットを引き出せていない」というコメントに表れている。
特定企業のスイート製品が各分野でベストの製品であるということはなく、中には古いアーキテクチャの製品が含まれていたり、買収製品の寄せ集めで作られた結果、ツール間連携すらできないものもある。ファッションの例が適切かはわからないが、すべてを1ブランドでそろえなくても、今はハイブランドとファストファッションを組み合わせてオシャレを楽しむ時代でもある。
自社の運用や目的に合えば、高機能CMSと安価なMAの組み合わせや、その逆もまた然りである。また、過去の例を見れば、クラウドブームで各企業がクラウドに移行したものの、今ではパブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミスのように、それぞれの環境を生かしたハイブリッドソリューションが支持を集めている。
デジタルマーケティングの世界でもDMPからCDPといったテクノロジーの変化から、さらなる進化とハイブリッドな環境に適応するための改善が進んでいる。このような背景からも、ベスト・オブ・ブリードによるマーケティングテクノロジー・ロードマップの見直しが期待される。
2020年は、各社にとって適切なツールを見極めた上で、企業全体でデータを適切に使用し、そこから生み出される競争上の優位性を確認、実証していく年になるだろう。