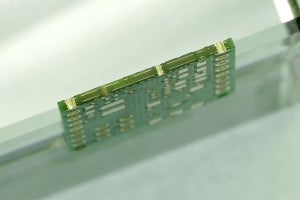量子ドット(QD)はスーパーハイビジョンが目指す広色域の映像を実現する有力な材料として期待され、液晶のバックライトに搭載したQLED-TV(QDシートLCDテレビ)がOLED-TVとの主導権争いを繰り広げてきた。
2013年にソニーが液晶テレビに搭載したことで業界の注目が集まり市場の拡大が期待され、これまでに多くの企業が参入してきたが、市場は期待される程なかなか伸びてこなかった。その原因は、価格の高さやCdが使われている事への抵抗が大きな原因だと言われているが、他にも理由があるのではないだろうか。
3月に米サンディエゴで開催されたQD Forumに参加し、様々な発表や参加者との議論を通して感じたのは、この技術の難しさと、それにチャレンジしてきた様々な企業の取り組みの状況であり、徐々に今後の方向が見えてきたという感もある。これまで市場には出たものの、地を這うような低空飛行を続けてきたQDディスプレーが、この先上昇に転じる気配も出てきた。
さらに、これまでディスプレー市場をターゲットに繰り広げられてきた量子ドットという材料がもっと幅広い可能性を持った材料であり、この材料開発に取り組む各社がそれぞれの方向で様々なアプリケーションにチャレンジし始めたことも今回のQD Forumではっきり見えてきた。
多様化するディスプレー応用の形態と新たな可能性
QDの応用形態は様々である。図1に、今回のQD Forumで聞いたアイデアも交えて筆者の視点で整理し直してみた。QDそのものはナノメータサイズの微粒子であるが、その使い方を整理してみると点から線、面、立体型へと進化している。これを判りやすくゼロ次元から三次元に例えて見た。
すでに市場で実用化が進んでいる使い方は、LCDバックライト用のQDシートである。このディスプレー用途のバックライトQDシートで真っ先に実用化が進んだ理由は、表示の広色域化という市場のニーズにぴったりとマッチした材料であったことと、材料を供給するメーカにとっては、ディスプレー製造の世界が「面積ビジネス」で成り立っており大画面になればなるほど好都合であるといった思惑があることも確かである。
一方で、さらに発展させた形態の開発も進んでいる。SamsungによるQD on GlassおよびQDカラーフィルタである。このQDカラーフィルタは、2~3年前に液晶ディスプレー用として開発が始まったが、液晶で使われている偏光板をインセル型にする必要があり、技術の難易度が高く断念された経緯がある。代わって現在開発が進められているのが、青色OLED(有機EL)をバックライト代わりにして緑と赤のQDをカラーフィルタ代わりにして色変換をするOLED-TVである。このQDカラーフィルタが実用化できれば、今後出てくるミニLED/マイクロLEDへの応用も視野に入ってくる。
印刷方式でOLEDの置き換えを目指す自発光型のQLEDは、開発が進むもののまだまだ課題は多く、実用化には数年かかるだろうと言うのが最近の業界関係者のほぼ一致した見方であり、図の中では時間軸も含めた「四次元的」と表現してみた。
-
図1 QDの様々な応用形態。これまでのLCDへの応用が進んでいるPhoto Luminescentだけでなく、QD Forumで発表された様々な形態を、筆者の視点で整理し直してみた。技術的難易度は、基本的に下に行くほど高くなるが、応用範囲もディスプレーに留まらず太陽電池やセンサに広がっていく (筆者が作成)
本格的な上昇に転じる気配を示すQDディスプレー市場
QDが初めてディスプレーに搭載された2013年、各QDメーカーや業界の調査会社は皆、数年後には大画面TVで採用され1000~2000万台の大きな市場に成長するという強気の市場予想を発表していた。しかし、2019年現在の市場を見ると、ここ数年は400万台程度の横ばいに留まっている。その内容も主にSamsung一社が牽引し、中国のTCLやHisenseなどが細々と続いている状況である。その理由の1つには価格の高さも言われるが、その他に今回のQD Forumでも指摘されていた「広色域に対する必要性が認知されていない」という状況にもある様だ。
とは言いながらも2019年に入ってからQDを搭載した65型4K-TVがVISIOから約1500ドルで出るなど低価格が進んでいることと、8K-TVの急速な拡大に伴う色域への認識も徐々に高まりつつあり、市場が上向く気配を見せてきた、との報告も今回の会議で公表された。市場調査会社の予測では、ここ数年400万台程度で低空飛行していた市場も2019年には約700万台、2020年には1000万台を超え、2025年には2500万台まで上昇し、いよいよ本格的な普及期に入るという期待も出始めた。