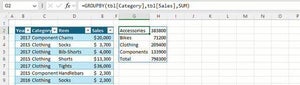「働き方改革関連法」が4月1日から施行された。大企業と中小企業によって施行タイミングは異なっているが、十分に準備した上でこの4月を迎えられたという企業もあれば、実質的な対応はこれからという企業もあるだろう 。そうした中、企業側の視点から「最短・最速」で「働き方改革関連法」にどう対応していくべきなのかについて、オービックビジネスコンサルタント(OBC) マーケティング部 リーダーの津吉沙織里氏に改正への対応ポイントを聞いた。
「企業側としては、まずは法令違反を回避したいという思いが強いように見受けられます。しかし、人手や時間をかけて対策するのは難しい状況です。特に影響の大きい改正労働基準法について、厚生労働省からQ&Aが公開されているので、基本的にはこれを見ていただければいいのですが、かなり量があり、求めている答えをピンポイントで探すのは大変です。対応への準備が順調に進んでいるお客様や、社会保険労務士の先生に話をお聞きしたところ、自分にとって必要なことを効率よく学び、ツール等を利用してできるだけ簡単に対応計画を作ることが大切であることがわかりました」と津吉氏は語る。
有給休暇消化は計画的な消化を促し、アラート&指導で対応
改正労働基準法では、2019年4月1日から企業規模を問わずすべての企業に義務付けられたのが年次有給休暇(以下、有休)の確実な取得である。対象となるのは、年に10日以上の有休が付与されるすべての労働者となっている。
「パート・アルバイトを含む、年10日以上の有休を付与されている人すべてを対象に、有休のうち5日間については取得時季を指定して与えることが企業の義務となりました。従来、有休の取得は労働者の権利だったわけですが、5日分は企業の義務になったわけです。違反した場合、1人あたり30万円以下の罰金となります」(津吉氏)
パート・アルバイトの場合は労働時間によって付与条件は異なるが、フルタイム労働者の場合は、入社から半年が経過すれば10日が付与される(全労働日の8割以上出勤)ため、多くの労働者が対象となる。
取得させる方法は、企業による時季指定のほか、従来通り労働者側が時季を指定する方法や、計画的付与制度の活用も可能だ。計画的付与制度では、企業カレンダーのような形で一斉に休みにする日や、部署ごとの休日を指定して消化させることができる。
有休が付与されてから1年間に確実に5日の有休を取得させるためには、進捗管理が非常に重要になる。個人単位で取得率を定期的に確認し、取得率が伸びない従業員に対して本人、上司に対して積極的な指導および支援を行うことが有効だ。
「法改正以前から有休の取得促進に取り組まれていたお客様の事例からおすすめしたいのは、6カ月間で3日の取得目標というような目標値を決めて達成状況を管理し、未達成の場合には本人と上司に指導するということを繰り返しながら10カ月程度を過ごし、それでも達成していない人に対しては、具体的な取得日の相談をして取得してもらう方法です」と津吉氏は語る。
「企業側からの指導方法について決まった形はないので、口頭による促しでも達成されれば問題ありません。しかし未達成の人が出た場合に、十分に指導を行っていたという証跡になるものは残っていた方がいいので、メールなどの手段を使って促進の取組を実施し、1年間の中で継続的に有休取得の促進に取り組んだ実績を残しておけるといいと考えられます」と津吉氏は語った。
有休付与から1年で全員を休ませる難しさ
入社日に合わせた個別付与をしている場合、4月一斉入社を採用していれば6カ月後の有休付与日が統一されるが、「中途入社が多い」「通年採用を導入している」ケースは入社日が分散するため管理が複雑になる。また、新入社員には入社時に前倒し付与をしている場合等には管理が難しくなる。
「個別付与を採用しており、入社日が分散している場合は管理負担が大きくなるため、基準日付与への変更を検討することを社会保険労務士の先生なども推奨されています。なお、すでに基準日付与を採用しており、入社年と翌年以降で義務化の対象期間が重複するケースがあると思いますが、特例により、重複するそれぞれの期間を通じた期間の長さに応じて比例按分した日数を取得させることができます。現状の有休の付与ルールに応じて、ルールの変更を検討したり、必要な業務を確認したりすることが重要です」(津吉氏)
また、企業として気になるのは既存の各種休暇・休業制度との兼ね合いだろう。たとえば介護休業や育児休業といった制度を利用した場合は、残る労働日数で5日の有休取得が現実的に可能な場合は休ませることが義務となる。
「リフレッシュ休暇などの独自の休暇制度がある場合、法定の有休日数を上乗せして付与する休暇制度ならば5日の対象日として扱うことができますが、法定の有休を増やさずに、特別休暇として与えていた場合は対象外です。労働者が自由に休める場合には有休とみなすことはできますが、たとえば5日まとめて休むことが条件等の場合には対象外ですね。また人間ドックを受ける場合などの休暇制度も対象外となってしまいます」と津吉氏は解説した。
このほか、半日単位で取得した分は取得義務を果たしたことになるが、時間単位で取得した分はカウント対象にできないというルールもある。企業はこうしたルールを把握した上で、自社のどの休暇制度が有休消化にあたるのか、半日休暇を取得したときに取得義務分にカウントされるのかなど、自社の勤怠管理システム上の処理を確認し、全従業員に着実な消化を促さなければならない。
「取得状況については有休管理簿を作成し、3年間保存することが義務になりました。しかし、必ずしも専用の帳簿を作成する必要はありません。基準日、取得日、取得日数について同一の帳簿にまとまっている必要もなく、必要な時に明確な形で提示できるならば既存システムのデータを活用することも可能です」と津吉氏は語るが、既存の手法では十分な管理を行えない企業も少なくなさそうだ。