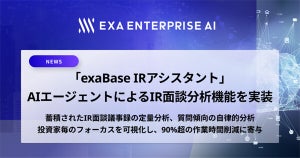地球温暖化とは、たんに私たちの生活圏の気温が上がることを指すのではない。気温が上がると大気が含むことのできる水蒸気が増え、なにかのきっかけで、雨や雪として一気に落ちてくるようになるかもしれない。洪水や渇水のパターンも現在とは違う姿になる可能性がある。
-
図 地球温暖化で気温が2度上がったとき、大雨などの極端な気象をもとにして求めた「水文気候学的強度」が1.5度に比べて上がっている地域を赤で、下がっている地域を青で示した。青より赤で覆われた部分が広く、この0.5度の差で、洪水と干ばつのダブルパンチを受けやすくなる地域が多いことがわかる。(金さんら研究グループ提供)
いま世界は、地球温暖化の原因となる二酸化炭素が私たちの暮らしからあまり出ていなかった産業革命前に比べ、平均気温の上昇を2度未満、できれば1.5度に抑える目標をたてている。「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」が2018年の特別報告書で定めた目標だ。この0.5度の差が、私たちがさらされる気候変化のリスクに、どれくらい影響するのか。それを洪水と干ばつのダブルパンチを受ける可能性の観点から調べたのが、東京大学生産技術研究所の金炯俊(きむ ひょんじゅん)特任准教授らの研究グループだ。
洪水や干ばつは、私たちの生活をじかに脅かす。地球温暖化の進行にともない、いま降水量の多い地域ではさらに多く、少ない地域ではさらに少なくなる傾向が、これまでの研究で指摘されている。だが、ある地域が洪水にも干ばつにも襲われるとすれば、その気候に適応するための社会のインフラは複雑なものになるだろう。金さんらは、この点に着目した。地球温暖化による昇温を平均2度に抑えたときと1.5度に抑えたときとで、洪水と干ばつのダブルパンチに遭う可能性は、どう違ってくるのだろうか。
その地域差を数字の上で比較するため、金さんらは「水文気候学的強度」という数値を世界全体にわたって計算した。トータルでは同じ量の雨が降るとしても、こまめに少しずつ降るよりも、「降るときは何日も続けて降るが、いったんやむと、次に降るときまで長い期間があいてしまう」という降り方だと、大きな数値になる。つまり洪水にも干ばつにも遭いやすい「洪水かつ干ばつ」型の降り方を検出するための数値だ。
コンピューター計算で予測した「2度上昇」のときの水文気候学的強度を「1.5度上昇」の場合と比べたところ、北半球の中高緯度のほとんどの地域で、その値は大きくなっていた。わずか0.5度の差でも、「降るときは降る、降らないときは長いこと降らない」という傾向が広範囲で強まるのだ。地域ごとにみると、日本を含む東アジアでは、降る期間の雨量が増すことでこうした極端な降り方になり、地中海沿岸では、雨の降らない期間が長引くようになることがわかった。これはまた、気温の上昇を1.5度に抑えることで、この洪水・干ばつ型の降り方をかなり抑制できるということでもある。
日本では昨年7月、台風や梅雨前線の影響で西日本を中心に記録的な大雨となり、土砂災害などで多くの犠牲者が出た。だが翌8月の西日本の降水量は、平年比で20%以下の地域もあり、非常に少なかった。洪水・干ばつ型の降り方は、もう身近に表れている。地球温暖化が進むと、きわめて激しい雨や熱波などの極端な気象が頻発すると考えられている。この先どうやっても、2040年前後にいったんは2度くらい昇温するという予測もある。こうした予測を我が事として社会はとらえられるのか。来るべき気象災害の軽減は、そこに大きくかかっている。
|
関連記事 |