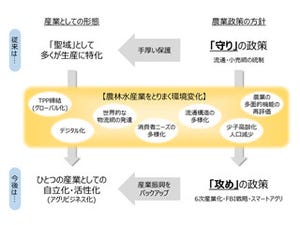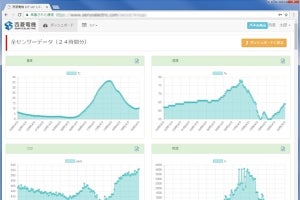世界的な日本酒として知られる「獺祭(だっさい)」の蔵元である旭酒造。その酒造りは、杜氏を設けず製造法をデータ化、ITを活用することで、美味しさと大量生産の両立を実現したことで知られる。
そんな同社の桜井博志会長が9月11日、東京・八王子の東京工科大学・日本工学院八王子専門学校にて、これまで同社が取り組んできたさまざまな挑戦についての講演を行なった。
折りしも、同社は、2018年7月に発生した西日本の大雨の影響で酒蔵の一部が浸水するなどした影響から、獺祭の製造を停止。公式Twitterアカウントで、9月13日より出荷を再開することを告知した直後の開催、ということで、櫻井氏も、酒蔵を240年続いていた木造のものから近代的なビルに建て替えていたことで、自分たちの命が助かり、商売の再開にもこぎつけることができたと説明。「昨日と同じ今日、明日があるとは限らない。かならず社会は変化し、自分たちを取り巻く環境は変化する」という持論を披露した。
なぜ獺祭はデータを活用した酒造りをするのか
同社のデータを活用して日本酒を製造するという姿勢も、こうした環境の変化に対応するために生み出されたものだ。ある年、杜氏から、他の蔵元に移りたいという申し出があり、酒造りを知らない一般社員しかいない状況となってしまった。そこがデータの本格的な活用が始まった。
例えばデータ活用の1つとして、温度管理が挙げられる。同社の酒蔵は常に摂氏5度の状況を保つことで、365日の生産を可能としている。しかし、今回の西日本豪雨により、3日間の停電が発生。酒蔵で発酵中であった150本の発酵タンク(四合瓶換算で約70万本)のもろみのコントロールが効かなくなり、その結果、獺祭が要求する品質に到達できない日本酒が大量に作られることとなってしまった。「せっかくのお米をいただいて、酒を作っているわけで、何とかしたい」との想いから、漫画家の弘兼憲史氏の協力を得る形で、「獺祭 島耕作」として販売が決定。売り上げの一部を西日本豪雨の被災地域への義援金として寄付するといったこともあり、発売直後に予約完売の状態となった。
すべては飲んでくれる人の「美味しい」を求めて
現在、同社のデータ活用は、さまざまな広がりを見せている。例えば、2014年から富士通と連携し、富士通の食・農クラウド「Akisai」を契約栽培農家に導入し、酒造好適米の栽培技術の見える化・共有化を促進することで、原料となる米「山田錦」の収量増加に向けた取り組みを進めてきた。また、2018年4月から6月にかけては、富士通および富士通研究所と協力して、富士通研究所が開発した日本酒作り支援のためのAI予測モデルを用いた獺祭の醸造実験も行なわれた。
「田んぼの状況をデータ化して、それを元に、いつ水を入れるのか、水を切るのか、肥料をあげるのか、刈り取りをするのか、といったことを進めている。酒造りのときも、徹底的にデータ化することで、経験豊かな杜氏よりもおいしい酒を造ることを目指したが、それは農家でも同じことだと感じた。データ化しないで昨日と同じことをやっていては変わらないが、実際は気候は毎日違うし、去年と今年でも違ってくる。杜氏や農家の人たちは経験でその変化を補っていたが、それは結局データ化と同じこと」と、米作りとのものでもデータ化を進めることで、山田錦の収量は現在62万俵を超すまでに拡大。旭酒造は、そこから17万6000俵を購入し、獺祭の製造に活用しているという。
しかし、櫻井氏はデータ化の意義を「一定の品質のものを作ろうというわけではない。データ化することは、ちょっとでもおいしいものを作ろうという試みの手段の1つ」と説明。「データ化を進めれば進めていくほど、データではできないことが分かって、未来は分からないという現実がはっきりしてくる。だからこそ、データ化をしていく必要がある」とし、データ化の根底に、獺祭を飲んでくれる人たちに、よりおいしいお酒を飲んでもらい、美味しい、という思いを提供したいという気持ちがあることを強調していた。
参考
・旭酒造 公式Twitterによる獺祭の出荷再開発表
・旭酒造と富士通 食・農クラウド「Akisai」を活用した酒造好適米の栽培技術の見える化を開始(富士通プレスリース)
・旭酒造と富士通、予測AIを活用した日本酒醸造の実証実験を開始(富士通プレスリリース)
・西日本豪雨被災者復興支援 純米大吟醸 獺祭 島耕作