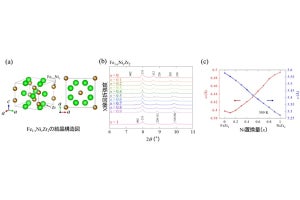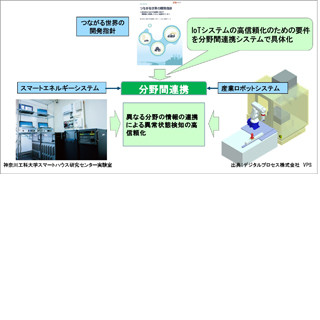日本医療研究開発機構(AMED)は7月9日、東京女子医科大(女子医大)を中心に研究開発が進む治療の現場においてIoTを活用することで、各種の医療機器や設備を接続、連携させることで、手術の進行や患者の状況などを瞬時に時系列でそろえ、医師やスタッフ間で共有することを可能とする「スマート治療室SCOT」の事業化を前提とした「スタンダードモデル」が信州大学に設置されたことを明らかにした。
-
左から日本医療研究開発機構 産学連携部 部長の高見牧人氏、東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 村垣善浩 教授、信州大学 医学部 脳神経外科 本郷一博 教授、デンソー 新事業統括部 メディカル事業室 室長の奥田英樹氏、日立製作所 ヘルスケアビジネスユニット 外科治癒ソリューション本部長 中西彰氏
2018年7月10日訂正:記事初出時、高見牧人氏の所属を日本医療機能評価機構と記載しておりましたが、正しくは日本医療研究開発機構となりますので、当該部分を訂正させていただきました。ご迷惑をお掛けした読者の皆様、ならびに関係各位に深くお詫び申し上げます。
目指すは医療とデジタルの融合
スマート治療室プロジェクトに関わっている企業、大学は、東京女子医科大学のほか、信州大学、広島大学、東北大学、鳥取大学、デンソー、日本光電工業、ミズホ、パイオニア、キヤノンメディカルシステムズ、日立製作所、セントラルユニ、グリーンホスピタルサプライ、エア・ウォーター、エア・ウォーター防災、SOLIZEの5大学・11社。スマート治療室は、「ベーシック」、「スタンダード」、「ハイパー」の3種類が想定されており、2016年にこのうちのベーシックが広島大学に、ハイパー(プロトタイプ)が女子医科大にそれぞれ設置されており、今回、スタンダードが信州大学 医学部付属病院に設置されたことで、3種類すべてが稼動することとなる。
日本医療研究開発機構 産学連携部 部長の高見牧人氏は、「目指すのは医療とデジタルの融合。いろいろな分野でデジタルやICTが活用されている。医療分野も、医療とICTやデジタルが融合することで、新たな治療や患者にとってよりよい医療を目指すことができるようになる。その代表がスマート治療室となる」と説明。将来的には、AI(人工知能)と組み合わせて、手術中の手技をどこまで行なうと最適化、といった指針の提示なども期待できるようになるという。
治療室内のすべての機器を1つのネットワークに接続
スマート治療室では、治療室に搭載された医療機器や照明などの設備は産業用ミドルウェア「ORiN(Open Resource interface for the Network)」の医療版「OPeLiNK」を活用して接続される。これにより、さまざまな医療機器のデータが時間を同期して1つに集約して保存されることとなり、術中に発生したイベントやコメントも時間と同期した形で保存。術後の振り返りなどで状況の確認を行いやすくなるほか、光ファイバ網を活用することで、治療室外の医局(戦略デスク)と接続。治療室にベテラン医師が不在であっても、遠隔地から、手書き入力や音声を活用して、治療室の医師などに指示やアドバイスを送ることができる。
信州大学は手術室が手狭になったことを受け、2018年4月に6階建ての新診療棟(包括先進医療棟)を建設。新たに6つの手術室が設置され、その中の1室(10m×9m)の治療室をスマート治療室化したという。
導入されたスタンダードモデルは臨床利用可能なOPeLiNKが導入されており、手術室ないのほぼすべて(17台)の医療機器の情報を同期させ、4Kの80型モニタ「OPeLiNK Eye」に表示させ、医師や遠隔地のスーパーバイザがそうした情報を自分が見たいように構成を変更して活用することができる。実際の稼動は、2018年7月下旬からを予定しており、脳腫瘍摘出手術を中心に40例ほど手術を行い、その評価を行なうことを計画しているとする。
国際標準に向けた取り組みも進展
スタンダードモデルは、研究開発プロジェクトが終了した後の2019年度の事業化が見込まれている。プロジェクトとしては、日本の新たな産業基盤として、世界展開を進めていきたいとしており、規格の標準化に向けた取り組みも並行して進めていくとしている。
すでに治療室インテグレーションを行うプロジェクトの1つであるドイツのOR.netプロジェクトと共同提案という形で標準化に向けて連携を深めているとのことで、日独共同プロジェクト化に向けた動きが見えているという。
なお、スマート治療室の最終形態であるハイパーモデルは、2018年度末に女子医大に臨床研究可能な手術室を設置し、高度な意思決定ナビゲーションを中心とした情報のAI化や、新規開発のロボットベッドなどのロボティック機器の導入などが図られ、高密度集束超音波などの新規精密誘導治療の検討が行なわれていく予定だという。