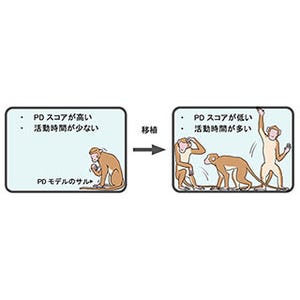慶應義塾大学(慶応大)は4月24日、難聴・めまい・甲状腺腫を特徴とする染色体劣性遺伝疾患である、Pendred症候群に対する低用量シロリムス療法の医師主導治験を実施すると発表した。
この治験は、慶応大 医学部耳鼻咽喉科学教室の小川郁 教授、藤岡正人 専任講師らにより、同じく慶応大の岡野栄之 教授(生理学教室)と実施したiPS細胞を用いた研究の知見をもとに行われるものとなる。
会見にて藤岡氏は、「難聴は、高齢者のうつ、認知症発症のリスクファクターの1つである一方、一度固定すると、治らないことが問題」と説明する。老人性難聴や突発性難聴、メニエール病などといった、難聴の多くの原因は内耳にあることが知られており、WHOによると、65才以上の人口の30~40%が難聴によるハンディキャップを有しているといわれているとのこと。
さらに、先天性疾患の中で難聴はもっとも罹患率が高く、その約半数は遺伝子に変異が見つかる遺伝性難聴であり、中でも、今回治験を実施する「Pendred症候群」は遺伝性難聴の中で2番目に患者数の多い病気であるという。
しかし、疾患を理解するためには病気が進行している組織を調べる必要があるが、「内耳は骨の内部にある臓器で、検査のために細胞を採取することができない」、「Pendred症候群には動物モデルが存在しない」などといった問題から、症例を深く理解することができず、これまで治療法の開発は難しいと考えられていた。
iPS細胞を用い、動物モデル不在の症例を治療へ
「そうした状況を受け、今回、ヒトiPS細胞から内耳細胞を効率的に安定して作成する方法を開発し、内耳の中でも聴覚を担当する部分の細胞を作製する方法を見出した」と藤岡氏。さらに、その細胞を用いて、難聴ではない健常者の内耳細胞と比較して、患者の細胞の脆弱性を明らかにすることに成功したという。
加えて、細胞ストレスに対する細胞脆弱性を改善する薬剤として、免疫抑制に用いられている、「シロリムス」という薬剤が、Pendred症候群の患者由来のiPS細胞から作成した内耳細胞の細胞脆弱性を低減するだけではなく、低用量(通常使用する量の約1/10)でも効果をもたらすということを見出した。
-
疾患iPS創薬研究の開発経緯。動物モデルが存在しない疾患の治療法を開発するため、iPS創薬を用いたin vitro試験を実施した。その結果、既存薬スクリーニングから、「シロリムス」が治療に有効である可能性が示された
これらの結果から、Pendred症候群の患者に対してシロリムスを少量投与することで、内耳細胞の脆弱性が改善し、細胞死抑制により病勢の進行を遅らせられることで難聴・めまい発作が減弱する可能性が推定された。
治験にはIoT技術を活用
そうはいっても、疾患モデル動物が確立されていないため、発見した候補薬がその安全性と、どの程度の効果をもたらすかは予想困難だ。
そこで研究チームは今後、このPendred症候群の患者を対象に、シロリムス製剤を低用量で投与することの安全性、および難聴・めまい発作に対する有効性、さらにはその有効性の評価法の探索を行うために、医師主導治験を実施していく。
-
治験実施計画。16例の患者にシロリムス製剤、もしくはプラセボ(偽薬)を投薬し、安全性や有効性を評価する。プラセボを使用するのは、患者によっては、「薬を使っている」という事実による心理的な効果で、治療効果が出てしまうことがあるためだ
なお、シロリムス製剤は臓器移植に対する免疫拒絶予防やリンパ脈管筋腫症に対して、長期投与での十分な忍容性と安全性をもって効果を発現することが確認されているため、治験では濃度を下げ、患者の安全性を確認しながら、その治療効果についても詳細に検討していくとのこと。
また、投薬の治療効果は来院時の検査に加え、自宅でも患者に検査機器やタブレット端末を貸し出し、難聴やめまいの変化を毎日モニターすることで、症状や体調の日々の変化を調査するのだという。
治験対象者には、
体のゆれや平衡をモニターする、眼鏡型重心動揺測定装置
聴力を測る、ポータブルオージオメータ
眼球の振動を診る、ワイヤレスフレンツェル眼鏡
が配布され、あらかじめ配られたマニュアルをもとに、自宅で各項目を計測し、タブレット端末を介して治験データセンタへと送ることが求められる。
Pendred症候群の症状は、体調の変化や日々の生活状態で変動すると言われているため、このような日々の検査で膨大な量の検査データを収集することで、治療法の効果を詳細に検討していくとのことだ。
-
IoTを活用した治験データ登録システム。左から、ポータブルオージオメータ、ワイヤレスフレンツェル眼鏡、眼鏡型重心動揺測定装置。患者にはマニュアルがわたされ、各装置を用い、毎晩寝る前に決められた作業を行うこととなる
なお、治験の期間は基本的に10か月程度を予定している。藤岡氏は「今回の治験を含め、すべてが順調に進んだ場合、うまくいけば5年ほどで実用化のめどが立つことが期待される」と今後の期待を述べた。