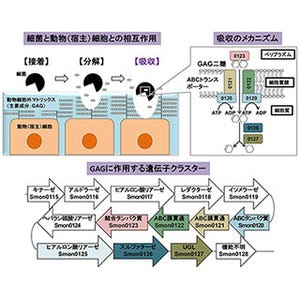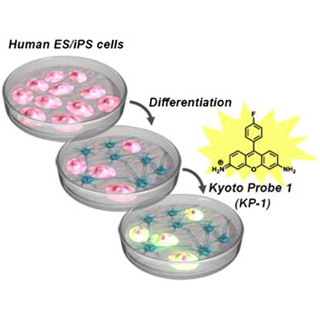京都大学(京大)は2月27日、草地性絶滅危惧チョウ類であるコヒョウモンモドキを材料に、縄文時代から現在までの個体数の増減の歴史を明らかにしたと発表した。
同成果は、京都大学大学院農学研究科の中濵直之氏(当時)、横浜国立大学環境情報研究院の内田圭 産官学連携研究員、神戸大学大学院人間発達環境学研究科の丑丸敦史 教授、京都大学大学院農学研究科の井鷺裕司 教授らの研究グループによるもの。詳細は英国の学術誌「Heredity」の電子版に掲載された。
近年多くの草地性生物が絶滅の危機に瀕していることから保全意識が高まっているが、これまでに長期的な視点と短期的な視点の両方から日本国内で草地性生物の歴史を明らかにした研究例はなかった。
今回の研究ではコヒョウモンモドキの遺伝子解析を行い、縄文時代から現在までの個体数の増減を調査した。その結果、縄文時代中期以降は個体数が大きく増加したものの、20世紀以降の草地面積の減少に伴い過去30年の間に個体数が激減したことがわかったという
また、過去30年間の個体数の変化の推定には、チョウ類の標本のDNAを用いている。これまで昆虫の乾燥標本は、DNAが劣化しているため遺伝解析が難しいとされてきたが、今回の研究により過去の情報の復元に標本DNAが有用であることを示したとしている。
なお、今回の成果を受けて研究グループは、同研究を通じて減少のメカニズムが解明できたことから、今後、同種はじめ多くの草地性絶滅危惧種の保全への応用も期待できるとしている。