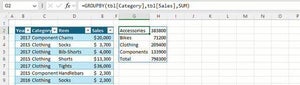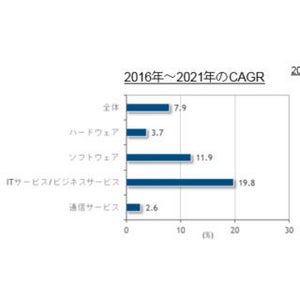パーソル総合研究所は2月8日、東京大学中原淳准教授との共同研究「希望の残業学プロジェクト」の結果を発表した。同調査は会社員6000人(管理職1000人、一般社員5000人)を対象に実施したもの。
初めに、代表取締役社長 渋谷和久氏が同プロジェクトの狙いについて説明した。近年、働き方改革が推進されたことにより、長時間労働を是正する機運が高まっているが、「残業時間の削減が目的となり、施策によって変化するはずの組織のコンディションが軽視されていないか」「残業時間削減の手法が、ハードの施策に偏っており、ソフトの領域に目が向いていないのではないか」という課題意識が生まれてきているという。
そこで、同プロジェクトでは、「残業時間削減」と「組織コンディションの向上」を両立させるには、どのような取り組みが有効なのかを明らかにしていく。
「長時間労働は、介護者、女性、外国人など、残業に適合できない人材の労働を困難にする。われわれの調査では、2025年には530万人の人材が不足するという推計が出ている。人手不足を解消するためにも、長時間労働は解決すべき課題」(渋谷氏)
残業多い業種、職種、残業を増やしている要因が明らかに
調査結果については、中原准教授から説明が行われた。同プロジェクトのコンセプトについては、「直感と経験に基づく議論ではなく、あくまでも調査データをもとに長時間労働問題を分析する。そして、残業削減を目的とするのではなく、その先にある企業・組織・働き手へのメリットを明らかにし、具体的な打ち手を作っていく」と述べた。
調査の結果、30時間以上残業している人の割合が多い業種1位は運輸・郵便業、2位は情報通信業、3位は電機・ガス・熱供給・水道業となった。また、職種の1位は配送・物流、2位は商品開発・研究、3位はIT技術・クリエイティブ職という結果となった。
係長以上の上司層に絞った調査では、業種は建設業、製造業、運輸・郵便業、職種は商品開発・研究、専門職種、生産管理・製造が、残業が多かったことがわかった。
この結果について、中原准教授は「メンバー層の調査は残業が30時間以上の割合を調べているが、30時間は多いと見ていいと思う。また、働き方改革に伴う残業抑制により、メンバー層の残業が減った分、上司層にしわ寄せがきている」と述べた。
残業が多い業種・職種を分析した結果、残業を増やしていた要因のうち、最も影響度が高いものは、突発的な業務が頻繁に発生することが明らかになった。これに、仕事の相互依存性、社外関係性・顧客とのやり取りの多さが続く。
残業が発生するメカニズムを解明
中原准教授は調査結果を分析・整理した結果、残業が発生する職場には、残業が「集中する」「感染する」「麻痺する」「遺伝する」という特徴が見られたと指摘した。
「集中」とは、部署内の仕事のシェアがうまくいっておらず、優秀な部下や女子に残業が集中していることを意味する。中原准教授はこの状況について、「これでは部下の能力が伸びない。全体に仕事を割り振っていく必要がある」と述べた。
「感染」とは、職場内の同調圧力により、帰りにくい雰囲気が蔓延していることを意味する。「周りの人が働いていると帰りにくい」という状況は、若い人ほど顕著だという。例えば、男性20代は50代の1.9倍、女性20代は1.7倍、帰りにくさを感じているという結果が出ている。さらに、上司の残業時間が多ければ多いほど、「帰りにくさ」は増すという傾向も明らかになっている。
「麻痺」とは、長時間労働によって「価値・意識・行動の整合性」が失われ、健康被害や休職のリスクが高まる状況を指す。今回の調査では、残業時間が60時間を超えると、「幸福度」と「会社への満足度」が増すという結果が出ている。加えて、残業が60時間を超える人は、「食欲がない」「強いストレスを感じる」「重篤な病気・疾患がある」という質問への回答率が高くなっている。
つまり、残業が60時間を超えている人は、幸福度と会社への満足度が高い一方で、体の不調を抱えているという、矛盾した状況に陥っているおそれがあるというわけだ。
「遺伝」とは、上司の若い頃の長時間の労働の習慣が、下の世代(部下)にも継承されていることを意味する。新卒入社時に「残業が当たり前の雰囲気だった」「終電まで残ることが多かった」という状況を経験している上司は、転職しても部下に残業を多くさせているという結果が出ている。上司の残業体質は、世代に加えて企業を越えて受け継がれてしまっていることになる。
中原准教授は、企業に求められる残業施策として、「麻痺」の発生を防止するとともに、残業習慣を是正することを推進していくとよいと述べた。また、残業施策の効果を最大化するには、従業員本人と職場のコミットメントと施策の告知を行うとよいという。