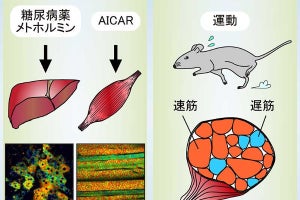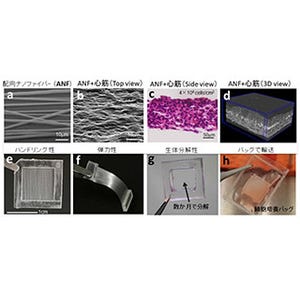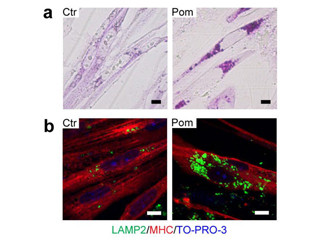京都大学(京大)は、立っている時の脊柱の傾きと脊柱の柔軟性低下が、変形性股関節症の進行に関わる重要な要因であることを明らかにしたことを発表した。
この研究成果は同大医学研究科の建内宏重助教、同・市橋則明教授らの研究グループによるもので、12月18日、国際変形性関節症学会の学術誌「Osteoarthritis and Cartilage」に掲載された。
股関節の痛みや可動範囲の制限、筋力低下などの症状が出る疾患である「変形性股関節症」は、歩行や立ち座りなどの運動機能や生活の質にも大きな悪影響を与える。女性に多く、日本では約120万から420万人の患者がいるとされている。
同疾患は慢性進行性であるため、その進行予防は極めて重要な課題である。現在まで、骨形態の異常や遺伝的要素、年齢(加齢)、性別(女性)など複数の要因が疾患進行に関わることが明らかになっている。これらの要因は、リハビリテーションなどの運動によって変化させることができない要因であるため、変形性股関節症の進行予防を目的としたリハビリテーションのターゲットを明確にできず、どのような運動が有効なのかが不明であった。
このたび研究グループは、リハビリテーションの現場で一般的に測定・評価されている要因の中で運動により改善させることが可能なものに着目し、それらの中から変形性股関節症の進行に関わる要因を探索した。同疾患と診断された患者50名を対象とした研究の結果、股関節の関節可動域制限や筋力低下など股関節自体の問題よりも、立っている時の脊柱の傾きと脊柱の柔軟性低下が重要な要因であることが明らかとなった。
立位姿勢や脊柱の柔軟性は、患者の負担なく詳細に評価することが可能であるため、今後は広 くリハビリテーションの現場においてそれらのデータが蓄積され、より詳細な分析が進むことが予想される。変形性股関節症の進行についてハイリスクな患者を、より明確に特定できると期待される。
現段階では、リハビリテーションによって変形性股関節症の進行を抑制できるという十分なエビデンスは存在しないが、立位姿勢や脊柱の柔軟性は理学療法士の適切な指導のもと医療機関や自宅での運動によって変化させることが可能である。
研究グループは今後、立位姿勢や脊柱の柔軟性の改善を手段とした変形性股関節症の進行予防を目的とした研究を実施することで、進行予防に有効なリハビリテーションの開発につなげていきたいと考えていると説明している。