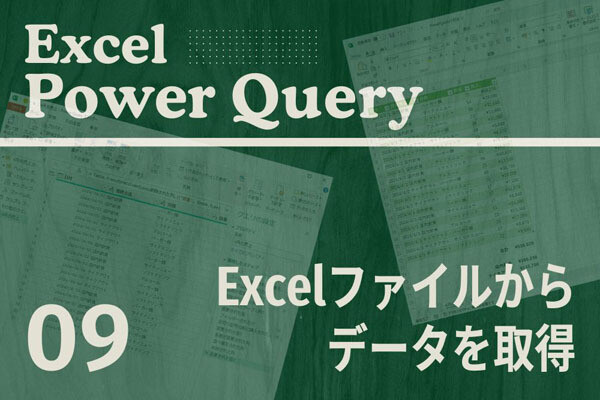内田洋行は11月27日、同社の「知的生産性研究所」が 2010年から 2017年に受託した161 件のコンサルティング・サービス「Change Working コンサルティング・サービス」の実績をもとに、働き方変革の実態調査に関する初の研究発表を行った。
「知的生産性研究所」は、1989 年にワークスタイルを専門的に研究することを目的に設立された。
発表にあたり、内田洋行 代表取締役社長 大久保昇氏は、「時代はハードからソフトへ、そして現在は働く人が課題になっている。弊社では、2010年から『Change Working コンサルティング・サービス』をやっていきたが、今回発表するのは、この7年での成果、事例を研究発表という形で分析したものだ。今、日本企業は株価高騰による高揚感もあるが、将来にわたる閉息感もある。また、長時間労働に対するプレッシャーもある。今回の発表で、企業において変化の創造性をどう高めていくかをお伝えしたい」と挨拶した。
同社がこれまで扱ってきたコンサルティングのクライアント業種の割合は、1位が39.8%で製造業、2位が通信・ITで20.5%で、以下、商社・卸(12%)、金融・保険(7.2%)と続く。
変革の対象部門は、38.6%と4割弱は全社だが、部門別に展開する場合は、研究・開発が22.9%、営業が14.5%、本社・管理が12%、設計・製造が6%という割合になっているという。
内田洋行 執行役員 知的生産性研究所 所長 平山信彦氏は「研究開発部門の成果を挙げていくためには、働き変革を進めていく必要があると考えている経営者が多い」と説明した。
コンサルティングの内容では、フレームワーク(なぜ働き方変革を進めていくのか、働き方変革の目標、そのために何をするのかなど)が39.8%で最大。以下、施策推進・総意形成が21.7%、施策評価が10.8%、研修・ワークショップが9.6%、受託調査が9.6%と続く。
コンサルティングの対象人数では、100~499人が1/3で最大で、続いて100名以下が19.3%と、大企業を対象としたコンサルティングが多い中で、比較的小規模にやっている例が多い。
同社では、細かなところまで目が届くため、組織単位に進めていくことを推奨しているという。
働き方変革を主管する部門としては、経営企画、人事、総務など、やはり管理部門が多い。
働き方変革の目的としては、競争に勝ち残れる柔軟で強靱な組織をつくりたいという経営視点での目的と、働きがいを感じる組織をつくるという社員視点での目的の2つのハピネスを求めているという。これらの評価軸としては、創造性の向上、効率性の向上、躍動制の強化が挙げられ、制度・しくみ、ワークスペース、ICTなどの支援環境整備と社員の意識や組織風土の行動変革の2つがあるという。
具体的には、最も多いのは「社内コミュニケーションの強化/サイロ破壊」で、次いで「イノベーション創出力・創造性の強化」「社員の・成長/自律性の強化」。製造業に限定して傾向をみると、「イノベーション創出力・創造性の強化」がトップで、次い で「社内コミュニケーションの強化/サイロ破壊」という結果だという。
行動変革施策では、社内コミュニケーションの活性化や社内の動きの可視化に関わる 施策が最も多く、次いで会議体・会議運営の見直し、デジタルによる情報・知識の共有に関わる施策が多く採られている。
環境整備施策に関しては、グループウェア・社内 SNS の整備・活用促進が最も多く、 次いでコミュニケーション支援スペースの設置、社外との交流施設の設置と、コミュニケーションに関わる施策が上位を占めている。
平山氏は、「これらを両輪にし、社員の行動様式、意識を変えていかないと、どんなにすばらしい環境を整備しても、働き方変革は起きない」と語った。
同氏は、働き方変革を成功させる要因として、「社員の参画」と「アーリーアダプタの醸成」の2つを挙げた。
社員の参画は最大の成功要件で、なぜ働き方を変えるのか、変えるとどうなるかを明快に示し、働き方変革に対する理解と共感を得ることが必須となるという。
また、プロジェクトメンバー以外で、自発的・積極的に取り組んでくれるアーリーアダプタの醸成が成否を分け、こういった人が1割~2割に増えてくると、様子見をしている用心深い社員を動かすことができるという。
平山氏は、「社員自身が働き方を変えていこうと意識づけがもっとも大きな成功要因であり、もっとも難しい」と述べた。
なお、「知的生産性研究所」では、働き方変革の考え方や実践的な変革推進方法を広く社会に提案すべく、書籍として「チェンジ・ワーキング イノベーションを生み出す組織をつくる」(翔泳社、1800円+税)を 11月29日に発刊する。この書籍の中では、小誌がレポートしたウシオ電機の事例が紹介されている。