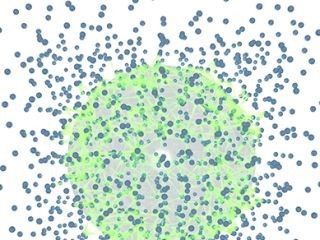インド、オマーン、カナダ、エジプトなどの物理学者の国際研究チームは、相対性理論と量子力学を統合する量子重力理論を実験的に検証するための新しい手法を提案している。既存の光学技術を用いた実験観測によって、ループ量子重力理論や超ひも理論などの妥当性を検証できるようにするという。研究論文は、「Nuclear Physics B」に掲載された。
マクロな重力についての理論である一般相対性理論と、原子以下といったミクロな世界を記述する量子力学は、互いに矛盾する点があり、理論の誕生から100年ほど経った今日もいまだに統一されない状況が続いている。このため両者の統合を目指した量子重力理論の研究が続けられており、ループ量子重力理論や超ひも理論などが統一理論の有力候補とみなされている。
ループ量子重力理論は、物質にそれ以上分割できない最小単位としての素粒子があるのと同じように、時間や空間にもそれ以上分割できない離散的な最小単位があると考えるのが特徴である。また、超ひも理論は、物質の構成単位である素粒子が大きさのない点ではなく「振動するひも」であるとする理論だが、この場合も時空構造における長さの最小単位は「ひも」の長さということになる。
ループ量子重力理論や超ひも理論で扱う時空の最小単位は、プランクスケール程度、すなわちプランク長(10-35m程度)やプランク時間(10-44秒程度)といった極めて微小な値をとる。このような極端に小さなスケールで成り立つとされる量子重力理論を実験的に調べようとすると、世界最大の粒子加速器である欧州CERNの大型ハドロン衝突型加速器(LHC)で実現可能なエネルギーよりも15桁程度も高いエネルギーが必要になるとされてきた。これが量子重力理論の妥当性を実験的に検証するのが難しくなっている理由のひとつである。
ループ量子重力理論や超ひも理論は、「非可換幾何学」と呼ばれる数学理論を基本として構築されている。二つの数aとbの間に成り立つ積算の可換性、つまり「ab=ba」という関係(交換法則)が成り立たないことを非可換性という。たとえば二つの行列AとBの積算は、一般には「AB≠BA」であり、交換法則が成り立たないので非可換である。そこで、空間内の点の座標を可換な数を使って表す通常の幾何学を拡張して、空間座標を行列や演算子で表すのが非可換幾何学ということになる。時空構造に離散的な最小単位があるとするループ量子重力理論や超ひも理論の考え方は、非可換幾何学から自然に出てくるとされる。
今回の研究は、非可換幾何学で扱うような非可換構造が現実の時空間にあるかどうかを実験的に検証する方法を提案するというものである。その方法は既存の技術で実行でき、しかもレーザー装置を用いた卓上の実験機器で実験可能であるとする。
レーザー装置による実験において、通常の可換的関係に何らかの変化が起こるかどうかについて、MEMS振動子を使って調べるのだという。もしもこのような変化が存在するとすれば、それは時空の非可換構造を示唆するものであり、観測可能な光学的な位相変化が可換的関係の変化によってつくりだされる効果なのだと考えられる。研究チームの計算によれば、プランク長付近のエネルギースケールでの現象を扱うために必要な位相変化は、既存の光学装置を使用した観測精度でもとらえることが可能であるという。