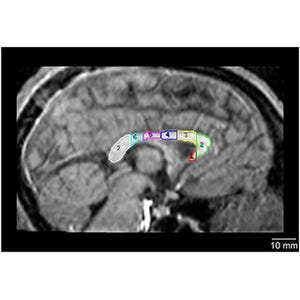京都大学は、タンザニア・マハレの野生チンパンジー集団で、出産直後の新生児が他のチンパンジーに奪われ食べられるという非常にまれな事例を観察したと発表した。
同研究は、京都大学理学研究科・日本学術振興会特別研究員の西江仁徳氏と中村美知夫准教授の研究グループによるもので、同研究成果は、10月6日、Wiley社の国際学術誌「American Journal of Physical Anthropology」に掲載された。
同研究は、2014年12月に、タンザニア・マハレの野生チンパンジー集団の観察中に、たまたまメスの出産とその直後のオスによる新生児の強奪・共食いを目撃したことから始まった。20頭前後のチンパンジーの集まりを追跡・観察していたとき、デボタ(推定14歳のメス)が地面にうずくまった姿勢でいきなり出産し、デボタの後ろに座っていたダーウィン(25歳のオス)が生まれた瞬間の新生児を拾い上げて逃亡し、その後この新生児を食べる様子が観察された。これは、野生チンパンジーの出産の観察としては6例目、集団内での子殺しとしては46例目の報告になるが、出産とその直後の新生児の強奪・共食いをつづけて観察したものとしては世界初の事例となる。
多くの哺乳類でも、オスによる子殺しの事例が報告されている。オスは自分と血がつながっていない離乳前の子供を殺すことによって、メスに早く次の子を受胎させることが可能になることから、子殺しはオスにとっての繁殖上の利益があるとの仮説が提案されている。一方、メスにとっては、自分の子供を殺されることは繁殖上の大きな不利益となるため、出産後のメスが単独で過ごす時間を増やしたり、子殺しのリスクが高い状況から離れたりする「産休」をとることで、危険を回避することが示唆されている。しかし、野生下ではチンパンジーの出産の報告が非常に少ないこともあり、出産前後の過ごし方や出産前後の母子が抱えるリスクについては十分に調べられてこなかった。
マハレで蓄積されてきた21年分の長期データを用いて調べたところ、野生チンパンジーのメスが出産前後に不在になる「産休」期間は、同時期の他のメスの不在期間と比べて長い傾向があることがわかった。このことは、マハレの野生チンパンジーのメスは、出産前後に「産休」をとる傾向があることを示している。デボタがなぜ「産休」をとらず「公衆の面前で」出産したのかはわからないが、今回の事例では「産休の欠如」が新生児を奪われる要因となった可能性がある。
同研究により、野生チンパンジーのメスが「産休」をとることを長期データから示すことができたため、これまでの子殺しの報告例についても出産前後の「産休」の長さとの対応を調べることで、オスの子殺しリスクに対するメスの対抗戦略の有効性を明らかにできる可能性があるという。また、今回のデボタは初産だったと考えられるが、「産休」をとることには出産の経験や他のメスの出産の観察による学習が必要な可能性もあり、初産と経産のメスのとりうる行動の違いもあるかもしれないということだ。