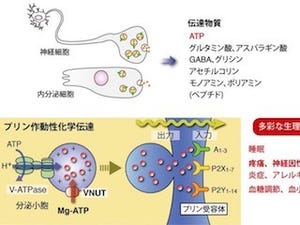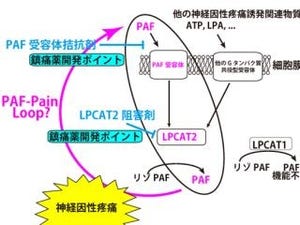産業技術総合研究所(以下、産総研)は、脳卒中後に生じる痛みである脳卒中後疼痛のメカニズムの解明や、脳卒中後疼痛のために開発した治療法を評価するためのモデル動物を開発したと発表した。
同研究は、産総研人間情報研究部門システム脳科学研究グループの長坂和明技術研修員、高島一郎研究グループ長、松田圭司主任研究員、肥後範行主任研究員らによるもので、同研究成果は、9月4日、国際科学誌Scientific Reportsにオンライン掲載された。
脳卒中によって、視床という脳の領域に損傷を受けると、脳卒中後疼痛という痛みが生じることがある。本来、痛みは身体の異常を知らせる生理的反応であるが、脳卒中後疼痛は「痛みそのものが病気」という特殊な痛みで、軽い感覚刺激でも痛みを感じるアロディニアという症状がしばしばみられる。脳卒中後疼痛は脳卒中の発症後、数週間から数か月経過後に出現するため、この間の脳の変化が痛みを生み出すと考えられてきた。しかし、その変化の実態は解明されておらず、治療技術の開発も進んでいない。治療技術の開発には、その症状を再現できるモデル動物の確立が不可欠であり、脳卒中後疼痛についても適切なモデル動物が求められていた。
同研究グループは、サルの脳の視床後外側腹側核に血管壁を破壊する酵素を注入して局所的に脳出血させた。その後、出血によりできた血腫や浮腫の体積は、損傷後3日~1週間後は増加したが、2週間後には減少した。そこで、動物の感覚応答の変化を計測するため、痛みを生じない程度の弱い機械的体性感覚刺激を上肢に与え、逃避しはじめる刺激の閾値を計測した結果、脳損傷前は痛みを感じることがなかった軽い刺激に対しては出血後8週以降から、低い温度の刺激に対しては出血後4週以降から痛みを感じていることが示された。これは、視床後外側腹側核の損傷が安定して数週間経過した後に、アロディニアのような症状が生じていると考えられる。
さらに、脳卒中後疼痛の背景にある脳の変化を解明する第一歩として、疼痛の発症との関連が示唆されているミクログリアの変化を調べた。損傷周囲領域では、損傷を受けていない健常領域と比べて、ニューロン近くに活性化したミクログリアが集積していることが確認できた。活性化したミクログリアの顕著な増加はげっ歯類を用いたモデルよりも長く続き、脳出血の3ヶ月後でも見られた。この結果から、同モデルでは、脳卒中後疼痛患者と同様の時間経過で脳に不適切な変化が生じていると考えられる。
これまで、げっ歯類を用いた視床出血後の感覚変化の研究では、出血後1週間以内に、より弱い刺激で逃避する行動が始まり、ヒトの病態とは異なっていた。今回確立したモデル動物はヒトに近い脳を持つサルを用い、実際にヒト患者に近い病態が得られたため、脳卒中後疼痛を引き起こすメカニズムの解明や、脳卒中後疼痛の治療の効果の評価に適したモデル動物と考えられる。今後は、開発したモデル動物を用いて、脳卒中後疼痛の治療や、痛みを緩和する電気刺激技術や薬剤の開発に貢献することが期待されているということだ。