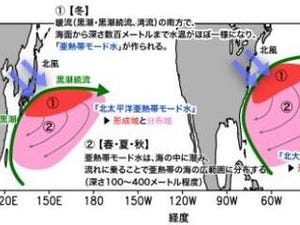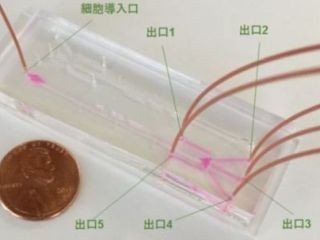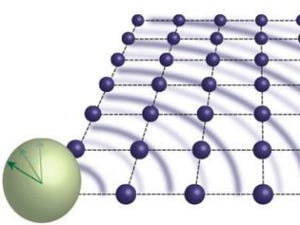東京大学(東大)は9月13日、約5,600~5,200万年前に繰り返し発生した急激かつ短期的な地球温暖化の詳細な記録を、インド洋の深海堆積物から復元し、解析した結果、海洋の生物生産が増大して大気-海洋系から余分な二酸化炭素を除去することで温暖化が終息したことを、地球科学とデータ科学の融合的アプローチにより明らかにしたと発表した。
同成果は、東京大学大学院工学系研究科の安川和孝 助教、加藤泰浩 教授、中村謙太郎 准教授、千葉工業大学次世代海洋資源研究センターの藤永公一郎 上席研究員と高知大学海洋コア総合研究センターの池原実 教授の研究グループによるもの。詳細は英国の学術誌「Scientific Reports」掲載された。
今から約5,600~5,200万年前の前期始新世は、恐竜が絶滅した約6,600万年前から現在までの新生代の中で、最も温暖な時代であった。この気候に加え、さらなる温度上昇を伴う「超温暖化」と呼ばれる、急激かつ短期的な地球温暖化が繰り返し発生していたことが知られている。「超温暖化」は、大量の温室効果ガスが大気-海洋系に放出されたために生じたと考えられていることから、人類が現在放出している大量の二酸化炭素によって将来的に何が起こるかを知るためのケーススタディとも捉えることができる。こうした前期始新世の「超温暖化」の痕跡は、最近15年くらいの間に、太平洋や大西洋、北極海、オセアニア、ヨーロッパ、北アメリカなど、世界各地から報告されているが、インド洋における詳細な記録はほとんど報告されておらず、インド洋は前期始新世の「超温暖化」に関して巨大な情報の空白域となっていた。
今回、研究グループは、インド洋で過去に掘削された深海堆積物コアから試料を採取し、化学分析を行った。その結果、「超温暖化」を示す複数の炭素同位体比の異常が確認され、インド洋における「超温暖化」の痕跡を高時間解像度で復元することに成功した。これにより、前期始新世における一連の「超温暖化」が全地球的な環境変動であったことが確実になったとしている。
また、同研究で得られた炭素の安定同位体比と29種類の元素含有量から成る30次元の地球化学データセットを、独立成分分析という多変量解析手法で解析。その結果、データが持つ全情報量の84%が、統計的に独立している4つの成分(生物源炭酸カルシウム、生物源リン酸カルシウム、海洋表層の石灰質プランクトン群集の変化または堆積後の続成過程の影響、生物源バライト)で説明されることが分かったという。
これらのうち、生物源バライト(硫酸バリウム)の堆積は、「超温暖化」時の炭素同位体比異常と連動して増加していた。大気-海洋系の二酸化炭素は、海洋表層で光合成をする生物(プランクトン)によって有機物に変換され、深海へ運ばれる。その過程で有機物の一部は分解され、バライトが生成され、海底へ沈降していくため、海底堆積物へのバライトの沈積量が増加することは、海洋における有機物の生産と深海への輸送、すなわち輸送生産性の増大を意味する。
このことから、同研究で抽出した生物源バライトに関連する成分は、海洋の輸送生産性の増大が大気-海洋系内の余分な二酸化炭素を除去することで、温暖化状態から元の状態へと地球の気候を回復させる「負のフィードバック」を表していると考えられるという。このフィードバックは、最も深刻な「超温暖化」であった約5,600万年前で機能しただけでなく、より小規模な他の複数の「超温暖化」においても同様に機能した普遍的なメカニズムであることが、明らかになったとしている。
なお、研究チームは同成果によって、今後、地球システムに内在するこうした負のフィードバックの機能するタイミングや、回復にかかる時間スケールをより詳細に明らかにすることで、地質学的時間スケール(数万年以上)と人類社会の時間スケール(数千年以下)のギャップを埋め、気候変動という現象についての本質的な理解が進むとともに、その影響を予測する精度の向上につながると期待されるとしている。