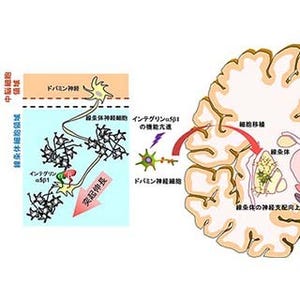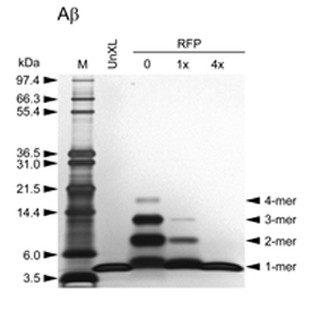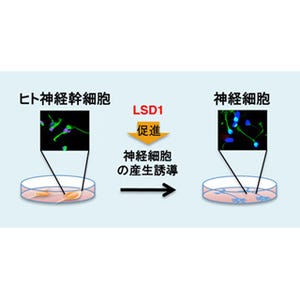京都大学iPS細胞研究所(京大CiRA)は8月31日、パーキンソン病霊長類モデルのサルにヒトiPS細胞由来ドパミン神経前駆細胞を移植し、術後のサルの行動解析によりパーキンソン病の症状が軽減されていることを観測したと発表した。
同成果は、京大CiRA臨床応用研究部門 菊地哲広研究員、髙橋淳教授らの研究グループによるもので、8月30日付けの英国科学誌「Nature」オンライン版に掲載された。
パーキンソン病は、脳のドパミン神経細胞が減少し、それらの細胞が産生するドパミン量が減ることで、手足の震えや体のこわばり、運動減少などの症状が出る進行性の神経難病。従来の薬物や電極を脳に植え込む治療法では、ドパミン神経細胞そのものの減少を食い止めることはできず、病状の悪化に伴い症状の改善が困難になる。
そこで、iPS細胞由来のドパミン神経前駆細胞を脳に移植することによってその症状を軽減する治療法開発を目指した研究が行われてきた。しかし、こうした細胞移植が治療法として確立するには、移植した細胞が長期間にわたって機能するのか、また、安全性が確保できるかどうかの検証が必要となる。今回、同研究グループは、パーキンソン病霊長類モデルのカニクイザル(サル)にiPS細胞由来ドパミン神経前駆細胞を移植することによって、治療法の有効性と安全性の確認を行った。
研究ではまず、髙橋教授らの研究グループが2014年に確立したパーキンソン病に対する細胞移植の非臨床試験のプロトコールをパーキンソン病モデルのサルに用い、ヒトiPS細胞由来ドパミン神経前駆細胞を脳に移植。移植後のサルの行動解析からパーキンソン病の症状が軽減されていることを観測した。パーキンソン病患者由来、健康な人由来のiPS細胞から作製したドパミン神経前駆細胞のいずれを移植した場合においても同様の結果が確認されたという。
次に、移植した細胞が脳内に生着し機能していることをMRIとPET画像を用いて調べ、後に摘出した脳の細胞組織の解析でMRIとPET画像が有効であることを確認。さらに、少なくとも移植後2年以内において脳内で腫瘍を形成していないことを確認した。
これらの結果は、ヒトiPS細胞由来のドパミン神経前駆細胞をパーキンソン病患者に移植する治療法が有効かつ安全である可能性を示したもので、同研究グループは、今後、iPS細胞を用いたパーキンソン病の細胞移植療法の治験に向けて申請準備を進めていきたい考えだ。