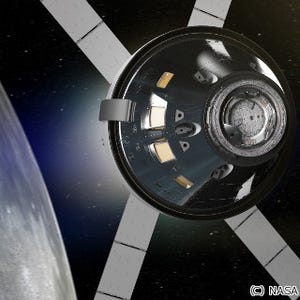米国航空宇宙局(NASA)は2017年8月3日、将来の有人太陽系探査を見据え、新しい「原子力ロケットエンジン」の実現に向けた技術の開発を始めると発表した。原子力技術で多くの実績をもつ米国企業BWXテクノロジーズとの共同で行われ、契約額は1880万ドル。約3年をかけ、エンジンや核燃料の設計、試験の実施を目指す。
原子力ロケットは理論上、これまでに実用化されたあらゆるロケットエンジンをはるかに超える、きわめて高い性能を出すことができ、有人月・火星探査はもちろん、その先の宇宙空間への飛行にも大きく役立つ技術である。かつて人類がアポロ計画を始め、宇宙開発に無限の希望を抱いていた1960年代に開発が行われたが、膨大な開発費や、必要性の弱さ、安全性などの面から打ち切られ、実際に宇宙を飛ぶことはなかった。
そして今、ふたたび月へ、火星へ向けた有人飛行、そして火星への移住までもが現実味を帯びてきた中、原子力ロケットと、そして原子力の宇宙利用全体にも、ふたたび光が当たりつつある。
宇宙の原子力、あれこれ
まず最初に、宇宙における原子力について簡単に整理しておきたい。
宇宙開発において一番有名な原子力の利用法といえば、「原子力電池」だろう。先ごろ打ち上げから40年を迎えた探査機「ボイジャー」や、初の冥王星探査に成功した「ニュー・ホライズンズ」、火星探査車「キュリオシティ」などに搭載されており、太陽光が届きにくく太陽電池が使えない環境での活動を支えている。
ただ、原子力電池は"原子力"といっても、原子力発電所のような原子炉を積んでいるわけではない。実際には、放射性物質のプルトニウム238などの崩壊熱を利用して、熱電変換素子などで発電するという仕組みで、核分裂したり、ましてや臨界状態に達することは決してない。
原子力電池は英語で「Radioisotope Thermoelectric Generator」、略して「RTG」といい、直訳すると「放射性同位体熱電発電機」という意味になる。そのため原子力電池というのは、放射性物質を使っていることからきた意訳といえよう。
|
|
|
|
惑星探査機などに搭載されているRTGの内部のプルトニウム238 (C) Department of Energy |
冥王星を探査した「ニュー・ホライゾンズ」の画像。左下に見える黒い円筒から板が生えているような部品がRTGである (C) NASA |
一方で、まさに原子炉そのものが宇宙に打ち上げられたこともある。たとえば1965年には米国が「SNAP-10A」という宇宙用原子炉を積んだ衛星を打ち上げ、故障するまで1か月ほど実際に発電し、試験を行った。1980年代にも「SP-100」という原子炉の開発が行われたことがあるが、こちらは打ち上げには至っていない。
ソビエト連邦(ソ連)では、1970~80年代に本格的な宇宙用原子炉「ブーク」(Buk)や「トパース」(Topaz)の開発に成功。実際にこれらを積んだレーダー偵察衛星が数十機も打ち上げられ、運用された実績がある。
宇宙用原子炉が開発された背景には、小型かつ大きな電力が生み出せる発電機が必要になったという経緯がある。レーダー偵察衛星を動かすためには大電力が必要だが、それを太陽電池でまかなおうとするとサイズが大きくなり、低軌道にわずかに存在する大気との抵抗が増えて高度が下がってしまう。そこで大電力をまかないつつ、衛星のサイズを抑えるため、宇宙用原子炉が求められたのである。
宇宙用原子炉の仕組みは、熱源として使って熱電変換する点はRTGと同じだが、原子炉はその熱量が桁違いなので、より大電力を生み出すことができる。また後に、地上の原子炉のようにタービンを回したり、さらにはスターリング・エンジンを使った発電方法も研究されている。
ちなみにトパースの技術は、ソ連解体後に米国が購入し、英国やフランスといった国の技術者も立ち会いのもとで地上試験が行われ、調査や評価が行われた。ただSP-100と同様、これまでのところ米国の衛星に組み込まれて宇宙を飛んだことはない。また、1990年代には、NASAで原子炉を電気推進エンジンの電力源として使う構想もあったが、実現には至っていない。
|
|
|
|
米国が1960年代に開発した宇宙用原子炉「SNAP-10A」 (C) Department of Energy |
ソ連が1970~80年代に開発した本格的な宇宙用原子炉「トパース」。レーダー偵察衛星の電力源として、実際に打ち上げられ、運用された (C) Rosatom |
原子力ロケット
このように、宇宙における原子力の利用にはいくつかの種類があるが、今回NASAが開発を決めたのは「原子力ロケット」と呼ばれる、原子力を電力源ではなく、推進力として使うものである。
その仕組みは、臨界状態の原子炉の炉心に、液体水素などの推進剤を当て、その熱で超高温・高圧のガスにし、それを噴射するという単純なものである。こうした方法を「熱核ロケット」ともいう。
ちなみに原子力ロケットには、熱核ロケット以外にも、核爆弾を宇宙飛行に使う「核パルス推進」という方法もある。ロケットの後方に核爆弾を次々に発射し、爆発させ、その反動で進むというもので、もちろん言うまでもなく、構想のみで実現には至っていない。
熱核ロケットの最大の特長は効率がとてもよいところにあり、現在実用化されているような、燃料と酸化剤を燃やし、発生したガスを噴射する形式のロケットエンジンと比べ、2倍以上も効率(燃費)がよい。つまり同じ量の推進剤でも、より速いスピードを得ることができる。また推進剤も、液体水素が最も性能がよいものの、要は炉心に当ててガスになればよいので、ケロシンや水を使うこともできる。
逆に欠点としては、安全性の問題がある。これは前述したRTGや宇宙用原子炉にも通じることだが、打ち上げに失敗すれば、放射性物質が撒き散らされる可能性がある。RTGでは強固なカプセルに入れられたり、宇宙用原子炉も運用終了時には高軌道に捨てるなどして、少なくとも地上に被害が出ないような配慮ができるが、しかし原子力ロケットはその仕組み上、炉心に当たって汚染されたガスを噴射することになるので、大気圏内で使うわけにはいかないし、地上で噴射試験をする場合にも細心の注意を払う必要がある。
RTGや宇宙用原子炉とは異なり、原子力ロケットはこれまで実用化されたことはないが、1950~70年代には米国とソ連でさかんに研究され、米国では「ナーヴァ」(NERVA)、ソ連では「RD-0410」といったエンジンが実際に造られ、噴射試験まで行われている。
ソ連では有人月飛行用のロケットの上段エンジンとして、また米国でも、アポロ計画以降に計画されていた有人火星探査に使うことが考えられていたが、いずれも実用化までに膨大な開発費が必要なことや、そもそも有人月・火星飛行計画が打ち切られ必要性がなくなったことなどから、実現することはなかった。
|
|
|
|
原子力ロケットエンジンの構造図。原子炉の炉心に推進剤を当てて加熱し、発生した超高温・高圧のガスを噴射する (C) Department of Energy |
NERVA計画の中で行われた、原子力ロケットエンジンの噴射試験の様子 (C) NASA |
しかし、それでも原子力ロケットがもつ可能性まで失われたわけではない。その後もふたたびの有人月探査や、さらにその先の有人火星探査について議論されるとき、原子力ロケットを使うべきとの声は根強くあった。ただ、いずれも青写真止まりで、実際の研究・開発にまで進むことはなかった。
そんな中で、NASAは近年、有人火星探査の実現に向けて徐々に歩みを進めている。まだ十分な予算がついているわけではなく、実現するかどうかはわからないものの、ロケットや宇宙船の開発が進んでいるところからも、少なくともアポロ計画以来、一番実現に近づいていることは間違いない。
こうした動きを受け、NASAは今回、ふたたび原子力ロケットの実現に向けた研究・開発を行うことを決定した。