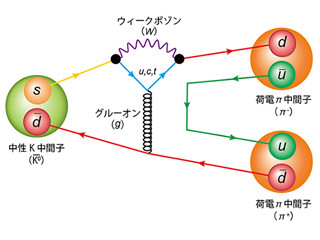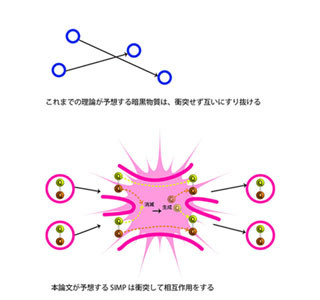欧州原子核研究機構(CERN)は、2つの光子同士がぶつかって散乱する「光子・光子散乱」と呼ばれる現象の直接的証拠を、大型ハドロン衝突型加速器(LHC)による実験で確認したと発表した。光子・光子散乱は、量子電磁力学(QED:Quantum electrodynamics)によって1930年代から存在が予言されていたが、実験が難しくこれまで確認されていなかった。研究論文は物理学誌「Nature Physics」に掲載された。
古典電磁気学では、光子同士がお互いに相互作用することはないとされる。古典電磁気学で扱う粒子の相互作用は、正または負の電荷をもった荷電粒子同士の電磁的相互作用であるが、光子は電荷をもっていないため相互作用できないと考えられる。
一方、相対性理論や量子力学を取り入れて古典電磁気学を拡張したQEDでは、古典理論ではあり得ないさまざまな現象が起こるとされており、光子同士の相互作用もその1つである。
QED理論では、光子のエネルギーによって真空が励起され、電子と陽電子のペアが対生成されると考える。生成された粒子のペアは、すぐに対消滅して真空に戻るので「仮想粒子対」とも呼ばれる。対消滅時にはエネルギーが光の形で放出されるので、過程全体を通してみると、光子が仮想粒子対に一瞬分かれ、すぐに元の光子に戻ったように見える。仮想粒子対の状態では電子と陽電子が電荷をもつため、電磁気学的な相互作用が光子間にも働くと考えることができる。
光子同士が弾性衝突して進路が変わる光子・光子散乱についても、QEDの理論構築が進んだ1930年代からすでに予想されていたが、これまで実験的に確認されたことはなかった。これは光子・光子散乱が確率的になかなか起こらない事象だからである。
光子のエネルギーをωとすると、光子同士の散乱断面積σは、σ=3.5×10-70・ω6m2という式で与えられる。可視光領域の場合、ωは1eV(電子ボルト)のオーダーなので散乱断面積σは10-70m2程度という非常に小さな値になる。散乱断面積が小さいということは、すなわち散乱が起こる確率が低いということである。
ただし、上の式で散乱断面積が「ωの6乗」に比例する形になっていることに注目すれば、光子のエネルギーをある程度大きくすることによって、光子・光子散乱が観測可能なレベルまで確率を上げることができると考えられる。というわけで、実際に高エネルギー状態の光を使った光子・光子散乱の観測実験がこれまでにいろいろと試みられている。日本では2014年に東京大学と理化学研究所が、X線自由電子レーザー施設(SACLA)で10keVオーダーのX線を用いた光子・光子散乱の直接観測実験を試みたが、このときには散乱断面積の大きさが届かなかったようで実際に光子・光子散乱を確認するには至らなかった。
今回、CERNの研究チームが行った実験では、鉛イオン同士を加速器内で衝突させ、このとき鉛イオンの周囲に発生する大量の光子の束を粒子検出器アトラス(ATLAS)で観測するという方法がとられている。鉛イオン同士の核子あたりの重心系衝突エネルギーは5.02TeV(テラ電子ボルト)である。
高エネルギー状態での重イオン衝突によって発生した光子同士が相互作用する現象は「超周辺衝突(UPC:ultra-peripheral collisions)」と呼ばれる。衝突するイオンの陽子数に対応して電磁場強度が強まり、強い相互作用の影響が出なくなるのが超周辺衝突の特徴であるとされる。
鉛の原子核の場合、陽子数82なので電磁場強度が最大1025V/mとなって、シュウィンガー限界と呼ばれる値(仮想電子が電磁場中で加速され、相対論的効果によって質量が増大することで実電子になって真空から飛び出せるようになる電磁場の強さ)を上回る。このため超周辺衝突ではQEDの効果が大きく効いてくる。今回の光子・光子散乱の観測では、この効果が利用されている。
重イオン衝突実験は2015年に実施され、40億回以上の事象のデータが収集された。これらのデータを分析したところ、光子・光子散乱の可能性がある13個の候補データが見つかったという。バックグラウンド事象に対する統計的有意性が標準偏差4.4σという値になったことから、研究チームはこれらのデータが偶然生じた誤差ではなく実際に光子・光子散乱であったと結論づけた(標準偏差が4σの範囲から外れる確率は0.006%)。また、これらのデータから測定される散乱断面積の大きさも、標準模型からの予測値に適合したと報告されている。
LHCでの次回の重イオン衝突実験は来年2018年に予定されており、光子・光子散乱についてもさらに研究を続けるとしている。多くのデータを集めることで、より精度の高い結果が得られるようになるとみられる。
QEDの理論では、真空とは何もない空っぽの空間ではなく、粒子と反粒子のペアが生成消滅を繰り返している動的な場であると考えられている。この理論を実験的に検証していくことで、真空と素粒子の理解がさらに深まり、宇宙が誕生した仕組みなどの根源的な謎に迫ることができると期待されている。