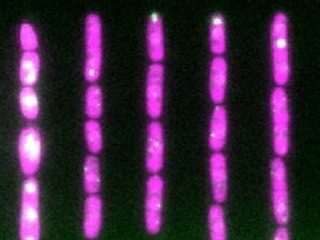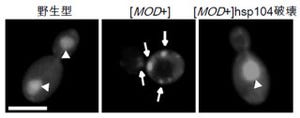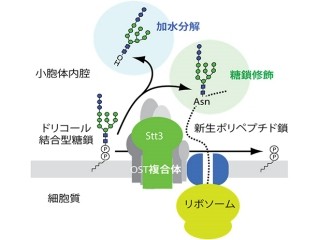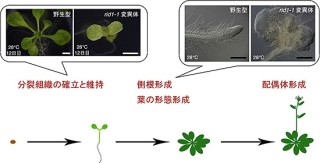理化学研究所(理研)は、出芽酵母の「化学遺伝学アプローチ」を用いて化合物(薬剤)の標的分子を予測/同定する方法を開発したことを発表した。この方法は、大腸菌、分裂酵母などの微生物、さらには動物細胞でも同様に活用可能で、ヒト細胞を用いれば、新しい有用薬剤の発見など創薬研究に貢献するものと期待できるという。
同成果は、理研環境資源科学研究センター、東京大学、ミネソタ大学、トロント大学の国際共同研究グループによるもの。詳細は、国際科学雑誌「Nature Chemical Biology」(オンライン版)に掲載された。
創薬研究においては、化合物(薬剤)が作用する生体内や細胞内の標的分子(タンパク質)を同定することが重要だ。化合物の標的分子の同定には、それらの物理的相互作用を直接的に検出する方法がある。しかし、化合物と標的タンパク質の結合力が弱い場合や試験管内で細胞内の生理的条件を再現できていない場合などは同定が困難だった。
これまでの研究から理研の研究チームは、出芽酵母の二重遺伝子破壊株の合成致死性を調べて、網羅的な「遺伝子-遺伝子相関性」を明らかにし、そのデータベースを作成していた。今回、国際共同研究グループは、出芽酵母の遺伝子破壊株を化合物で処理することで、化合物の感受性を測定するという化学遺伝学アプローチを採用。そこから得られた化合物-遺伝子相関性の情報を理研のデータベースと照合することにより、化合物の標的分子とその機能を予測/同定できることを示した。
また、この化学遺伝学アプローチと「バーコードシークエンス法」を組み合わせることにより、数百の化合物の標的分子の予測/同定を行う方法も確立した。これにより、理研の天然化合物バンク(NPDepo)をはじめ合計7つの化合物ライブラリーに所蔵される化合物1万3,524個についてスクリーニングを行い、出芽酵母遺伝子との相関プロファイルを作成し、化合物の標的機能の注釈付けを実施。その結果、NPDepoライブラリーには17の生物学的プロセスのうち大部分を標的とするさまざまな化合物が含まれているのに対し、米国の国立衛生研究所(NIH)や国立がん研究所(NCI)の化合物ライブラリーの化合物の標的機能には偏りがみられることを確認したとする。
なお、研究グループでは、今回開発した方法は新しい有用化合物の作用メカニズムの解明を進めるための有効な手段になると説明している。