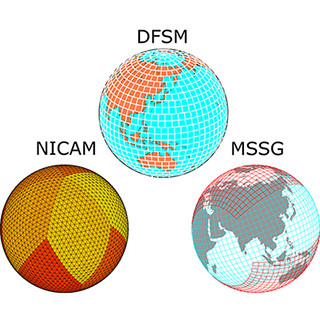気象庁気象研究所は、スーパーコンピュータ「京」によって台風全体を高分解能で計算し、海上の台風の地表面付近、特に台風の最も風速が強い領域における風の微細構造明らかにしたと発表した。
同研究は、気象庁気象研究所及び東京大学大気海洋研究所の伊藤純至、海洋研究開発機構の大泉伝、東京大学大気海洋研究所の新野宏らの研究グループによるもので、同研究成果は、6月19日付でSpringer Nature社出版の国際学術誌「Scientific Reports」誌に掲載された。
台風の暴風は、時間的・空間的に大きく変動する1km以下のスケールの微細構造を持ち、その微細構造による強風が被害を大きくするが、観測の機会や高分解能な観測手段が限られているため、微細構造は明らかになっていない。観測の不足を補うため、数値シミュレーションによる台風の再現結果を用いる研究が期待されているが、台風に伴う微細構造を解像する高い分解能で台風全体を覆うような計算は従来のコンピュータでは不可能であった。同研究では、理化学研究所のスーパーコンピュータ「京」を駆使し、広い計算領域と、現業予報よりもはるかに高分解能で地表面付近の微細構造をも解像する「台風全域ラージ・エディ・シミュレーション(台風全域LES)」を実現し、台風の地表面付近における微細構造を明らかにした。
地表面付近の鉛直方向の速度をみると、水平方向に数100m~数kmごとに、線状の上昇流域と下降流域が交互に並んでいる様子がみられた。また、地表面付近には周期的なロール状の流れのパターンがみられ、台風中心からの距離によって、異なる特徴をもつ3種類のロール構造「タイプA:半径20kmより外側でみられ、ロールの軸は周方向からやや内向き」、「タイプB:半径12km~20kmの範囲でみられ、ロールの軸は半径方向へ向く」、「タイプC:最大風速半径より内側の半径12km~8kmの範囲にみられ、ロールの軸は周方向からやや外向き」に分類された。タイプAロールは、既往研究でもその存在が予想されていたが、タイプBとCは同研究で初めて計算されたロール構造となる。
地表面付近で台風中心へと吹き込む風は、壁雲に近づく上昇流に転じる。その際、風速の高度分布には風速の極大が形成されるが、タイプBはそのような風速分布が原因となって生じるロール構造と考えられる。タイプCは壁雲の近くの接線方向の風速が最大となる半径付近にだけ生じており、回転の効果が著しく強い場合にのみ生じる特殊な不安定現象が発現したものと考えられる。タイプA、Bによる海面から壁雲への水蒸気の輸送は、台風の壁雲を構成する積乱雲の駆動源となる一方で、タイプCの存在は地表面付近に限定されている。タイプCでは、下降流が上空の大きな運動量を地表面付近に運ぶことにより、顕著な突風を引き起こしており、突風率の標準値よりもはるかに大きな値が局所的に生じていた。
以上のように、本研究で行った台風全域LESにより、これまでほとんど未解明であった、台風の中心に比較的近い領域の地表面付近に存在する微細構造の特徴と生成機構が明らかになった。今回得られた結果は、台風の地表面付近の未知の物理過程を明らかにするという学術的な貢献に加えて、地表面付近で起こりうる突風に関する防災上重要な情報を与え、また、数値予報モデルで台風の強度をよりよく予報するための有用な情報を与えるという。観測技術の向上により、同研究によって新たに存在が示唆された2種類のロール構造について、今後、存在が確認されることが期待されるということだ。