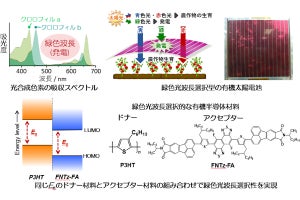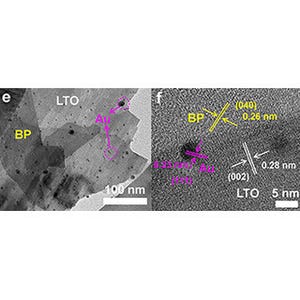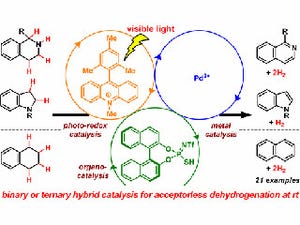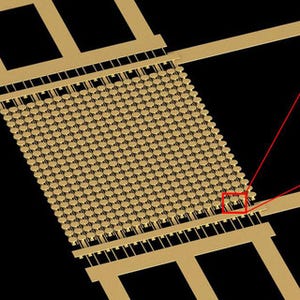米国ブルックヘブン国立研究所(BNL)は、太陽光と水を利用して水素を生成する人工光合成向けの光触媒を開発した。研究を進める中で、どのような形態の触媒が人工光合成の効率を高めるかについて、新しい知見が得られたという。研究論文は、米国化学会誌「Journal of the American Chemical Society」に掲載された。
同チームが開発した人工光合成用触媒は、2種類の光触媒が組み合わさって、1つの「超分子」を形づくるように設計されている。超分子は、ルテニウム金属イオンの触媒反応中心を複数もった光吸収部と、ロジウム金属イオンの触媒反応中心1個をもった水素生成反応促進部、さらにこれらの部位の間をつなぐ架橋分子から構成されている。ルテニウム触媒部が吸収した光によって励起された電子が、架橋分子の働きによってロジウム触媒部に伝達され、水素生成反応に使われる仕組みである。
ルテニウム触媒の反応中心の個数は3個または6個のものが作られているが、これまでの研究から、反応中心を6個にすると、3個のときと比べて触媒性能が大幅に上がることが分かっていた。具体的には、ルテニウム触媒3個の場合には、1触媒分子に対して生成される水素分子は40個だけだったが、6個にした場合は効率が7倍以上も良くなった。また、触媒の持久性についても、ルテニウム触媒3個の場合は反応開始から4時間で触媒機能が消えてしまったが、6個の場合には10時間300サイクルに及ぶ反応で触媒機能が持続した。しかし、これらの触媒の構成要素は非常によく似ているため、なぜこれほど大きな性能差が現れるのか当初はよくわからなかった。
研究チームは、酸化還元反応中の電位の状態を調べるサイクリックボルタンメトリなどの手法を用いて、この超分子系で起きている反応を調べる研究を続けた。その結果、ルテニウム触媒6個の系では、3個の系に比べると電子がやや少ないため電子をより受容しやすくなるということがわかった。このことから、ルテニウム触媒6個の系のほうが、電荷伝達の上で都合が良いのではないかという仮説が立った。
この仮説を検証するため、レーザーパルスの照射によって分子が励起してから、励起状態が消えて元に戻るまでの時間を測定する実験を行った。ナノ秒過渡吸収分光法と呼ばれる分析手法である。その結果、励起状態で分離した電荷がルテニウムからロジウムへ伝達される現象が、ルテニウム触媒6個の系だけに存在していることが明らかになり、仮説が裏付けられた。また、励起状態での電荷分離が予想よりもかなり速いスピードで起きていることもわかった。今回の測定機器では電荷分離の速さに追いつけなかったため、今後はさらに時間分解能を上げた測定実験を計画しているという。
論文の筆頭執筆者Gerald Manbeck氏は、「複数のプロセス間での反応速度が異なっていることが、高効率な水素生成を行う分子システムの開発を難しくしている」と指摘する。分離した電荷が再結合して熱を生じる前に触媒反応による水素生成を終わらせる必要があり、これが触媒開発の大きな課題のひとつになっているという。
また、水素分子1個を生成するためには電子2個が必要なので、触媒反応では2個目の電子が現れるまで1個目の電子を保持しておかなければならない。したがって、触媒の性能を上げるためには、独立に働く複数の光吸収部をもった超分子を設計することで利用可能な電子の発生確率を上げたり、光が弱い条件下でも機能するように分子の能力を改良したりする必要がある。こうした事情が触媒分子の開発を複雑にしているという。
今回の研究を通して、ルテニウム触媒6個の系の優位性や電荷分離のメカニズムなどがわかってきたことで、さらなる触媒開発につながるだろうと研究チームは強調している。