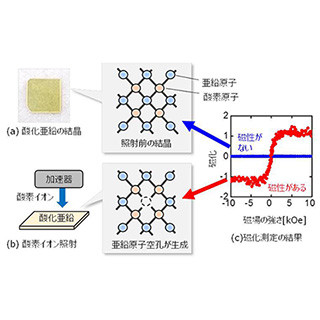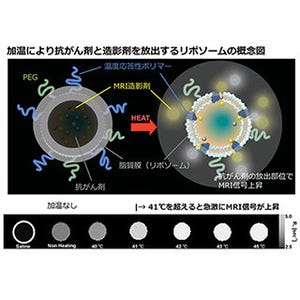量子科学技術研究開発機構(量研機構)は5月15日、20世紀から続く物理学の問題のひとつである光子と光子の相互作用を検証する方法を理論計算により発見し、新しい実験手法を提案したと発表した。
同成果は、量子科学技術研究開発機構関西光科学研究所 ジェームズ・コーガ上席研究員、高崎量子応用研究所東海量子ビーム応用研究センター 早川岳人上席研究員らの研究グループによるもので、5月17日付けの米国科学誌「Physical Review Letters」オンライン版に掲載された。
20世紀の量子電磁力学(QED)の登場によって、電磁気力と光が新しい理論で記述されるようになった。QEDは従来の常識に反して、光子と光子が合体や散乱などの相互作用を行うことを予言したが、このような現象が実際に発生する確率は極めて小さく、計算も困難であるため研究はあまり進展しなかった。
光子と光子の相互作用のひとつに「デルブリュック散乱」がある。デルブリュック散乱とは、光子が原子核の近傍で電子と陽電子を生成した後に対消滅して再び光子を生成する現象であり、見かけ上は光子が原子核によって散乱されたように見える。20世紀には、主に原子炉で生成した放射性同位体を用いて実験が進められていたが、この方法ではデルブリュック散乱のみを計測することができないという問題が理論的に明らかになり、1990年代以降研究は停滞していた。
しかし21世紀に入ると、レーザーと加速器技術が急速に進展し、高輝度レーザーコンプトン散乱ガンマ線ビームが近い将来に実用化されようとしている。この高輝度ガンマ線ビームの特性を活かした実験を行えば、デルブリュック散乱のみを選択的に計測できる可能性がある。
同研究グループは今回、理論計算によりデルブリュック散乱のみを計測可能な実験条件を求め、世界で建設中の高輝度レーザーコンプトン散乱ガンマ線ビーム装置によって、実験可能であることを明らかにした。光子と光子の相互作用を検証するさまざまな実験が提案されているが、同研究グループは、高い精度で5年以内に実現可能なのは本提案のみと言っても過言ではないと説明している。今後、今回の結果についての検証が期待される。