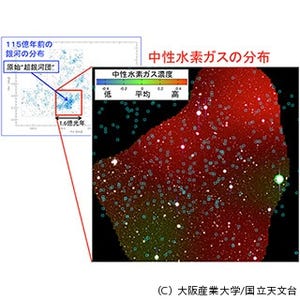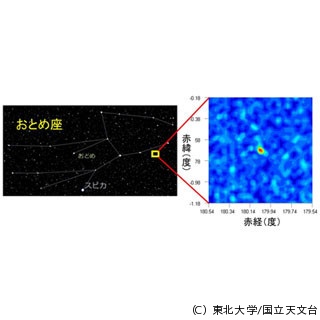国立天文台などは5月18日、観測ロケットCLASPを使った紫外線偏光観測によって、太陽上空の構造を調べることに成功したと発表した。
同成果は、国立天文台、宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所、アメリカ航空宇宙局マーシャル宇宙飛行センター、カナリア天体物理学研究所、フランス宇宙天体物理学研究所らの研究グループによるもので、国際科学誌「The Astrophysical Journal Letters」および「The Astrophysical Journal」に掲載される。
温度6000度の太陽表面より外には、彩層(約1万度)・遷移層(1万~100万度)・コロナ(100万度以上)といった高温な太陽大気が広がり、大気中では太陽フレアやジェットなどさまざまな活動的現象が起きている。しかし、このような高温で活動的な太陽大気が低温な表面の上空に存在できる理由は、未だ解明されていない。
表面から大気へエネルギーを供給するメカニズムとして、磁場が重要な働きをしていると考えられ、太陽表面での精密な磁場観測は数多く行なわれてきた一方で、加熱と活動の現場である彩層からコロナでの磁場観測は難しく、その知見は限定的となっている。
今回の研究で利用されたCLASP(Chromospheric Lyman-Alpha SpectroPolarimeter)は、日米仏が共同開発した観測装置。2015年9月3日にアメリカ・ホワイトサンズ実験場からNASAの観測ロケットにて打上げられ、宇宙空間を飛翔する約5分間、太陽表面から数千kmほど上空にある彩層・遷移層が放つ紫外線(ライマンα線、波長121.6nm)の偏光を観測した。
この結果、太陽が出すライマンα線が散乱偏光していることが明らかになった。偏光の強度は理論モデルの予想と大筋で合っていたが、空間的に細かいスケールで偏光の様子が変化していることなど、太陽の彩層・遷移層が想像されていた以上に複雑な構造をしていることが示された。また、彩層上部~遷移層に磁場が存在しているということを示す結果も得られている。
現在は、CLASPより回収された光学素子と観測装置本体を再利用した再飛翔実験CLASP2計画が、2019年の打上げ・観測実施に向けて始動している。CLASP2では、観測するスペクトル線をライマンα輝線と同様に有用だと考えられている電離マグネシウム線(280nm)に変更する予定。電離マグネシウム線では、ライマンα輝線で観測した直線偏光に加えて円偏光を観測することができるため、磁場情報がより正確に把握できることが期待されている。