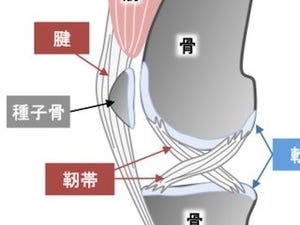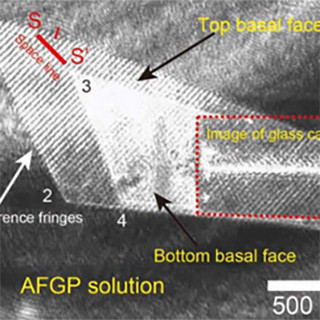大阪府立大学と北海道大学は27日、大阪府立大学 大学院 生命環境科学研究科の高野順平教授と汪社亮研究員、北海道大学 大学院 農学研究院の内藤哲教授らは、植物のホウ酸輸送体のひとつが土壌側の細胞膜に偏って局在する仕組みの一端を解明し、偏った局在が植物体としての栄養獲得に有利であることを実証した。加えて、ホウ酸輸送体と近縁の輸送体を改変して局在を人為的に土壌側に強く偏らせることに世界で初めて成功したことを発表した。この研究成果は3月24日、国際誌「The Plant Cell」オンライン版で公開された。
この研究は、大阪府立大学、北海道大学、岡山大学、京都大学の共同研究で、日本学術振興会による最先端・次世代研究開発支援プログラムと科学研究費補助金の支援を受けて実施されたもの。
植物は細胞を包む細胞膜に埋め込まれた輸送体を利用し、土壌から栄養素を吸収する。その栄養素を茎や葉へ運ぶためには根の表面の細胞で栄養素を取り込み、根の中心部に位置する導管まで届ける必要があり、根の細胞内で土壌に面した側、もしくは導管側(根の内側)に偏って分布する輸送体が次々と見つかっている。栄養素の輸送体が偏って局在することは土壌からの栄養素獲得、そして導管への輸送に重要であると考えられてきたものの、その証明はこれまでなされていなかった。
今回、同研究グループは、シロイヌナズナのホウ酸輸送体(チャネル)である「NIP5;1」が、根の細胞において土壌側の細胞膜に偏って局在する仕組みの一端を解明した。NIP5;1は特徴的な繰り返しアミノ酸配列を持っており、リン酸化されるとエンドサイトーシスという機能により細胞内に積極的に取り込まれ、土壌側の細胞膜に再配置される。続いて、繰り返しアミノ酸配列を改変してNIP5;1 の分布の偏りを弱めると、ホウ酸の土壌から茎葉への輸送効率が悪くなることを示した。これにより、植物の栄養素の輸送体が偏って局在することの重要性を世界で初めて証明した。
さらに、NIP5;1のアミノ酸配列を利用して、NIP5;1に全体の構造が似ている輸送体を人為的に局在をより強く偏らせることにも成功したということだ。
現在、世界の耕作地において、土壌の栄養欠乏や毒素蓄積が重大な問題になっているが、今回の研究が輸送体の細胞膜内での局在を人為的に制御する道を拓いた。これをさまざまな輸送体に応用することで、栄養素の根での吸収や可食部への蓄積を高めたり、重金属などの毒素の吸収や蓄積を低減させたりすることが可能になると期待される。