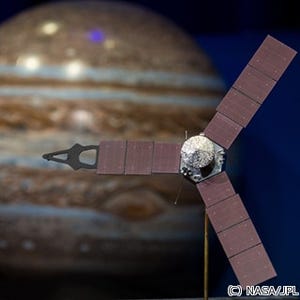国立極地研究所、国文学研究資料館、京都大学等の研究者からなる研究グループは、「明月記」などの古典籍に残されたオーロラの記述と、樹木年輪の炭素同位体比を比較することなどにより、平安・鎌倉時代における巨大磁気嵐の発生パターンを明らかにした。同研究は米国地球物理学会の発行する学術誌「Space Weather」にオンライン掲載され、同誌のEditors’ Highlightに選ばれた。
現代は太陽活動が激しくなっており、磁気嵐が発生することで、地上では大規模な停電、宇宙では人工衛星の故障を引き起こすといった実被害に結びつく危険性があることから、「宇宙災害」という言葉も生まれている。同研究では、日本および中国の古典籍の記述と、過去の太陽活動の指標となる樹木年輪の測定結果から、過去の巨大磁気嵐の発生パターンを解明することを試みた。
藤原定家(1162-1241)が残した「明月記」には、1204年2月21日と23日、京都で「赤気」(オーロラ)が見えたとの記述がある。これは、1週間のうちに何晩も、京都のような緯度の低い地域でオーロラが観測された「長引く赤いオーロラ」の記録として、これまでに調査されている中では日本で最古のものになる。
中国の歴史書「宋史」には、同2月21日に、太陽に大きな黒点が観測されたと記されている。これらの記述は、現代的な観測データから推定する限り、太陽から噴き出たコロナ質量放出が何度も地球に直撃することで、大きな磁気嵐が単発で終わらず何度も発生する「連発巨大磁気嵐」が起こっていたと考えられる。過去の研究でそれぞれの文献についての調査はなされていたが、今回2つの文献の記録を突き合わせることで、約800年前に巨大な磁気嵐があったことが、「地球での現象」と「太陽の現象」の両面から再確認された。
同研究グループは、さらに時代を遡って連発巨大磁気嵐の発生パターンを検討するため、「宋史」における900年代~1200年代の「長引く赤いオーロラ」の記録と、太陽活動の強弱を反映する樹木年輪の炭素同位体比の測定データを比較した。その結果、太陽活動の極小期前後よりも、極大期付近に多くオーロラの記録がされていたこと、また、太陽活動が長期的に弱くなった1010~1050年には、そのような「長引く赤いオーロラ」の記述がないことが明らかになった。
このたび得られた知見は、科学的には、将来起こりうる最悪の宇宙環境を理解、予測し、「宇宙災害」への具体的な対策を立てる上で重要となる。また、人文学的側面としては、過去の宇宙環境が解明されることで、古典籍の読み方も変化し、当時の人々の天文観へのより深い理解に役立つことが期待される。
なお、同研究は、総合研究大学院大学の複合科学研究科極域科学専攻と文化科学研究科日本文学研究専攻の学融合共同研究事業「オーロラと人間社会の過去・現在・未来」及び「日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画」の中で実施された。