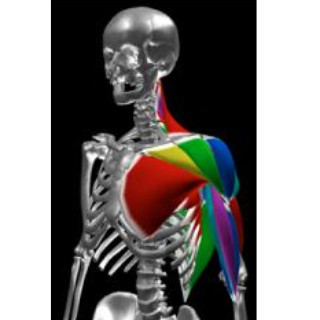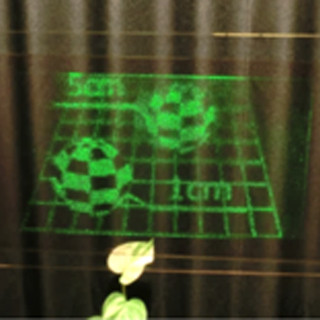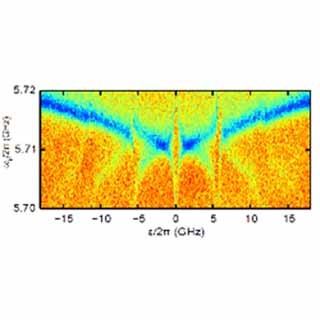情報通信研究機構(NICT)は2月22日、「どのようなものを見ているのか」という知覚判断は、見た内容だけでなく、見た内容に伴う運動行為にかかる負荷を反映していることを実験的に証明したと発表した。
同成果は、NICT脳情報通信融合研究センター(CiNet)の羽倉信宏 研究員、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)およびウェスタンユニバーシティらで構成される研究グループによるもの。詳細は神経科学の国際科学誌「eLife」(オンライン版)に掲載された。
これまで、脳への入力情報の処理である知覚判断と、脳からの出力情報の処理である運動行為は、それぞれ独立なものであると考えられてきた。そのため、例えば木に実っているブドウを取ろうとして、跳び上がるも、なかなか取れずに最後は、あのブドウはすっぱくてまずい(熟れていない)と言って去っていくという話がイソップ寓話にあるが、この場合、一番熟れている葡萄を選び出すための入力処理(知覚判断)と、その葡萄を取ろうとする運動を作り出すための出力処理(運動行為)は独立であり、運動行為は単に知覚判断を反映するためだけのものということになる。
今回、研究グループは、この定説が正しいかどうかを確かめる実験を実施。その結果、運動行為にかかる負荷が視覚入力の知覚判断に影響を与えることを確認し、結果として、見ているものが何であるのかを判断するときは、視覚による情報のみではなく、判断の報告に至るまでの処理すべてを利用して行っていることが示されたことになるという。
今回の成果について、研究グループでは、「運動行為にかかる負荷が想像以上に私たちの意思決定に反映されているという結果は、例えば、製品の見た目によるデザインと、使いやすさ(行為の負荷)は独立でないことを示唆しており、新しい製品デザインの開発などに役立てられることが期待される」と説明しているほか、今後は、ヒトの日常行為は、些細な癖が存在するなど、必ずしも適応的ではないことから、そのような非適応的な行為の負荷を増やすような環境をデザインすることで、ヒトの情報処理・行為の適応性を高めるような研究も進めていく予定としている。