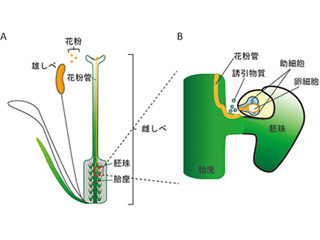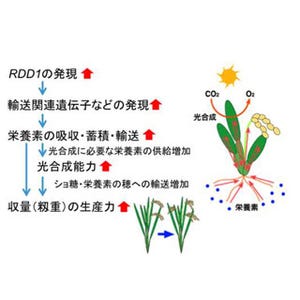岡山大学と農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)は5月16日、オオムギの休眠を制御する新たな仕組みを発見したと発表した。
同成果は、岡山大学 資源植物科学研究所 佐藤和広教授、農研機構 小松田隆夫主席研究員らの研究グループによるもので、5月18日付の英国科学誌「Nature Communications」オンライン版に掲載された。
現在栽培されているオオムギの祖先となった野生オオムギは、中東を中心に自生しており、秋から春にかけて生育するが、成熟後、夏の高温乾燥を耐えるために発芽を一定期間休止し、数カ月を種子の状態で休眠して過ごすことが知られている。
現在、世界で栽培されているオオムギは、地域やその用途によって種子休眠の長短に大きな差がある。たとえば、ビールやウイスキー用のオオムギは、醸造を効率的に行うため、休眠が短く、一斉に発芽するものが適している。しかし、日本や北欧などの収穫期に雨の多い地域では、休眠が短い品種などで穂についたまま芽の出る穂発芽が発生し、農業生産に大きな損害が出ている。
今回、同研究グループは、野生オオムギに存在する主要な種子休眠性に関わる「Qsd1」のDNA配列を決定。遺伝解析に用いた種子休眠に差のある品種の遺伝子配列を解析し、遺伝子内のアミノ酸のひとつが変化することで、休眠性遺伝子が休眠型から非休眠型に変わることを突き止めた。
さらに、Qsd1はこれまで植物種子の休眠性では報告のないアラニンアミノ酸転移酵素を制御することを発見した。従来、植物の種子の休眠にはアブシジン酸(ABA)などの植物ホルモンが関わっていると考えられていたが、今回解析されたオオムギの種子休眠性遺伝子は、植物ホルモンの作用とは直接的に関わりのない原因で制御されていることが明らかになった。
また、300品種あまりの野生オオムギと栽培オオムギのQsd1遺伝子配列を比較したところ、休眠性が短くなった品種では同じ部分の配列が変異してアミノ酸が変わり、別のタンパク質として発芽を促進することがわかった。これらの休眠の短い品種の多くは醸造用で、遺伝子配列を解読した進化解析の結果、その祖先はイスラエル付近(南レバント)の野生オオムギに起源することが示された。イスラエル起源の野生オオムギは、その後、栽培オオムギとしてヨーロッパに伝わり、チェコや英国を中心に醸造用オオムギとして改良された際に休眠性が短くなり、近代になって日本を含む世界各地に伝わったことが明らかになった。
同研究グループは、Qsd1が種子の胚のみで特異的に働くことも明らかにしており、今回の成果を用いて遺伝子鑑定による休眠性の長短を制御することで、醸造業や収穫時に雨の多い地域のオオムギ生産に貢献することが期待されるとしている。