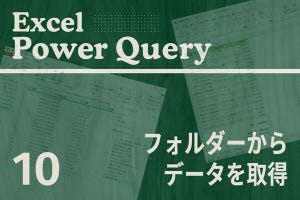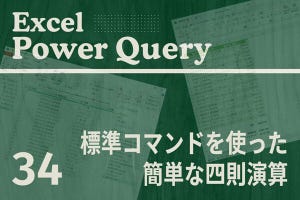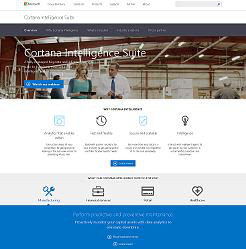米Microsoft主催の開発者会議「BUILD 2016」が米カリフォルニア州サンフランシスコで3月30日~4月1日(現地時間)にかけて開催された。Windows 10の次期大型アップデートやHoloLensの出荷開始、botサービス用フレームワーク提供など盛りだくさんな情報で話題となっていた同イベントだが、本稿では特にエンタープライズまわりの話題を中心に重要トピックをおさらいしてみたい。
このBUILD 2016では大小合わせてさまざまなトピックが発表されており、その内容は非常に多岐にわたる。そのまま羅列するだけでは膨大な量となるため、本稿では「Windows 10エコシステム」「Office 365」「Microsoft Azure」にカテゴリを大別して、ポイントを押さえていく。発表内容的には「Windows 10エコシステム」が開催1日目の基調講演、「Office 365」「Microsoft Azure」が2日目の基調講演での発表内容をベースにしている。基調講演の模様はオンデマンド配信でいつでも確認可能だが、それぞれ3時間近いセッションのため、まずはポイントを把握しておくといいだろう。
UWPアプリへの移行を促すMicrosoftの施策
BUILD 2016では、これまで「Redstone (RS1)」の名称で呼ばれていた次期Windows 10の大型アップデートの正式名称が「Windows 10 Anniversary Update」となり、今年2016年夏の提供となることが発表された。昨年2015年11月に提供が行われた「November Update (1511)」では新機能らしい新機能の追加はほとんど行われなかったが、Anniversary Updateではいくつか重要な機能追加が行われている。中でも開発者にとって特に重要だと思われる新機能は次のものだ。
- Windows Helloの生体認証がアプリやEdgeでのWebアクセスで利用可能に
- ロックスクリーン状態でもCortanaを通じて(アプリなど)各種機能へのアクセスが可能
- UWP(Universal Windows Platform)アプリがXbox Oneでも利用可能になり、Xbox Dev ModeでSDKを通じてアプリ開発が可能に
前2者はアプリのフロントUIとしてWindows 10固有の機能が利用できることを意味しており、使い方しだいではアプリやサービスの利便性を向上できるだろう。Xbox Oneについては一般的なアプリが対象というよりも、どちらかといえば「Windows 10 PCとXbox Oneの両方で動作するゲームをクロスプラットフォーム開発する」という意味合いが強い。デバッグ機能がXbox Oneに付与されることで、直接ゲームコンソール上で各種作業が可能になるメリットがある。この話題そのものはエンタープライズには大きな影響はないかもしれないが、Microsoftのスタンスとして「既存アプリケーションのUWPへの移行」を積極的に推し進めたいという考えの現れであり、Anniversary Updateの提供が1つの転換点だといえるのかもしれない。
この考えは、同社が発表した「Desktop App Converter」にも現れている。これは従来まで「Project Centennial」と呼ばれていたもので、昨年のBUILD 2015で発表され、今回初めてデモストレーションを交えて紹介が行われた。既存のデスクトップアプリケーションに対して、UWPと同じようにWindows Storeを通じて配布が可能なパッケージ形式に変換する仕組みであり、コードを徐々に書き換えていくことで将来的に完全なUWPアプリとして動作が可能となる。変換された直後のコードはWin32や.NETといった従来環境にそのまま依存しているため、手動で変換作業を行わない限りはWin32サブセットを持たないWindows 10 Mobileなどでは動作しない。そのため、位置付け的にはレガシーアプリケーションをUWPへの移行していくための暫定策のようなものだといえる。
またUWPだけでなく、AndroidやiOSを含むプラットフォームを横断したクロスプラットフォーム開発を推進していく方針を示しており、この中核として今年2月に買収を発表した「Xamarin」を据えていくようだ。Xamarinは.NETとC#をベースとしたクロスプラットフォーム開発環境であり、この元となったプロジェクトの草創期から開発を手がけているMiguel De Icaza氏が自らステージ上で自らデモを披露し、コード記述からエミュレータによるテストまで、すべてをVisual StudioとXamarin上で実現できることを紹介している。なお、Visual StudioユーザーにはXamarinの無償ライセンスが提供されることが発表され、MicrosoftによるXamarin買収効果が直接デベロッパーに恩恵となって返ってきた形だ。これは無償のCommunity Editionでも利用できる点も大きい。このほか、Xamarinランタイムのオープンソース化の発表や、1000以上の実デバイスでの自動テストを実行できる「Xamarin Test Cloud」の紹介も行われており、Windows 10以外のスマートデバイスをもターゲットにする場合の開発手段として、有力な選択肢となるだろう。
Office 365を拡張するツール群
今回のBUILD 2016ではすでに発表済みのものも含めて、Office 365周辺の新サービスに関する話題が豊富だった。
●Microsoft Graphとアドインモデル
Microsoft GraphはOffice 365上の各データに直接アクセス可能なAPIとサービスの総称で、すでに昨年2015年秋に提供が開始されている。各種メールや連絡先、予定表、Officeファイルまで、Graphを通じてデータに触れることができ、これを利用してサードパーティがさらに新しいアプリやサービスを開発できるという点が特徴だ。さらにHTML5などWeb標準技術を使った「アドイン」による拡張の概念をOfficeアプリでは取り入れており、実際に基調講演の壇上ではStarbucksがOutlook向けのプラグインを介したプロモーションの実例を披露している。この種のアドインはWebやPCだけでなく、iOSなどのスマートフォンアプリでも利用可能であり、デバイスの種類を選ばない。
●Office 365 GroupsとOffice 365 Connectors
Office 365 Groupsは、Office 365上のユーザーを自由に組み合わせてグループ化が可能な仕組みで、グループ化されたユーザーの間では共通のInboxを共有することになる。ここでは各種事務連絡や情報共有、議論などが記録されていくが、Office 365 Connectorsを組み合わせることで、例えばTwitterやBing Newsなど、さまざまな外部サービスをフィードとして取り入れて、Inbox上に簡単に蓄積できる。これらの追加情報はフィルタリング処理のほか、各メンバーが自由に追加可能で、Connector自体も自ら開発が可能だ。Connectorの詳細に関しては専用ポータルが公開されており、そちらを参照してほしい。
基調講演ではこのほか、「Power BI」の埋め込みツールを使ったHighspotというサービスのデモストレーションを行っている。ここではWeb上に直接Skype機能を埋め込み可能な「Skype Web SDK」や、同機能をAndroidやiOSアプリにも埋め込める「Skype for Business App SDK」、さらに各種ソーシャルネットワークやチャットサービスで利用可能な自動応答システムを実装可能な「Microsoft Bot Framework」など、各種機能を簡単に自社のカスタマイズアプリやサービスに取り込む様子が紹介されている。
Microsoft Azure関連の新トピック
Microsoft Azure関係でも複数の話題が出ている。上記の項目でもすでに紹介済みのものが含まれるが、すべてのアップデート内容や詳細についてはMicrosoft Azureのページを参照してほしい。
- マイクロサービス型アプリケーションの実行基盤「Azure Service Fabric」の一般提供を開始
- Service Fabric for Windows Serverのプレビュー版、Service Fabric on Linuxのプライベートプレビュー版の提供を開始
- Azure IoT Starter Kitsの販売を開始
- Power BI Embeddedのプレビュー版提供を開始
- Azure DocumentDBの新価格体系とスケーリング対応
- MongoDB APIとドライバを介したDocumentDBへのアクセス手段を提供
全体を通しての感想として、昨年のBUILD 2015ではWindows 10リリース直前ということもあり、やはりWindows 10やUWPに関する部分に話題が集中していた感があったが、今回はそれよりもむしろOffice 365やMicrosoft Azure、特にクラウドを介して異なるプラットフォームやデバイス同士がいかに連携して企業における生産性を高めるかという点にフォーカスが当たっていた印象を受ける。おそらくは、Microsoftとしてのビジネスの主軸も「クラウド」「Office」「エンタープライズ向けの施策」に移ってきていることの証左ともいえるかもしれない。