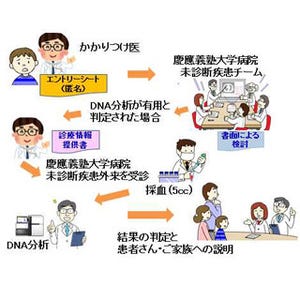理化学研究所(理研)は3月17日、アルツハイマー病モデルマウスの失われた記憶の復元に成功したと発表した。
同成果は、理研 脳科学総合研究センター 理研-MIT神経回路遺伝学研究センター 利根川進センター長、マサチューセッツ工科大学 博士課程 ディーラジ・ロイ氏らの研究グループによるもので、3月16日付けの英国科学誌「Nature」オンライン版に掲載された。
アルツハイマー病(AD)では、海馬およびその周辺で神経細胞の変性が始まることから、海馬の働きの異常がAD初期の記憶障害を引き起こしている可能性が指摘されていた。しかし記憶障害は、記憶を新しく形成できないために起こるのか、それとも形成された記憶を正しく思い出せないため起こるのか、そのメカニズムは不明となっていた。
同研究グループはこれまでに、光感受性タンパク質を特定の神経細胞群に発現させ、その神経細胞群に局所的に光を当てて活性化/抑制する技術「光遺伝学」を用い、海馬の「記憶エングラム」と呼ばれる細胞群に個々の記憶の痕跡が物理的に保存されることを証明している。今回、同研究グループは、ヒトのAD患者由来の遺伝子変異が導入されたADマウスを用い、記憶エングラムがどうなっているのかを直接調べることにした。
普通のマウスを実験箱Aの中に入れ弱い電流を脚に流すと、マウスはこの嫌な体験の記憶を形成し、翌日同じ箱Aに入れられるとその記憶を思い出して"すくむ"。一方、7カ月齢のADマウスは、嫌な体験をしてから1時間以内であれば箱A内ですくむが、翌日になるとすくまなくなる。つまり、ADマウスは、嫌な体験の記憶を作ることはできるが、24時間後にそれを想起することができなくなっていると考えられる。
そこで同研究グループは、神経が活動するとその発現が誘導される遺伝子の調節領域と標識する期間を限定させることができるTet-offシステムを用いて、ADマウスが箱Aで嫌な体験をしている最中に活動した記憶エングラム細胞において、光感受性タンパク質遺伝子ChR2が発現するよう標識。嫌な体験の翌日、箱Aに入れてADマウスがすくまないことを確認してから、別の実験箱Bに入れ、標識したエングラム細胞群を青色光により活性化すると、ADマウスはすくんだという。これは、ADマウスにおいても記憶エングラムは形成されているが、その記憶エングラムを正しく想起できないことから記憶障害が引き起こされている可能性を示唆している。
同研究グループはさらに、このADマウスにおける記憶想起の障害が、神経細胞同士をつなぐシナプスが形成されるスパインという構造の減少と関連していることを突き止めた。シナプスは何度も刺激されると増強されてスパインも増えるため、同研究グループは、シナプスを増強することでADマウスの記憶想起の障害を回復させられるのではないかと考えた。
そこで、もともと嫌な記憶と結びついていた実験箱Aに入れながら、標識しておいたADマウスの記憶エングラムへの入力を青色光によって人為的に何度も活性化させ、シナプス増強を起こしたところ、シナプスを増強したADマウスは、2日後に箱Aに入れられると、箱Aという自然な手がかりだけで嫌な記憶を思い出してすくむようになったという。
利根川センター長は今回の成果について、「少なくとも、AD病初期の患者の記憶は失われているのではなく、思い出すことができないだけなのかもしれないのです。初期の患者には記憶を保持する細胞が維持されているというのであれば、将来、これらの細胞から記憶を取り出す技術が開発されれば、障害を軽減できるかもしれません」とコメントしている。