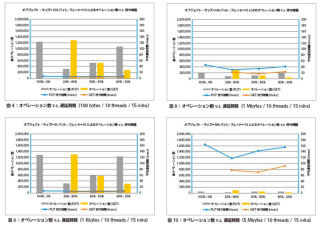レノボ・ジャパンは今年、設立10周年を迎えた。これに合わせて、11月11日に都内でメディア向け事業説明会を実施。日本アイ・ビー・エム(日本IBM)から続くThinkPadの歴史を振り返るとともに、今後の事業戦略について説明した。
「ThinkPadの父」が語るThinkPadと歩んだ道のり
まず、同社の取締役副社長である内藤在正氏の登壇からスタート。「ThinkPadの父」として知られる内藤氏は、1974年に日本IBMに入社してから、初代「ThinkPad 700C」の技術開発に関わるなど、ThinkPadの発展を支えてきた。
実は、日本が世界市場向けのThinkPad開発を担当していたということを知っている人はあまり多くないのではないだろうか。この背景として、日本IBMには、LCD ディスプレイ、HDD、低消費電力CMOS、高密度実装基板、PCチップセットなどPCを作るうえで重要な技術力が揃っていた。さらに、バッテリ、フロッピーディスクドライブ、キーボード、カーボンファイバーなどの分野で高い技術を持つ企業が日本に多く集まっていたことも挙げられる。
内藤氏は、ThinkPadの歴史を5つの世代に分けて紹介した。ブランド創世記である1992~1999年は、初代「ThinkPad 700C」を発表。多くの反響があり、ブランドとして好調なスタートを切った。しかし、ある時オーストラリアのユーザーからひどい壊れ方のPCが戻ってきたという。これを見たチームメンバー全員が愕然としたそうだ。当時70万円ほどの製品で、開発チームの中では「当然、大切に扱われるはず」という意識があった。しかし、これを機に「ユーザーがどのような使い方をしても、ストレスなく使用できる製品でなければならない」と意識を改め、「その後から、どこまでやったら壊れるか、PCの限界をテストするようになった」と語った。この出来事から、「製品ではなく使用しているPCの向こうにいるユーザーを見て開発する」といった考えを持つようになったという。
ブランドとして順調な滑り出しを遂げたThinkPadだが、第2世代となる2002~2004年は、苦しい時期だったと振り返った。多種多様なラインアップを取り揃えたThinkPadだが、当時のIBM会長にThinkPadの新機種を渡した時、「機種ごとにスイッチの位置が違う」という指摘を受けた。このことから機種間で整合性が取れていないことを認識し、シリーズや操作方法などを統一したそうだ。
この時代は、ITバブル以降の不況の時期とも重なり、ユーザーからは低価格の製品を求める声が上がっていた。しかし、IntelのMobile PentiumシリーズにTDP 8Wや16W、24Wモデルが登場して冷却機構が大型化。ノートPCの設計が難しくなるなど、厳しい時代だったと振り返った。
2005~2009年の第3世代はイノベーションの時代だったという。2005年に日本IBMのPC事業はレノボへ移籍、会社として大きく変化した時代だ。どのようにPCが壊れるかを検証するために「堅牢性試験ラボ」を設立。実際に米国の大学へ赴き、学生がどのようにPCを扱っているかを研究したそうだ。その他、冷却性能やワイヤレス性能が向上するなど操作性の向上に努めた。
2010年からの第4世代では、第3世代での努力が実を結び、ThinkPad製品の優位性が高まった。中小企業向けの機種を取り揃えるなどユーザー層も拡大。IBM時代の12年間では2500万台の出荷数だったのに対し、レノボになってからの9年間で7500万台を出荷するなど、着実な発展を遂げた。
2012年から現在までの第5世代では、IT機器の多様化を受けて、ThinkPad YogaやHelixのような2 in 1 PC、デジタイザー・ペンのLenovo Pen、クラムシェル型など新たなフォームファクタの提案などを行っている。「今後も横浜本社と米沢工場が一体となって、レノボPCの開発を牽引していきたい」と述べた。