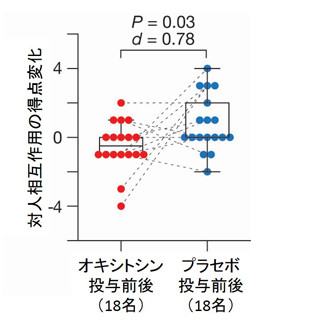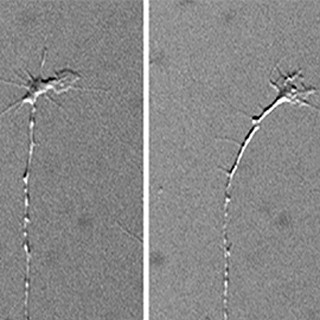国立精神・神経医療研究センター(NCNP)は9月15日、神経難病である多発性硬化症(MS)患者の腸内細菌叢について解析を行った結果、細菌叢構造の異常、特に特定の細菌で著しい減少がみられることを明らかにしたと発表した。
同成果はNCNP神経研究所 免疫研究部部長兼センター病院 多発性硬化症センターの山村隆 センター長、東京大学の服部正平 教授、麻布大学の森田 英利教授、順天堂大学の三宅幸子 教授の共同研究チームによるもの。9月14日(現地時間)に科学誌「PLOS ONE」オンライン版に掲載された。
MSは脳や脊髄、視神経に繰り返し炎症性の病変が生じる慢性疾患。視力障害や手足の麻痺、高次脳機能障害などの神経症状を伴う再発を繰り返しながら、徐々に神経障害が進行していく神経難病で、患者は全国に約2万人いると推定されている。日本では過去30年間で患者数が約1000人から2万人近くまで増加しているが、まだ原因ははっきり分かっていない。
近年、さまざまな自己免疫疾患に腸内細菌叢などが関与している可能性が注目されており、MSも自己免疫疾患の1つと考えられていることから、同研究グループは、患者数増加の背景に日本人の食生活の変化などが腸内細菌に影響を与え、発症しやすくなったのではないかという仮説を立て、MS患者の腸内細菌を構成する菌について研究を開始した。
今回の研究では、NCNP病院に通院中の20名の再発寛解型を示すMS患者の寛解期の糞便を解析し、糞便を構成する数百種類の菌種の同定、多様性の評価などを行った。その結果、MSの腸内細菌叢では健常者と比べて、炎症性のリンパ球に対して抑制的に機能するリンパ球を効率よく誘導する細菌と同じグループに属する細菌が減少していることが判明。この腸内細菌叢の異常が発症の危険因子になっている可能性が考えられるという。
再発頻度や再発症状の重症度などMSは個人差が大きい。同研究グループは今後、より多数の多様な背景をもった患者の腸内細菌叢の解析を進めることにより、同疾患の多様性を説明する因子が発見できる可能性があるとしている。