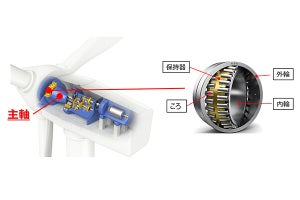シンガポールを拠点に世界中で照明デザインを手がける、Lighting Planners Associates 服部祐介氏。照明デザインという仕事、そのデザインプロセス、そして国による違いについて、彼が手がけたプロジェクトを巡りながら話を聞いた。
光だけでなく陰もデザインする
――"光をデザインする"ということについて教えて下さい。
光という存在自体は誰でも知っていますし、皆さんは日常的に光を体験していることだと思います。ただ、光が影響をおよぼす空間の印象や心地よさのようなものは、皆さんが無意識のうちに感じ取っていることが多いので、それをデザインするという仕事は分かりにくいかもしれません。
一言でいいますと、この仕事は照明に関する知識を利用して空間を光で演出する職業です。照明デザインと言うと舞台照明、映画照明など様々ですが、我々が専門としているのは建築照明、もしくはもう少し広義に環境照明という分野。照明器具をプロダクトとしてデザインしていると思われることも多いのですが、そうではなく、自然光や人工光(いわゆる照明器具)をツールとして空間をどのような光の環境にするかを考える職業なのです。建築、造園、電気設備など多岐にわたる知識を必要とするちょっと変わった職能かもしれません。
照明デザインの歴史は50~60年と浅く、それまでは職業として確立するまでは建築家が照明、主に自然光をどのように空間に取り入れるかを考えていたのですが、建築の用途が多様化し、照明のテクノロジーが複雑化し、専門職としての必要性が高まり生まれました。建築家だけでなく施工主が照明の重要性に気づき始めたことや、省エネが取り沙汰されるようになってからは、私たちの職能がさらに重要視されるようになってきました。
建築と私との出会いは、私がまだ高校生の頃に建築家 ル・コルビュジエの展覧会を訪れたことでした。大学で建築を学ぶようになり、そこで人が空間で感じる「環境」を形作るものには、音・光・空調の三つの要素があることを学びます。このとき初めて環境心理学という分野に出会い、大学院に進学以降、主に光環境について研究してつき詰めていくことになりました。ですから、実はデザインを学んだことはないんです。
照明デザインを専門に学べる大学は、アメリカ、スウェーデン、ドイツなどにはありますが数は少ないんです。ですから、私が勤めているLighting Planners Associatesという照明デザインの会社には、さまざまなバックグラウンドを持ったひとたちが集まっています。電気設備の設計をやっていたひと、造園をやっていたひと。それぞれいろんなきっかけで照明に出会ったひとたちが集まっています。
――シンガポールではどのような仕事を?
2008年に赴任しました。当時はまだマリーナ・ベイ・サンズもありませんでした。今もそうですが当時のシンガポールは建設ラッシュ。東京勤務だった頃に海外の案件を担当していたことなどがきっかけで、赴任することになりました。こちらでは都市計画のようなものから、ホテル、商業施設、オフィスビル、住宅コンドミニアムの照明デザインまで、照明に関わる幅広い仕事に携わっています。
都市計画の事例として、シンガポール政府からの依頼を受けて、ベイエリアやショッピングエリアなど中心街の景観を形づくる照明に関するマスタープラン策定を弊社で行いました。また、マリーナ・ベイ・サンズホテルに隣接する植物公園 ガーデンズ・バイ・ザ・ベイの照明デザインに私も参画しました。公園内には屋外施設もあるため、夜間の照明をデザインする仕事でもありました。どのエリアが、どの程度の明るさだったら、来訪者に理想のストーリーを体験してもらえるか。照明デザインは、「陰影をデザインする仕事でもある」ということを再認識しました。
来訪者の無意識をあやつるデザインのプロセス
――デザインを行う過程について詳しく教えて下さい。
ビクトリア・シアター&コンサート・ホールの事例でご紹介します。約100年間の歴史がある古い建物で、老朽化のためリノベーションが行われました。私も2009年から今年まで5年間携わりました。照明デザインのコンセプトは、“Old meets New”を伝えること。シンガポールでは貴重な歴史ある佇まいと、リノベーション後の新しさをハイライトするようデザインしました。
北欧は自然光をいかに取り入れるか、南国は遮るか
――国によって違いを感じますか?
特に中国のクライアントは、自分の建築をまわりで一番に目立たせることを好むことが多いですね。とにかく、周りより明るく奇抜に目立たせてくれと望む。香港や上海ならよいのかもしれませんが、パチンコ屋のように下品に明るくするのが適切でない立地にある場合は照明の数を減らしましょうと提案することも。こうした建築を取り巻く周辺環境を解釈しながらデザインを考えるマインドセットは建築を学ぶ過程で身につけたものです。
自然光に対する考え方も基本的には国によって異なります。たとえば、北欧では限られた自然光を建造物にどう入れられるかという視点でデザインします。一方、赤道直下などの南国では、暑さのしのぐために自然光をいかに遮るかという視点で考えます。その土地の立地、天候、そして経済状況も含めて環境です。照明もそれに対応させます。
生活の中に取り入れる照明の明るさの好みも異なります。ヨーロッパでは、レストランでもロウソクの光でステーキを食べたりします。肉がきちんと焼けているかどうかも分からないほど暗い場合もあります。スウェーデンの住宅を訪れたときも、ロウソクのような明かりで生活している家もありました。夕日やいわゆる間接照明などもそうですが、暖かみのある、いわゆる「色温度の低い」光が好まれます。白人は目の色素が薄いので光に敏感だとも言われています。
一方、東南アジアなど日照時間が長い地域では、冷たい白色の「色温度の高い」蛍光灯むき出しのところで食事をしてお酒を飲んだりします。日本では、障子や行灯など面で光る照明が日本らしいとされますよね。日本の多くの現代住宅は、天井にひとつ明るい蛍光灯がついていて、リビングをくまなく照らすような環境です。これは、私は知らない時代ですが、親やその前の世代の方々が戦後貧しい時代を裸電球で生活してきたので、明るいことが豊かだというマインドセットがあることに一因があるように思います。
――海外での仕事という面で苦労する部分もあると思うのですが。
たとえばインドで高層ビルの案件にたずさわっていたときに、予算を使い切ってしまいビル自体の建設が途中で止まったなんてことがありました。また、これはどの国でもあることですが、施工会社とのコミュニケーションに苦労します。日本では考えられないことが起こる。器具の設置作業を指示通りにやってくれなかったりするんですよね。慣れるまではいらいらしていましたが、むしろそれを楽しむ余裕がないとストレスを感じるのではないでしょうか。デザインに対する妥協は好きではありませんが、できるところはしないと作業が進んでいかないこともあります。海外ではそのバランス感覚が必要です。
――照明デザインのトレンドを教えて下さい。
発光ダイオード、いわゆるLEDがこれまでの照明をすべて置き換えようとしていることでしょうか。省エネにもなりますので、ランニングコストを削減したいクライアントにとっては魅力的です。企業イメージを良くするために照明はすべてLEDを、なんていうことを求められることがあります。しかし、われわれは従来の白熱灯、蛍光灯ほか様々な光を使い分けて提案するようにしています。白熱灯の光と比べてLEDの光は、食べ物のおいしさや女性の肌の美しさを表現することには向いていない。光源それぞれに特性がありますから。その環境に適した光をデザインすることがわれわれの任務です。
――デザイナーとして今後の展望は?
3.11の東北での震災後、色々な方が色々なことを考えたように、私も照明デザイナーとして何ができるかを考えました。被災地の方々が、電気の無い寒い中、暗く不安な夜を過ごしているのだろう。そこが明るいだけでも少しは安心できるのではないかと、太陽パネル内蔵のLEDが発光するキャンプ用のランタンを被災地に送ったこともあります。この震災がきっかけで、自分の照明デザイナーの社会的役割を考えるようになったと思います。
光というのはエネルギーが変換されて得られます。照明にはエネルギーが必要、つまりお金のかかることです。フィリピンのマニラを訪れたとき、夜間に空港からシティーエリアに向かっていたのですが、その道のりにスラム街があり、ものすごく暗くて、いかにも治安が悪そうでした。街が暗いと、犯罪などが起こりやすく治安が悪くなり、ますます貧しくなってしまいます。そういう場所には必要なだけの光があればなと思います。全ての場所を明るくすればよいということではありませんが、こういった負の悪循環は光でも打開できるのではと考えています。
いま照明デザイナーを起用するクライアントは、主に経済的に豊かな人や会社です。しかしそうでないひとたちにも自分の力を還元していきたいと思っています。そういった考えの中で将来やらなければと考えているのが、災害が起こった地域や暗く治安の悪い地域などに光を届けるボランティア。昼は太陽が分け隔てなく光を届けてくれます。夜もそうなれば素敵だと思うのです。
照明デザイナー 服部祐介
1980年、東京都生まれ。東京工業大学工学部建築学科卒。同大学院総合理工学研究科人間環境システム専攻にて環境心理学を研究。工学修士。2006年Lighting Planners Associates に入社し2008年からシンガポール事務所にて照明デザインに従事。主な担当プロジェクトに、表参道アカリウム、ヒルトン東京、Gardens By the Bay、ION Orchard、Tang Plaza ファサード改修、Peranakan Museum, Victoria Theatre and Concert Hall、CapitaGreen、Aman Shanghaiなど。その他、住宅プロジェクトも担当する。国際照明デザイナー協会(IALD)会員