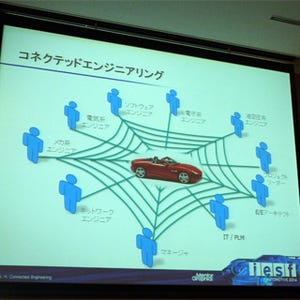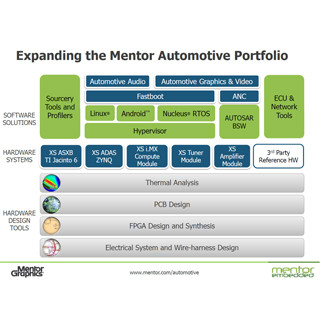2014年12月に名古屋と東京の2都市で開催されたメンター・グラフィックス・ジャパン主催の自動車業界向けのテクニカルフォーラム「IESF 2014」において、メンターが提供する「Capital」をハーネス開発のコアツールとして開発の上流から活用するフロー「MAZDA Generative Flow」の構築とマツダのエレキシステム開発の今後の取り組みについて、マツダの才上宗敏氏が講演を行った。
才上氏はマツダの車両開発本部電子開発部に所属し、車両のエレキ開発を担当する。部内の各グループは、「つながる」をキーワードに、あらゆるネットワークを駆使した情報活用によって「最高の価値」を「最安」でユーザーに提供する事を目指し、マツダのエレキ開発を進めている。そんなマツダに息づいているのは不屈のチャレンジ精神であるとし、「誰もが無理だと思うことに敢えて挑む。どんな困難や大きな壁に当たっても、決して諦めずに夢を追いかける。それが広島の、そしてマツダの精神。新しい技術は挑戦からしか生まれない。マツダはそんな信念を持って、クルマをつくり続けています」と挑戦し続けるマツダの姿勢を語った。ちなみに才上氏は、現在ではすっかりデファクトスタンダードとなった「引き上げ方式」のパワーウィンドウスイッチを世に送り出した人物でもある。
マツダのR&Dでは、その全開発領域において、目指す姿の実現に向けてどのように取り組んでいくかを一望できる「鳥瞰図」として描き出している。ABSシステム、ワイパーシステムなどのエレキシステムの整合を取りながら相互に接続するのがワイヤハーネスであり、才上氏はその設計、製造を「エレキをつなぐ仕事」と呼び、この「つなぐ」領域の革新に対してもエレキシステム開発の鳥瞰図を描いて継続的に取り組んでいる。
クルマの高機能化に伴ってシステムの数が増えると、その整合取りの数が二次曲線的に増加し「つなぐ仕事」の難度も急上昇することから、従来型の開発手法のままでは手に負えなくなる。また、開発現場では依然としてデジタル化されてない情報が横行し、プロセスの流れも組織間で分断され、結果として、情報の伝達ロス、伝達ミスが多発している。このことから、情報をデジタル化するだけにとどまらず、デジタル化された情報を自動処理できる環境、後工程での手戻りを解消するために上流でのコンカレント開発、さらには設計領域を超えた連携が求められると才上氏は整理した。
そこでマツダは、ツールとプロセスの両方から解を求め、鳥瞰図に描いた夢の実現に向けて、ワイヤハーネスの自動生成機能が1つの特長であるメンターのCapitalを核にした「MAZDA Generative Flow」を構築した。才上氏によると、Capitalのツールとしての方向性がマツダの求める鳥瞰図の方向性と一致したことに加え、エレキ開発領域のプラットフォームツールとしてクルマ1台のコンカレント開発を支援していくポテンシャルを感じたことが、メンターとの共創関係によるCapitalをコアとしたツールとプロセスの進化に取り組む決断の決め手になった。
才上氏によるMAZDA Generative Flowの「特長」は次の5つ。
- 同一CAD(Capital)で上流から下流まで一気通貫できるシームレスなデータフローの実現
- システム設計者が自らCapitalを使ってシステム図を作成し、後工程ではシステム結合した車1台分のデータを使って自らシステムの整合性を確認
- Capitalの自動生成機能を利用し、システム図から半自動で部品外部接続図を生成
- CADの中に設計ルールやノウハウを組み込み、設計者にとって使いやすいツールであり続ける
- Capitalの自動生成機能そのもの
CapitalをコアにしたMAZDA Generative Flowの構築にあたっては、すでに世界標準に近いソリューションがある領域にはマツダ独自のプロセスツールを作らないというアプローチで臨んだことで、新たなムダの発生を抑制しつつ、つなぐ仕事の効率化を実現できたと才上氏はまとめた。その取り組みとして、マツダ90年の開発歴史の中で伝統として受け継がれてきた設計者にとっては聖域とも言える図面の書き方までもCapitalに合わせて変更した。MAZDA Generative Flowの運用は始まったばかりではあるものの、習熟期を終え、将来さらなる削減効果を出せる手応えを感じているとのことであった。
最後に才上氏は、「クルマ1台分のコンカレントな開発」と「自動設計領域の拡大」をマツダの目指す姿とし、衝突安全、EMC、燃費、各種電波の受信性能などのCapital外の領域との連携拡大と形状設計、バリエーション設計、コスト削減、エレキアーキテクチャ設計などへの自動設計の拡大を進めていくつもりだと語った。つなぐ仕事の効率化をさらに拡大し、鳥瞰図に描いた「在るべき姿」を実現するために、共創の輪を広げ、非競争領域のムダ排除に取り組んでいきたいとし、共創への参画を参加者に呼びかけた。