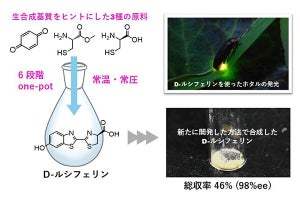突然の心停止は頻繁に起きる。どこで心停止したかによってその人の命運は左右される。自分の家族の心停止を目撃した場合には、知人や同僚らの目撃に比べて、早期の119番通報や心肺蘇生を含めた適切な一次救命処置を実施する確率が低く、結果的に患者の生存率が悪いことを、金沢大学医薬保健研究域医学系の田中良男(たなか よしお)協力研究員、前田哲生(まえだ てつお)助教、稲葉英夫(いなば ひでお)教授らが示した。
国内で発生した55 万人の病院外心肺停止患者データを解析した結果で、この影響は家族の人数が減少する日中に顕著だった。家族が一人で心停止を目撃した状況を想定した新しい蘇生教育の重要性や、患者の家族が心肺蘇生の実施をためらいがちであるという事実を社会が認識し、教育された隣人が迅速に助けを差し伸べるシステムを導入、普及させるよう、研究グループは訴えている。11月13日付の欧州蘇生協議会の医学誌Resuscitationオンライン版に発表した。
2005年~09年に国内で発生した55万人の院外心停止患者に関する総務省のウツタインデータを基に、目撃者との患者との関係を調べた。データがはっきりしていた14万人の患者を、目撃者によって「患者の家族」「患者の友人や同僚」「その他」に分けた。そのうえで、各グループ間での「口頭指導の成功率」「心肺蘇生の実施率と実施までの時間」「119 番通報までの時間」「機能良好1カ月生存率」を日中と夜間で解析した。
心停止を目撃したのが「患者の家族」であった場合には、自分の家族が心停止しているにもかかわらず、心肺蘇生の実施率は低く、心肺蘇生の開始や119 番通報も遅れ、生存率が最も低いことが明らかになった。これらの傾向は夜間より日中に著しかった。一方、最も生存率が高くなるのは「患者の友人や同僚」が心停止を目撃した場合で、やはり「持つべきものは友」といえそうだ。
患者の家族が心肺蘇生などの適切な対応をできない理由として、精神的動揺など心理的な要因や、助けになる人がそばにいないなどの複合的な要因が考えられる。また、少子高齢社会の日本では、日中に自宅にいる家族の人数が減る傾向にある。研究グループは「日中に高齢者夫婦のみが自宅にいる場合が多くなり、心停止に対する適切な対応ができないという問題を考慮すべきだ」と指摘している。
さらに稲葉英夫教授らは「『本質的に患者の家族は心肺蘇生の実施をためらう』という事実を社会全体が認識して、自宅で家族が心停止した場合を想定した新しいシナリオなどを用いた心肺蘇生法の講習会や、通報時に通信指令員が行う心肺蘇生の口頭指導の工夫が必要だろう。各国の蘇生に関するガイドラインに影響を与える結果だ」と指摘している。
|
関連記事 |