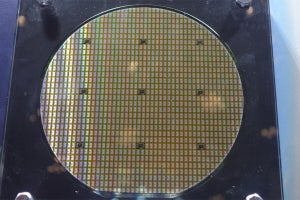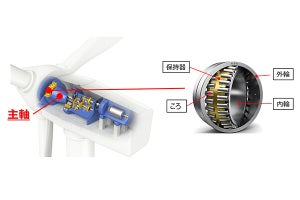一般的な切り絵のイメージを覆す作品を生み出している切り絵作家・福井利佐。インタビュー前編では、中島美嘉や水道橋博士といったアーティストとのコラボレーション作品の制作秘話や、福井さんの作家としての方向性を決定づけた卒業制作について、独特な"線の表情"が生まれたきっかけなどについて話を聞いた。後編となる今回は、切り絵の制作方法や、福井さんにとっての「切り絵」の面白さについて語ってもらった。
――(福井さんの切り絵に関して)以前に比べて、最近の作品は線が変わってきたように思います。
昔のほうがデザイン的なのかもしれません。今の作品は、より写実的というか。そのものをちゃんと描こうと思ったり、本質を追い求めていくうちに、そうなっちゃったんですよね(笑)。
――「本質」とは?
人間を描く場合は、その人の内面とかも絵から伝わるように、ということでしょうか。動物だったら、野性的な雰囲気とか、その暮らしから立ち上る匂いとか。そういうものを絵の中に取り込むことができているか、ということを考えならが作っています。
また、物理的に作品のサイズが大きくなってることもあり、線が多くなったり、表現が緻密になったりしています。昨年のポーラ ミュージアム アネックスの個展で発表した「Life-sized」というシリーズは、自身最大の作品となりました。
――黒い線から白い線へ。「Life-sized」では"白い切り絵"とその展示方法がとても斬新でした。白い線を切るアイデアは、どのように発想されたのでしょうか?
やはり「黒」のイメージが強い切り絵において、「白を切る」というのは、切り絵をやっている人にとっては必ず通る道ではないでしょうか。でも、あまり成功例を見たことがなかった。もちろん私も、ずっと白でやってみたいと思っていましたし、黒という色の力もありますが、私の作品は「線が強い」と言われることが多いので、そのイメージを一度取り払ってみたかったんです。同じ線を白で切ったらどうなるのだろう、と。そして会場の下見をした際に、そこに広がる白い空間を見て「ここでならできる!」と思ったんですよね。
でも、ただの白い紙を切るだけでは面白くないので、色紙を白で着彩し、切ったあとは色は付けない。さらに、展示を立体的にしようと考えました。浮かんでいるかのように、作品を展示空間の中に立たせたい。作品の裏側はもちろん、線の断面やそこに落ちる影、そういうものを見せたかったんです。
――実際にやってみて、手応えはどうでしたか?
白い作品として自分のやりたかったことは実現できましたし、古典的で民芸的な切り絵のイメージを覆した、"現代的な切り絵"を提示することができたと思います。
|
|
|
|
|
ポーラ ミュージアム アネックスで開催された、福井利佐「LIFE-SIZED」展示風景(2013年8月9日~9月8日) |
||
――福井さんにとって、大きな意味をもつ個展になりましたね。そういえば、以前、福井さんの作品が映像になったこともありました。
映像は大変でした(笑)。でも、メディアやジャンルは問わず、面白ければなんでもいい。切り絵がうまくいかせれば、映像でも立体でも。そのあたりを割とフランクに考えられるのは、グラフィックデザイン出身の強みだと思っています。