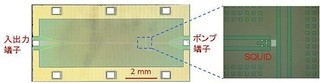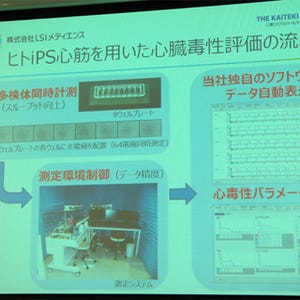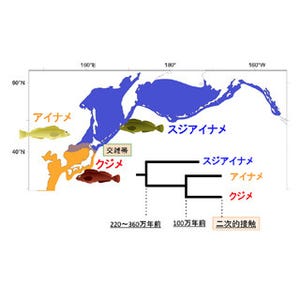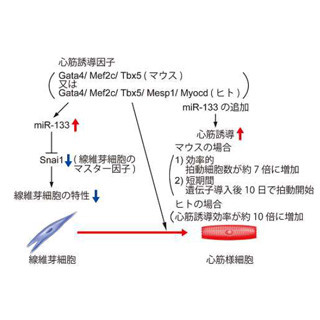東京医科歯科大学と科学技術振興機構(JST)は8月16日、マウスをモデルとした実験で体外に取り出して培養した小腸上皮細胞を消化管(大腸)へ移植することに成功したと発表した。
この成果は、同大学大学院医歯学総合研究科 消化管先端治療学の中村哲也 教授、同 消化器病態学分野の渡辺守 教授、同 水谷知裕 特任助教、同 福田将義 医員らの研究グループによるもので、米科学誌「Genes & Development」にて発表された。
同研究グループは2012年に、大腸の最も内側にならぶ上皮組織の幹細胞を体外で増やし、移植することで傷害を受けた大腸の修復が可能であることをマウス実験で確認していた。しかし、小腸について同様に体外で増やした細胞の移植による上皮組織の再生が可能かどうかはわかっていなかった。
今回の研究では、肛門付近の大腸に上皮の欠損を生じる大腸傷害マウスモデルを作成し、全身で蛍光を発する別のマウスから小腸上皮細胞を取り出して増やした後に、大腸傷害マウスへ移植。その後経過を観察して体外で増やした小腸上皮細胞を別のマウスへ移植し上皮組織が再生可能であるか、移植片内で再生する細胞はいかなる性質を示すのかを調べたという。
大腸傷害マウスを調べたところ、移植直後から蛍光で識別できる移植小腸細胞が大腸組織に接着して新しい上皮を形成し、2週間後には、移植細胞が生体内で分裂・増殖を繰り返すことが判明。4週間あるいは4カ月経過後にも、小腸細胞が移植を受けたマウスの大腸に安定して組み込まれていることがわかり、移植細胞が体内で上皮組織を再生する幹細胞として機能することが確認されたという。
次にこの移植片を詳しく調べたところ、増殖を繰り返す細胞群とともに通常の小腸上皮に含まれるすべてのタイプの細胞を含むことから、移植された細胞が個体内で小腸型の上皮幹細胞として機能していることがわかったという。それに加え、移植片内に通常小腸に見られ大腸には見られない特徴が含まれること、その細胞が示す遺伝子パターンも大腸とは明らかに異なることもわかり、実際に小腸型上皮幹細胞に特徴的な形態と機能を持つ細胞を確認することができたとのこと。
同研究グループは、これらの結果から、「体外で増やした小腸上皮幹細胞が、たとえ自身が由来する小腸と異なる(大腸)環境に長期間おかれても、小腸型幹細胞としての性質を維持できることも明らかとなった」と結論付け、今後この発見がさまざまな細胞を利用する消化管上皮再生医療技術の基礎となることが期待されるとしている。