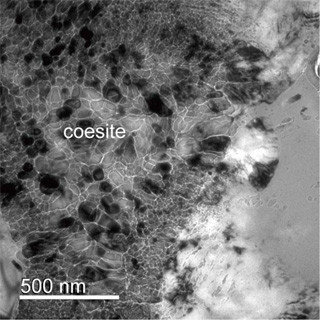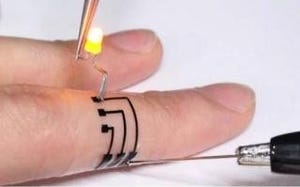東北大学は7月14日、半導体細線構造に印加する磁場方向を変化させることにより、量子干渉効果が最大となる角度からスピン軌道相互作用を直接決定できる検出法を確立したと発表した。
同成果は、同大大学院 工学研究科の新田淳作教授、好田誠准教授、佐々木敦也修士課程大学院生、国橋要司博士(現NTT物性科学基礎研究所)、ドイツ・レーゲンスブルグ大学のKlaus Richter教授らによるもの。詳細は、英国科学雑誌「Nature Nanotechnology」のオンライン版に掲載された。
スピン軌道相互作用は、電場を磁場に変換する相対論的な効果である。さらに、固体中では真空中に比べ、スピン軌道相互作用の効果が強くなり、固体物理のさまざまな分野で重要な役割を果たす普遍的な効果とされている。また、磁場を用いることなく、電場で電子スピンを生成・制御・検出することが可能となるため、スピントロニクスに重要な役割を果たすことが期待されている。
しかし、これまでのスピン軌道相互作用の評価には大きなバラつきがあった。半導体2次元電子ガス中の電場に起因したRashbaスピン軌道相互作用と、半導体構成原子のミクロな電場に起因したDresselhausスピン軌道相互作用の2つが存在するため、2つ以上の未知なパラメータを用いて実験データを解析する必要があったためである。
一方、この2つのスピン軌道相互作用の強さを制御し等しくすることができると、スピン緩和の抑制された永久スピン旋回状態が実現されるため、キャリア濃度を決定するホール測定のような、信頼性が高く、かつ簡便なスピン軌道相互作用の評価方法の確立が望まれていた。
今回、半導体細線構造に面内磁場(半導体2次元電子ガスに平行な磁場)を印加することにより、量子干渉効果の振幅が最大となる面内磁場方向から、実験データを解析することなく、直接Rashbaスピン軌道相互作用とDresselhausスピン軌道相互作用の比を求めることができる信頼性の高い計測法の開発に成功したという。
この成果について研究グループは、半導体や磁性体を用いたスピントロニクスだけでなく、スピン量子情報やトポロジカル絶縁体、マヨラナフェルミ粒子など、スピン軌道相互作用が重要な役割を果たす研究分野に、大きなインパクトをもたらすことが期待されるとコメントしている。