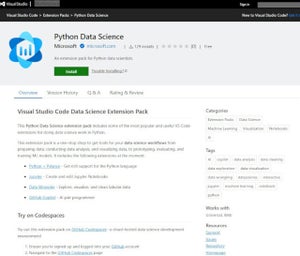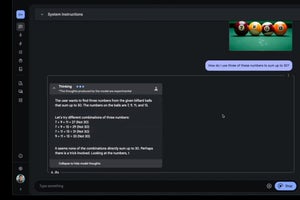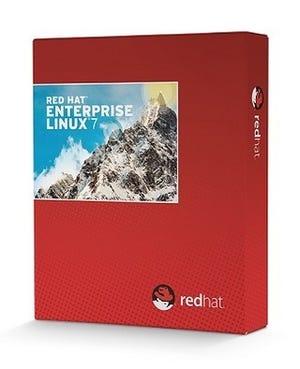レッドハットは7月10日、同社が提供するエンタープライズ向けLinuxディストリビューションの新版「Red Hat Enterprise Linux 7」(以下、RHEL7)をリリースしたことを発表した。
|
|
|
レッドハット 代表取締役社長 廣川裕司氏 |
RHEL7は、3年半ぶりに行われたメジャーアップデート。Linuxカーネル3.10を採用している。RHELへ取り込むにあたっては「1万7000以上のバグをフィードバックした」(レッドハット 代表取締役社長 廣川裕司氏)と言い、エンタープライズユーザーからの信頼に足るOSとして仕上げている。
発表会に登壇した廣川氏は、RHEL7に関して、「エンタープライズOSを再定義。"俊敏なIT"を実現する最新OS」というコンセプトを紹介。Linuxコンテナと呼ばれる機能により、物理/仮想サーバ、プライベート/パブリッククラウドなどの環境を問わず、容易にかつ軽量サイズでアプリケーションを移設できることを強調した。
アプリケーションの移設が容易になるLinuxコンテナ
RHEL7の目玉となるLinuxコンテナは、Dockerの正式サポートにより実現された機能だ。
Dockerは、Linux間でのアプリケーションの移設を容易にするプラットフォーム。一般的な仮想化技術では、OSも含む実行環境をまるごとパッケージ化するが、Dockerでは、アプリケーションや依存関係の情報だけをパッケージ化するため、軽量で可搬性が高いという特徴がある。
|
|
|
米Red Hat プリンシパルプロダクトマネージャーの鶴野龍一郎氏 |
広く普及しているRHELの最新版(もしくはDocker)さえ導入されていれば、アプリケーションを容易に移設できるというのは大きな利点。開発環境から本番環境へのリリースや、ハイブリッド環境での運用がこれまで以上に柔軟になると、ユーザーからの期待が高いという。
ただし、米Red Hat プリンシパルプロダクトマネージャーの鶴野龍一郎氏は、「ミッションクリティカル分野での本格的な活用は様子を見ながら進めてほしい」と注意を促す。
「Linuxコンテナを管理できるツール『Cockpit』が、Red Hat Enterprise Linux Atomic Hostというエディションでリリースされる予定。そう遠くないうちにリリースできるはずなので、今はLinuxコンテナを試しておいて、Cockpitが利用できるようになってから本格導入するかたちでも良いと思う」(鶴野氏)
XFSで最大500TB、systemdで集中管理、パフォーマンスも大幅向上
RHEL7では、Linuxコンテナ以外にもさまざまな特徴がある。
例えば、Windowsとの相互運用性を高めるべく、Active Directoryとの連携が強化されたほか、デフォルトのファイルシステムをXFSに変更し、データ領域が500TBまで拡張可能になった。
また、データベースやWebサーバなど、用途に応じたパフォーマンスプロファイルが用意されたうえ、プロセスごとのパフォーマンスを可視化するツールや、チューニングするためのツールなども導入されている。プラットフォームの性能も向上しており、Javaのワークロードに関しては25%の高速化が実現されている。
そのほか、System V initに代わるデーモン管理ツールとしてsystemdを採用。プロセス、サービス、セキュリティなど広範囲の集中管理が行えるほか、サービス起動の優先度を設定することも可能になっている。System V initやLSBと互換性があり、既存のスクリプトをそのまま使えるという利点もある。
さらには、OpenLMIというリモート管理ツールを採用。システムのさまざまな情報をリモートで監視でき、スクリプトなどを通じて細かい管理が行える。
なお、レッドハットでは、RHEL7のリリースに際して、8月よりシステム管理者向けのトレーニングをスタートする予定。7月16日には、RHEL7の特徴を動画で紹介するWebセミナーも開催する。Webセミナーは事前登録制で、先着500名にはAmazonクーポン券500円分が配布される。興味のある方は、早めに登録するとよいだろう。