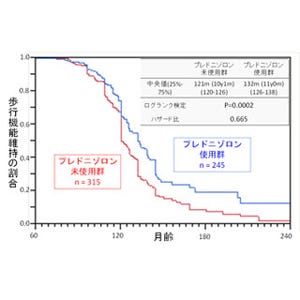東京大学(東大)は7月10日、X染色体上に存在するジストロフィン遺伝子の変異により引き起こされる遺伝性疾患である「デュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)」の症状がヒトに近いラットを作製することに成功したと発表した。
同成果は、同大大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 博士課程4年の中村克行氏(日本学術振興会特別研究員)、同大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻の藤井渉 助教、同大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 の山内啓太郎 准教授、同大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻の西原真杉 教授らによるもの。詳細は「Scientific Reports」に掲載された。
DMDは、新生男児約3500人に1人の割合で発症する病気で、ジストロフィン遺伝子からつくられるジストロフィンタンパク質が消失することで筋組織が脆弱化し、それによる筋力低下や運動不全、呼吸器機能低下ならびに心不全といった重篤な症状を示すことが知られている。
これまで、DMDの治療法開発に向け、マウスやイヌのモデル動物が用いられてきたが、DMDモデルマウスではヒトの症状に比べて軽度であり、イヌではヒトに類似した重篤な症状を示すものの、繁殖・維持に多大な労力が必要となっていることが課題となっていた。
今回、研究グループは繁殖・維持が容易なラットに注目し、新規ゲノム編集技術「CRISPR/Cas法」を用いてジストロフィン遺伝子に変異を導入することで、ジストロフィンタンパク質を消失したラットを作製したという。
有用性を検討した結果、正常ラットでみられる筋線維の細胞膜におけるジストロフィンタンパク質の発現がDMDラットでは消失しており、筋線維の破壊像や炎症細胞が多数現れる病変がみられたほか、筋力を測定するワイヤーハング試験において、DMDラットは正常なラットに比べて筋力が低下していることが確認されたとするほか、こうした筋組織の変性は横隔膜や心臓にも見られ、これらの症状はいずれもヒトのDMDでみられる典型的な病態に類似したものであることが示されたという。
また、DMD親ラットから子ラットにもこうした特徴が伝わるかどうかについて調べたところ、次世代の子ラットにおいてもジストロフィン遺伝子における変異が認められるとともに、親世代と同様なジストロフィンタンパク質の消失や筋線維の破壊像がみられたという。
研究グループでは、今回の成果を受けて、今後、このDMDラットがDMDの治療法開発研究において有用なモデル動物となることが期待されるとしている。